【完全版】老人の唸り声がうるさいと感じたときの原因とケア方法

高齢者と暮らしている中で、「老人の唸り声がうるさい」と感じた経験はありませんか?特に夜間や静かな時間に「んーんー」「うーうー」といった声が常に聞こえてくると、家族の睡眠に支障をきたすことも少なくありません。この記事では、そもそも「唸り声」はどんな声ですか?という疑問から始まり、その発声がなぜ起こるのかを詳しく解説していきます。
多くの場合、唸り声は無意識に発せられており、本人に自覚がないことも珍しくありません。また、「唸り声と認知症」の関連性にも触れながら、行動の背景にある心理的・身体的な要因についても考察します。老人が唸るのはなぜか、その理由を理解することで、ただの「うるさい音」ではなく、何らかの訴えやサインとして捉えることができるようになります。
声が漏れる、呼吸とともに唸る、唸り声が睡眠中に続くなど、症状の出方は人それぞれ異なります。本記事では、その多様なケースに対応するための原因分析と具体的な対応策をわかりやすく紹介していきます。
 よーかん
よーかん家族のストレスを少しでも軽減し、本人にとっても安心できる環境づくりのヒントになれば幸いです!
- 老人の唸り声がなぜうるさく感じられるのか、その原因や背景を理解できる
- 唸り声と認知症や身体的・心理的な問題との関係性について把握できる
- 無意識に出る唸り声に対して、家庭で実践できる具体的な対応策がわかる
- 医療機関や介護の専門職に相談するタイミングや判断のポイントを学べる
老人の唸り声がうるさいと感じたら


- 「唸り声」はどんな声ですか?
- 唸り声が無意識に出る理由とは
- 唸り声と認知症の関連性について
- 「んーんー」「うーうー」と常に声が出る訳
- 老人が唸るのはなぜ?主な原因とは
「唸り声」はどんな声ですか?


唸り声とは、日常生活の中ではあまり意識されないものの、聞く人に強い印象を与える独特な音声表現です。一般的には「うーうー」「んーんー」といった低くこもったような音であり、力が入ったときや不快感、緊張、痛みなどを感じた際に自然と発せられることがあります。人によっては言葉にならない感情や身体的不調を表す手段として現れることもあるでしょう。
これらの唸り声は、話し声とは異なり明確な意味を持たないため、周囲の人にとっては「何か不満があるのではないか」「具合が悪いのではないか」といった漠然とした不安を引き起こしやすくなります。また、家族や介護者がその声に慣れていない場合、夜間の静かな時間帯に突然聞こえると、精神的なストレスや不眠の原因になることも少なくありません。
唸り声は状況や個人によって幅がありますが、共通する特徴として、言語的な意味よりも「生理的・情動的な表出」である点が挙げられます。例えば、痛みを我慢しているとき、寝苦しさを感じているとき、何らかの不安が内面にあるときに自然と漏れる声として聞こえてきます。特に高齢者では、発声や感情表現の機能が年齢と共に変化するため、唸り声が増える傾向にあるのです。



ただし、これが「うるさい」「不快だ」と感じられる場合もあるため、家族や介護者としては、単なる騒音として捉えるのではなく、その裏にある本人の訴えや身体・心理の状態に目を向けることがポイントです!
唸り声が無意識に出る理由とは


無意識の唸り声が出る理由には、いくつかの生理的・心理的背景があります。高齢者に多く見られるこの現象は、本人にその自覚がないことがほとんどであり、指摘しても「そんな声は出していない」と返されるケースが多々あります。これは決して否定しているわけではなく、本当に気づいていないという状態です。
主な原因としては、脳の抑制機能の低下や、筋肉・神経系の老化が挙げられます。通常、人は感情をコントロールし、無意識の声や動作を抑える働きをしていますが、加齢によってこの機能が弱まると、意識せずとも声が漏れるようになります。特に脳の前頭葉が関与する「行動の制御」が弱まることで、感情がそのまま身体反応として現れやすくなるのです。
また、加齢によって発声器官の筋肉が衰えると、喉のコントロールが効きづらくなり、喉奥から「うー」「んー」といった音が自然と漏れる場合も。これは力を入れたときや、体勢を変えるときに顕著に現れることもあります。
さらに、心理的な要素も無視できません。何もしていないとき、ふと過去の記憶がよみがえったり、孤独や不安が心の中で膨らんだりしたときに、無意識にそれが唸り声として現れることがあります。こうした声は意図的ではないため、本人も止めることができず、周囲は対応に苦慮することになってしまいがち。



単に「うるさい」と片付けず、「何か伝えようとしているのかもしれない」と捉える視点を持つことが、支える側に求められます。
唸り声と認知症の関連性について


唸り声は認知症と深く関係している可能性があります。特に進行期から後期にかけての認知症では、言語による表現が難しくなり、代わりに唸り声や意味のない言葉で感情や不快感を伝えるようになることも。これは、言語中枢が損傷され、適切な言葉が出にくくなるためです。
認知症の周辺症状(BPSD)には、不安、混乱、興奮、徘徊、幻覚などが含まれますが、唸り声もその一つとして表れることがあります。本人は何かに困っていたり、痛みや不快感を感じていたりしても、それをうまく言葉で伝えることができません。結果として唸るという行動が唯一の「SOS」の手段になっているケースがあるのです。
また、唸り声は昼夜を問わず出ることがあります。特に夜間に唸り声が目立つ場合、認知症に伴う「夜間せん妄」の可能性も考えられます。これは、日中と夜の区別がつきにくくなり、夜になると不安や興奮が強くなってしまう現象です。家族の睡眠を妨げる原因にもなり、在宅介護では大きな課題となります。
ただし、唸り声がすべて認知症に起因するとは限りません。身体的な病気や環境要因、薬の副作用など他の可能性も考えられるため、慎重な観察が求められます。まずは、唸り声の頻度、時間帯、きっかけなどを記録し、必要に応じて専門医やケアマネジャーに相談することが大切です。
言ってしまえば、唸り声は「本人なりの伝え方」であり、見逃してはいけないサインの一つです。



適切な理解と対応が、本人の安心と周囲の負担軽減につながります。
「んーんー」「うーうー」と常に声が出る訳


「んーんー」や「うーうー」といった声を高齢者が常に発している場合、そこには身体的・心理的・神経的な複数の要素が関係しています。このような声は、意味を持たないように聞こえるかもしれませんが、実際にはその人の内面にある「伝えたいこと」や「不快な感覚」が、言語以外の方法で表出されている可能性があるんですよね。
高齢者の場合、加齢に伴って筋力や発声機能が低下し、無意識のうちに声が漏れやすくなります。特に横になっている時間が長い人や、喉や胸まわりの筋肉が弱っている人では、力を抜いたときに自然と息が声になって漏れ出すことも。これは病的な症状ではなくても、周囲には「常に唸っているように聞こえる」という印象を与えます。
また、認知機能の低下が進行すると、自分の状態や置かれている環境が理解しづらくなります。その不安や混乱、孤独感が声として漏れ出していることも。例えば、言葉で「不安だ」と伝えられない代わりに、「んーんー」という声が出てしまうケースも。こうした発声には、コミュニケーションの代替としての役割も含まれていると考えられます。
さらに、過去の体験や記憶に関連した感情が、無意識に声となって現れることもあります。多くの時間を静かな環境で過ごす高齢者は、頭の中で思考や回想がめぐり、その中での感情が発声に繋がることもあるのです。
いずれにしても、これらの声は「意味がないもの」「ただの癖」とは言い切れません。背景には身体的疲労、精神的な不安、神経の変化といった複雑な要素が絡んでいる場合があります。だからこそ、まずはその発声が本人にとって苦痛を伴っていないか、不快のサインではないかを観察し、必要であれば医療や福祉の専門家に相談することが重要です。



認知症のおばあちゃんが「うーうー」と声を出すとき、そばで話を聴いてほしい、トイレに行きたい、座ってて疲れたなどなど、色んなことが考えられるんですよね。不安や不快が解決すると、声がおさまることがよくあります。
老人が唸るのはなぜ?主な原因とは


高齢者が唸り声を出す場面には、いくつかの主要な要因が関係しています。唸る行動は単なる癖ではなく、身体や心、脳の状態を反映する重要なサインとしてとらえることが必要です。
高齢者は関節痛、腰痛、便秘、胃の不調など、慢性的な不快感を抱えていることが多くあります。これらの症状は、自覚していても明確に言葉で説明することが難しい場合があり、そのかわりに唸り声という形で外に現れることがあります。特に寝たきりの方や、動作が制限されている方では、この傾向が顕著になるでしょう。
次に、精神的・感情的な要因があります。不安や寂しさ、混乱などの感情をうまく表現できないときに、人は非言語的な方法でそれを表そうとします。唸り声はその一つであり、見知らぬ環境に置かれたり、日常生活に安心感がなかったりすると、その不安感が唸りとして表れることも。
さらに見逃せないのが、認知機能の低下による影響です。認知症をはじめとする脳の変性疾患が進むと、言語による意思表示が困難になり、行動や音声で代替しようとする傾向が出てきます。特に、思考の混乱や場所・人の認識が曖昧になる場面では、唸るという行動が頻繁に見られるようになります。
また、環境の変化や生活リズムの乱れが唸り声の引き金になることも。慣れ親しんだ生活から急に施設へ移った場合や、昼夜逆転が続いた場合などは、精神的な混乱や身体的不調を招き、それが唸り声として現れることもあります。
このように、唸り声には単一の原因ではなく、複数の要素が重なり合っているケースがほとんどです。本人の状態を把握し、変化があれば医療機関での診察やケアマネジャーへの相談を行うことが、適切な支援に繋がります。



唸り声は見過ごせない「声なき訴え」であるという認識を持つことが、家族や介護者にとって大切な視点です!
老人の唸り声がうるさいときの対応策


- 呼吸時に唸る原因とは何か?
- 唸り声が睡眠中に出る場合の対処
- 声が漏れる現象の医学的な背景
- 環境調整と生活習慣でできる工夫
- 専門職や医療機関への相談が必要な場合
呼吸時に唸る原因とは何か?


呼吸時に唸るような音が聞こえる場合、単なる癖や無意識の発声では済まされないことがあります。特に高齢者でこのような症状が見られる場合は、身体の内部、特に呼吸器系に何らかの異常があるかもしれません。唸るような呼吸音は、医療の現場では「呻吟(しんぎん)」と呼ばれることもあり、病的なサインの一つとされることがあります。
唸り声のように聞こえる呼吸は、息を吐くときに空気が喉や気道の狭い部分を通る際に発せられる音であることが多いです。この現象は、呼吸器の機能が正常に保たれていないときに起こりやすくなります。例えば、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息、肺炎、または加齢に伴う肺活量の低下などが原因となることがあるでしょう。特に肺胞がつぶれやすくなる高齢者では、息を吐く際に声帯が閉じきらず、低いうなり声のような音が発生することがあります。
一方、呼吸機能そのものに問題がなくても、喉や声帯に関わる筋肉が衰えていたり、姿勢が崩れていたりすることで気道が狭まり、音が出るケースも。
こうした症状を見逃さず、特に日中の活動時よりも夜間や横になっている時に目立つ場合は、早めに医師に相談することが大切です。家庭では気づきにくい呼吸の異常でも、医療機関では聴診や検査によって適切な診断が可能です。



唸るような呼吸音は、本人にとっても負担になっている可能性があるため、早期の対応が望まれます。
唸り声が睡眠中に出る場合の対処
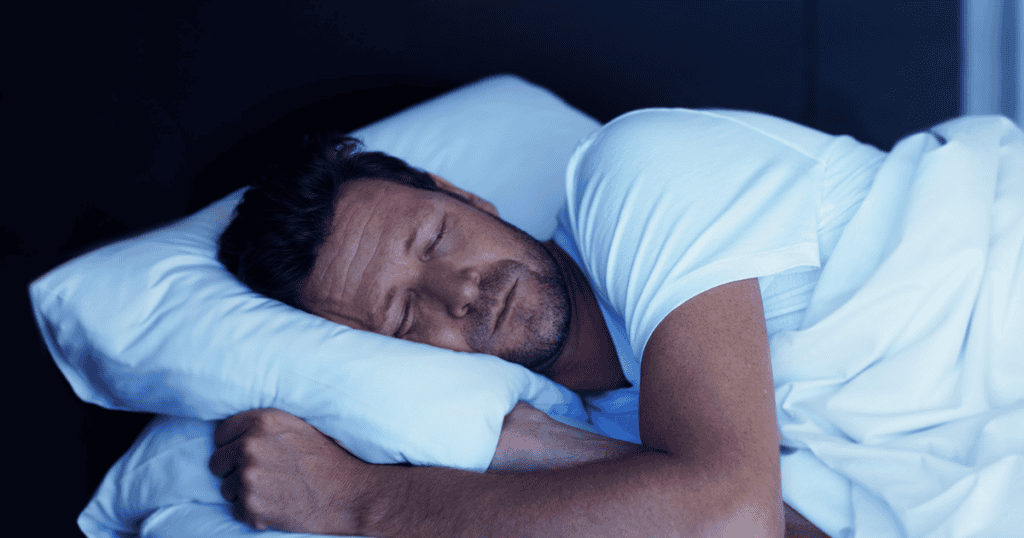
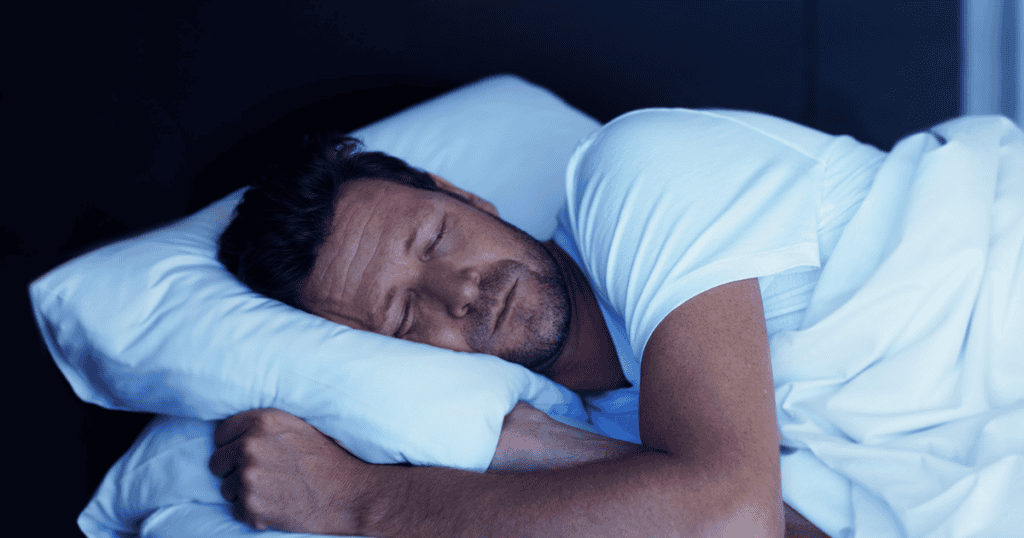
睡眠中に唸り声が出る場合、まず重要なのは「なぜ寝ている間に唸るのか」という原因の特定です。このような状態は、単なる寝言や癖では済まないケースもあり、本人が苦しんでいるサインである可能性もあるため注意が必要です。
多くは「カタスレニア」と呼ばれる睡眠障害が関係しています。これは睡眠中、特にレム睡眠の段階で「うーうー」といったうなり声を長く発する症状で、本人に自覚はなく、周囲の人が先に気づくことが一般的です。大きな問題を引き起こすことは少ないとされていますが、同居家族が眠れなくなるなど、生活に支障をきたすケースもあるでしょう。
また、睡眠時無呼吸症候群が原因で唸り声が発生することもあります。この場合は一時的に呼吸が止まり、その後呼吸を再開するときに声が出ることがあります。無呼吸による酸素不足は日中の眠気や集中力の低下につながるため、放置すべきではありません。
対処としては、まず睡眠環境を見直すことが有効です。寝室の温度や湿度、光、騒音などを整えることで、眠りの質が向上し、唸り声の頻度が減る場合があります。また、寝る前に温かい飲み物を飲むなどのリラックスできるルーティンを取り入れることで、精神的な緊張や不安を和らげる効果も期待できます。
ただし、症状が続く、または大きくなってきた場合は、睡眠専門の外来や耳鼻咽喉科、脳神経内科などで相談する方がよいでしょう。



家族としては、無理に唸り声を止めさせようとせず、見守りつつ記録を取り、専門家へ相談できる材料を準備しておくとよいでしょう。記録がある方が、医師も判断しやすくなりますよ。
声が漏れる現象の医学的な背景


高齢者に多く見られる「声が漏れる」という現象には、いくつかの医学的な背景があります。これは単なる発声の癖ではなく、身体的な変化や疾患が関与している場合があるため、注意深く観察することが重要です。
まず、加齢による声帯の変化が大きな要因です。年齢とともに声帯の筋肉や粘膜が萎縮し、声帯の閉じ具合が不完全になることがあります。この状態は「声帯萎縮」と呼ばれ、発声時にしっかりと声帯が閉じずに息が漏れるような音が混ざるため、結果として話していないときにも「うーん」「あー」といった音が無意識に出てしまうことがあります。
また、脳の機能が低下すると、声を出す制御がうまくできなくなることも。特に前頭葉の働きが弱くなると、発声や感情のコントロールが難しくなり、思わず声が漏れてしまう場面が増えることがあります。これは認知症の初期症状として現れることもあり、見逃してはならない兆候です。
さらに、神経系の疾患や過去の脳梗塞などによって、筋肉の動きや呼吸の調整がうまくいかなくなり、発声が不随意になるケースもあります。こうした背景があると、声だけでなく表情や動作にも変化が見られることがあるため、周囲の気づきが重要です。
声が漏れる現象は、生活にはすぐに影響を及ぼさないこともありますが、本人の精神的な負担や周囲の心配の原因になることがあります。場合によっては、音声訓練や嚥下リハビリ、薬物療法などの対処が必要になることもあるため、早めに耳鼻咽喉科や神経内科での評価を受けることをおすすめします。



色々な原因が考えられるので、異変を感じた場合は早めに医師に相談することで、適切な支援へとつながりやすくなりますよ。
環境調整と生活習慣でできる工夫


高齢者の唸り声が目立つ場合、その背景には生活環境の違和感や日常リズムの乱れが潜んでいることがあります。こうした状況を改善するためには、医療的介入に先立って、住環境や生活習慣を整える工夫が効果を発揮することがあるでしょう。
まずは、居住空間の「刺激の少なさ」と「安心感」が重要です。例えば、部屋が散らかっていたり、光や音が強すぎたりすると、高齢者にとっては不快や混乱の原因となり、唸り声として表出することがあります。これを防ぐために、照明はやわらかい暖色系のものを選び、物の配置を整理して、移動がしやすい動線を確保するとよいでしょう。また、壁にカレンダーや時計をかけて時間の感覚を保ちやすくしたり、家族の写真を飾って安心できる空間を演出することも有効です。
さらに、生活リズムを整えることも唸り声の予防に繋がります。朝は決まった時間に起き、日中は軽い運動や散歩などを取り入れ、夜はゆっくりと入浴し、リラックスした状態で就寝できるようにします。こうしたリズムが整うことで、不安や混乱が減り、睡眠の質も向上しやすくなります。
ただし、すべてを一度に変えるのではなく、少しずつ本人のペースに合わせて取り組むことが大切です。急激な変化は逆に混乱や不安を招くため、ゆるやかな調整を心がけましょう。加えて、テレビやラジオの音量にも配慮し、必要のない情報刺激を減らす工夫も役立ちます。



唸り声に悩んでいる家族にとって、「何ができるか」は見えにくいかもしれませんが、こうした環境と習慣の見直しは、すぐにでも始められる大きな第一歩になるでしょう。
専門職や医療機関への相談が必要な場合


唸り声が長期間続いたり、原因がはっきりしない、もしくは本人や家族の生活に明らかな影響が出ている場合は、専門職や医療機関への相談が強く勧められます。ただの癖や一時的な反応と思われがちな唸り声ですが、実際には体の不調や認知機能の低下など、重大なサインであることもあるからです。
最初の相談先としては、かかりつけの医師や地域包括支援センター、僕らケアマネジャーなどが適しています。医師であれば、身体的な疾患や認知症の初期症状などの有無を医学的に確認できます。ケアマネジャーであれば、日常生活や介護サービスの視点からアドバイスをもらえるため、家庭での対応がより現実的になるでしょう。
一方で、本人が受診を強く拒む場合や過去にトラブルがあった場合は、無理に連れて行こうとせず、家族側が医療機関に相談する方法もあります。受付で事情を説明すれば、医療側が本人への説明方法を工夫してくれることもあるでしょう。
何より大切なのは、唸り声が「本人の困りごとから発せられているかもしれない」という視点を持つことです。それを理解することで、家族の側も「どうすれば本人が楽になるか」を考える土台ができます。



誰かの助けを借りることは決して特別なことではありません。専門職と連携することで、本人にとっても家族にとっても安心できる暮らしに近づくことができます。ぜひ、僕らケアマネにも相談してくださいね!
老人の唸り声がうるさいと感じたときに知っておきたいこと
この記事のポイントをまとめます。
- 唸り声は「うーうー」「んーんー」といった低くこもるような音である
- 唸り声は意味のある言葉ではなく情動や不快感の表出である
- 聞く人に強い不安やストレスを与える場合がある
- 高齢者の唸り声は無意識で出ていることが多い
- 脳の抑制機能や発声器官の老化が無意識発声の一因である
- 唸り声は認知症の周辺症状の一つとして現れることがある
- 意思疎通が困難な高齢者にとって唸り声はSOSの手段になり得る
- 昼夜問わず唸り声が出る場合は夜間せん妄の可能性がある
- 常に声が出る背景には精神的不安や筋力低下が関与している
- 身体的不調や痛みが唸り声に現れるケースがある
- 呼吸時の唸りは呼吸器系疾患や声帯機能の低下が原因となる
- 睡眠中の唸り声は睡眠障害や無呼吸症候群によることがある
- 声帯萎縮や脳の機能低下により声が漏れる場合がある
- 環境の静穏性や生活リズムの見直しが唸り声軽減に効果的である
- 継続的な唸り声は医療機関や専門職に相談するべきサインである

コメント