【完全版】高齢者マークの追い越しは違反?交通ルールをやさしく解説

高齢ドライバーの増加にともない、「高齢者マークをつけた車を追い越してもよいのか?」という疑問を抱く方が増えています。特に「高齢者マークを追い越しても違反にならないのか?」や「高齢者マークの追い越しや追い抜きは禁止されているのか?」といった疑問を解消するためには、正しい交通ルールとマナーの理解が不可欠です。
この記事では、「高齢者マークの車を追い越してもいいですか?」と悩む方に向けて、道路交通法の観点からわかりやすく解説します。「高齢者マークの追い越しと追い抜き禁止の違い」や、「高齢者マークに対する幅寄せは違反になるのか」、「高齢者マークの車に割り込みをしても問題ないのか」といったテーマも取り上げます。
また、「障害者マークの車は追い越し禁止なのか?」や「聴覚障害者マークをつけた車は追い越してもよいのか」といった他の標識についても整理しながら、初心者マークをつけた車の追い越しに関する注意点にも触れます。
あわせて、「高齢者マークは何歳から表示が必要なのか」や「道交法における高齢者マークの扱い」、「優先道路での追い越しにおける注意点」なども詳しく紹介していきます。
高齢者マークに対する正しい知識を持つことは、安全運転だけでなく、思いやりある交通社会の実現にもつながります。
 よーかん
よーかんこの記事を通して、法律の理解とともに、他者への配慮を忘れない運転の大切さを学んでいきましょう!
- 高齢者マークの車を追い越す行為が法律で禁止されていない理由
- 「追い越し」と「追い抜き」の違いと注意点
- 高齢者マークへの幅寄せや割り込みが違反となるケース
- 障害者や聴覚障害者、初心者マークの車に対する配慮の必要性
- 高齢者マークの対象年齢と道交法における位置づけ
高齢者マークへの追い越しは法律で禁止か?


- 高齢者マークの車を追い越してもいいですか?
- 高齢者マークの「追い越し」と「追い抜き禁止」との違いを解説
- 高齢者マークへの幅寄せは交通違反になる?
- 高齢者マークの車に割り込みしても大丈夫?
- 道交法における高齢者マークの扱いとは?
- 高齢者マークは何歳から表示が必要?
高齢者マークの車を追い越してもいいですか?


結論から言うと、高齢者マークを付けた車を追い越すこと自体は禁止されていません。道路交通法では、高齢運転者標識(いわゆる高齢者マーク)をつけている車両に対して「追い越しをしてはいけない」とは明記されていないため、状況に応じて安全に追い越すことが可能です。
ただし、追い越し可能であるとはいえ、十分な注意と配慮が必要です。高齢者マークは、加齢によって認知機能や反応速度が低下している可能性がある運転者を示しています。そのため、急な進路変更やブレーキ操作、視野の狭さなどが影響し、思わぬ動きをすることもあります。特に右折のタイミングや車線変更の判断が遅れることがあるため、追い越す際には十分な車間距離を保ち、早めの合図や減速などを心がけましょう。
例えば、片側一車線の道路で高齢者マークを付けた車がゆっくり走っている場合、後方の車両が無理に追い越そうとすると、対向車線にはみ出す必要があります。このとき、前方の見通しが悪ければ非常に危険です。急いで追い越そうとせず、安全な場所やタイミングを見計らうことが大切です。
このように、追い越しは可能であるものの、高齢運転者への理解と譲り合いの気持ちを持つことが、安全運転に直結します。



交通ルールだけでなく、周囲への配慮という観点からも、マナーを大切にした行動が求めらるでしょう。
高齢者マークの「追い越し」と「追い抜き禁止」との違いを解説


言葉として似ている「追い越し」と「追い抜き」ですが、法律上ははっきりと定義が分かれています。この違いを理解しておかないと、意図せず違反になってしまうこともあります。
まず「追い越し」とは、前の車を進路を変えて追い抜き、その後再び元の車線に戻ることを意味します。例えば、片側一車線の道路で前の車を追い抜くために対向車線に出て、再び元の車線に戻る行為です。
一方「追い抜き」は、進路を変えずに横を通り過ぎる行為を指します。つまり、同じ車線や複数車線の道路で、右側や左側から単に前に出るだけの場合が「追い抜き」です。
高齢者マークのある車に対して「追い越し」は可能ですが、「追い抜き」に関しては注意が必要なケースがあります。たとえば、交差点付近や見通しの悪いカーブでは、追い抜きそのものが禁止されている場所も多く、無理に行えば交通違反となります。
このように、どちらの行為であっても「禁止されている場所・状況」で行えば違反になるため、標識や路面表示、交通状況をよく確認することが重要です。
さらに、「追い抜き禁止」と明示されている区間では、どんな理由があってもその場所で追い抜くことはできません。これは高齢者マークの有無にかかわらず全ての車両に適用されます。
つまり、追い越しと追い抜きの違いを正しく理解することが、安全運転と法令遵守の第一歩です。



高齢者マークの車に対しても、冷静な判断と配慮を忘れないようにしましょうね。
高齢者マークへの幅寄せは交通違反になる?


高齢者マークを付けた車への幅寄せは、交通違反に該当する場合があります。具体的には、「他の車両の通行を妨害するような幅寄せ行為」は、道路交通法第26条の2「通行の妨害禁止違反」に該当する可能性があるため注意が必要です。
幅寄せとは、他車両との距離を極端に詰めて進路変更を妨げたり、威圧的に接近する行為を指します。高齢者マークの車に対してこのような行動をとった場合、「嫌がらせ運転(いわゆるあおり運転)」と見なされ、厳しい処罰を受けるケースもあります。
例えば、高齢運転者が交差点で右折しようとしてゆっくり進んでいるとき、後ろから無理に接近してプレッシャーをかけるような幅寄せをすると、相手が焦って判断を誤る可能性もあります。このような行為は、事故のリスクを高めるだけでなく、モラル的にも非常に問題があります。
また、令和2年の道路交通法改正により、あおり運転に対する罰則が強化されたこともあり、意図的な幅寄せが発覚した場合、免許取り消しなどの重い処分が下される可能性があります。
一方で、運転中に不意に車線が狭まり、結果として幅寄せのような形になることもありますが、故意ではない場合は違反とは判断されにくいです。ただし、周囲の状況を確認せずに行った場合は、過失を問われる可能性もあります。
このように、高齢者マークの車に対する幅寄せは、違反行為と見なされるリスクが高く、決して許されるものではありません。



高齢者ドライバーに対しては、常に思いやりと余裕のある運転を心がけましょう!
高齢者マークの車に割り込みしても大丈夫?


高齢者マークをつけた車両に対して、無理な割り込みを行うことは原則として避けるべき行為です。法律上、すべての車両に対する無理な割り込みは、進路変更の妨害とみなされ、道路交通法に違反する可能性があります。特に高齢運転者は判断力や反応速度が低下していることもあるため、その行為が事故につながるリスクはより高まります。
割り込みとは、他の車両の前方に強引に入るような運転行為のことです。たとえば、車線変更時にウィンカーを点灯させず、すぐ目の前に車を入れるような場合がこれに当たります。高齢者マークを掲示している車に対してこのような行為を行った場合、相手のブレーキ反応が遅れ、追突などの事故が起きやすくなります。
さらに、令和2年の法改正により「あおり運転」が厳罰化されました。割り込みもその一種と見なされることがあり、悪質と判断された場合には、罰則の対象になることがあります。行政処分だけでなく、刑事罰を受ける可能性もあるため、慎重な運転が求められます。
もちろん、交通の流れや状況に応じて、安全なタイミングで車線変更をすることは問題ありません。ただし、相手車両との距離を十分に取り、ウィンカーを適切なタイミングで点灯するなど、安全運転の基本を守ることが重要です。
高齢者マークの車は、周囲の配慮を必要とする存在です。



焦りやイライラからくる割り込みは、思わぬトラブルの原因となるため、譲り合いの気持ちを忘れずに運転することが大切でしょう。
道交法における高齢者マークの扱いとは?


高齢者マークは、正式には「高齢運転者標識」といい、道路交通法に基づいて定められているものです。これは70歳以上の高齢運転者に対して、周囲にその年齢的特徴を知らせ、安全運転を促す目的で導入された制度です。
法律上、70歳以上の運転者が一定の加齢による運転機能の低下があると認められた場合、普通自動車を運転する際にこのマークを表示することが「努力義務」とされています。つまり、必ず表示しなければならないわけではないものの、できる限り表示するように促されているんですよね。
このマークを表示している車両に対しては、他の運転者が幅寄せや割り込みなどの妨害行為をすることが明確に禁止されています。これは道路交通法第71条の規定に基づき、「高齢運転者等標識自動車に対する妨害運転の禁止」として位置づけられており、違反すると反則金の対象になる場合も。
また、運転者がこの標識を掲げることで、周囲の車が配慮しやすくなるだけでなく、自らの運転への意識向上にもつながります。高齢になっても安全に運転を続けるための一つの手段として、社会全体がこの制度を正しく理解し、尊重することが求められるでしょう。
なお、マークのデザインは四つ葉のクローバーをモチーフとしたものに改良され、より親しみやすく、差別や偏見につながらないよう配慮されています。



道交法における高齢者マークの扱いは、単なる目印ではなく、交通安全に関わる重要な情報としての役割を果たしています。
高齢者マークは何歳から表示が必要?
高齢者マークの表示対象は、70歳以上の運転者です。ただし、これは義務ではなく、「努力義務」として位置づけられています。つまり、70歳以上であっても必ずしも表示しなければならないわけではありませんが、可能であれば表示することが望ましいです。
この基準は、道路交通法施行規則により明確に定められており、「加齢に伴い運転に支障があると認められる者」に対して、普通自動車を運転する際に高齢者マークの表示を推奨しています。75歳以上になると、更新時に「高齢者講習」や「認知機能検査」などの制度も加わり、運転適性がより厳しく問われるようになります。
例えば、70歳のドライバーが運転中に判断力や反応速度に不安を感じるようになった場合、自主的にマークを表示することで、周囲の配慮を受けやすくなるでしょう。特に市街地や狭い道路などでは、後続車や周囲のドライバーが高齢運転者の存在を意識し、より慎重な行動を取ることが期待されます。
ただし、このマークを掲示することで、まれに差別的な言動や不要な視線を感じるという声も。そのため、表示の有無は本人の判断に任されており、無理に掲示する義務が課されていない背景には、こうした事情も考慮されています。
このように、高齢者マークは70歳から表示できる制度ですが、その目的は「運転の妨げ」ではなく「安全のための配慮」です。



必要に応じて活用しながら、自分自身と周囲の安全を守る手段として前向きにとらえることが大切ですね。
高齢者マークへの追い越し時に守るべき配慮とマナー


- 障害者マークの車は追い越し禁止って本当?
- 聴覚障害者マークの車は追い越してもよい?
- 初心者マークの車も追い越していいの?
- 優先道路での追い越しルールを再確認
- 高齢ドライバーに配慮した安全運転のポイント
障害者マークの車は追い越し禁止って本当?


障害者マーク(身体障害者標識)を掲示している車に対して、「追い越しが禁止されている」と誤解されることがあります。しかし、実際には道路交通法において障害者マークの車両に対する追い越し自体が禁止されているわけではありません。
このマークは、身体に障害のある運転者が運転していることを周囲に知らせるためのものであり、他のドライバーに対して思いやりある運転を促すために設けられています。法的には「努力義務」の対象となっており、該当する運転者が自発的に掲示します。追い越しをしてはならないという明確な条文はありませんが、「幅寄せ」や「無理な割り込み」などの妨害行為は禁止されています。
例えば、追い越し時に不必要に接近して車間距離を詰めたり、割り込んで急ブレーキをかけるような行為は、障害者標識車両に限らず道路交通法上の違反となります。これが障害者マークを掲げた車に対してであれば、より悪質な妨害行為として見なされる可能性もあります。
つまり、障害者マークがついているからといって、すべての追い越し行為が禁止されているわけではないものの、安全性とマナーを十分に意識した行動が求められるということです。



無理な追い越しは避け、相手車両の特性を考慮した上で、適切なタイミングで追い越すよう心がけましょう。
聴覚障害者マークの車は追い越してもよい?


聴覚障害者マーク(正式には「聴覚障害者標識」)が掲示された車両に対して、追い越しをしても法的には問題ありません。ただし、この標識の意味や背景を理解しないまま安易に追い越しを行うと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
このマークは、聴覚に障害のある運転者がハンドルを握っていることを示すものです。運転そのものに必要な資格(補聴器装着などを条件にした運転免許)を有していることが前提となっており、安全運転を行う能力は十分にあります。ただ、クラクションが聞こえづらい、緊急車両の接近に気づきにくいなど、特定の場面での反応に制限があることは否めません。
このため、道路交通法では、聴覚障害者マークを掲示している車両に対して「幅寄せや割り込みなどの妨害行為をしてはならない」と明記されています。追い越し行為が、これらの妨害行為とみなされるような運転になった場合には、違反として処罰の対象になる可能性もあります。
追い越しそのものは許可されていますが、その際には相手車両との十分な車間距離を保ち、急な動きを避けるなど、通常よりも丁寧な配慮が必要です。



他者への理解と尊重が、最も重要な運転マナーだといえるでしょう。
初心者マークの車も追い越していいの?


初心者マーク(若葉マーク)をつけた車両を追い越すことは、法律上は認められています。ただし、その行動には慎重さと配慮が求められる点を見落としてはなりません。
初心者マークは、普通自動車の運転免許を取得してから1年未満のドライバーが表示することが義務付けられた標識です。このマークがあることで、周囲の運転者に対して「運転経験が浅いこと」を知らせ、安全に対する注意を促します。
法律上、初心者マークの車両を追い越すこと自体は違反ではありません。しかし、追い越しの際に無理な進路変更や、車間距離を詰めるような行為を行うと、初心者にとっては強いプレッシャーやパニックの原因になります。実際、運転経験の浅いドライバーが焦って誤操作を起こすケースも少なくありません。
また、初心者マークの車両に対する「幅寄せ」や「急な割り込み」は、道路交通法で明確に禁止されています。悪質な場合は、いわゆる「あおり運転」として重い罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
追い越す場合は、安全な間隔を保ちつつ、相手が動揺しないよう配慮した運転を心がけましょう。



単に前に出るだけでなく、お互いが安心して走れる環境を作ることが、結果的にはすべてのドライバーにとってプラスになります。
優先道路での追い越しルールを再確認


優先道路であっても、どんな場面でも自由に追い越しができるわけではありません。追い越しには一定の条件があり、それを無視すると違反や事故の原因になります。
優先道路における基本ルール
| 条件 | 追い越しの可否 | 補足 |
|---|---|---|
| センターラインが黄色の実線 | × 禁止 | 対向車との接触リスクがあるため |
| 見通しの悪いカーブ・坂道 | × 禁止 | 対向車が見えず危険 |
| 交差点の手前30m以内 | × 禁止 | 横から車両が出てくる可能性がある |
| センターラインが白の破線で見通し良好 | ○ 可 | 他車への配慮を前提とする |
| 複数車線の直線道路 | ○ 可 | 安全確認の上で実施 |
追い越し時の注意点
- 無理な追い越しはせず、後方の安全確認を徹底する
- 高齢者や初心者マークの車は特に慎重に
- 相手の進行に不安がある場合は追い越しを控える
- ウインカーを早めに出して意思表示する



優先道路という言葉に惑わされず、「今その場が安全か」を冷静に判断することが大切です。
高齢ドライバーに配慮した安全運転のポイント
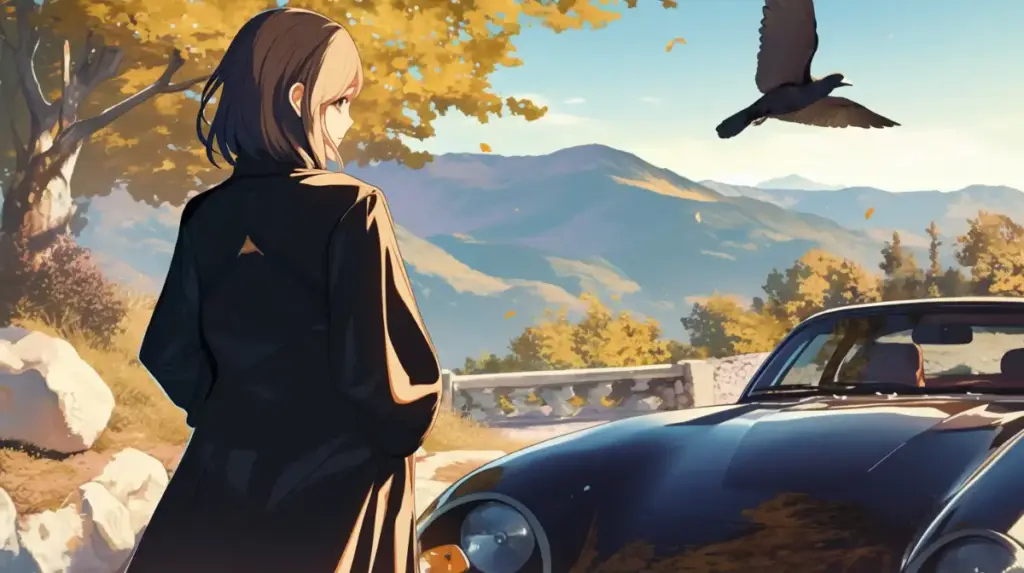
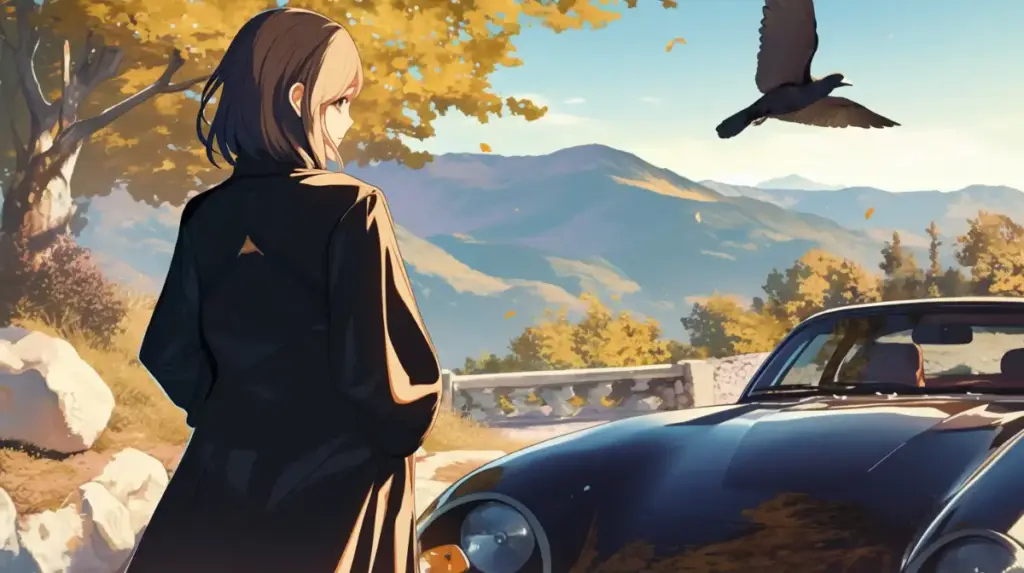
高齢ドライバーが増える中、すべてのドライバーが少しずつ配慮することで、安全な道路環境が生まれます。
高齢ドライバーに見られる特徴
| 特徴 | 運転上の傾向 | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 判断力の低下 | 信号変化に気づくのが遅い | クラクションは控え、余裕をもつ |
| 視野の狭まり | 周囲への注意が届きにくい | 車間距離をしっかり取る |
| 動作のゆっくりさ | 加減速が不安定 | 急な追い越しや割り込みを避ける |
具体的な配慮ポイント
- 高齢者マークの車を見かけたら、追い越しは慎重に
- 車間距離を十分にとり、急な接近を避ける
- 出発や右左折のタイミングが遅くても焦らせない
- 合流や車線変更では譲る意識を持つ



「お互い様」の気持ちで接することが、思いやりある運転につながります。
ちょっとした心がけで、事故リスクは大きく減らせますよ。
高齢者マークの車を追い越しする際に知っておくべきこと
この記事のポイントをまとめます。
- 高齢者マークの車を追い越すこと自体は道路交通法で禁止されていない
- 追い越しは可能だが高齢者の特性を理解した配慮が必要
- 「追い越し」と「追い抜き」は法律上明確に異なる行為
- 「追い抜き」は進路変更を伴わず、状況によっては違反となる
- 高齢者マーク車への幅寄せは通行妨害とみなされ違反となる可能性がある
- 幅寄せや急接近はあおり運転と判断されることもある
- 高齢者マーク車への割り込みも妨害行為と見なされやすい
- 法改正以降、妨害運転に対する罰則は厳格化されている
- 高齢者マークは70歳以上で表示が推奨される努力義務の標識
- 高齢運転者への妨害運転は禁止されており法的な処分対象となる
- 障害者マークの車も追い越しは可能だが丁寧な配慮が求められる
- 聴覚障害者マーク車両にも追い越し可能だが妨害行為は禁止されている
- 初心者マークの車も追い越しは可能だが慎重な対応が必要
- 優先道路でも追い越しにはルールと制限がある
- 安全運転には高齢ドライバーへの思いやりが欠かせない

コメント