セミの幼虫を乱獲で条例違反?都内で急増する“深夜の採集者”の実態!
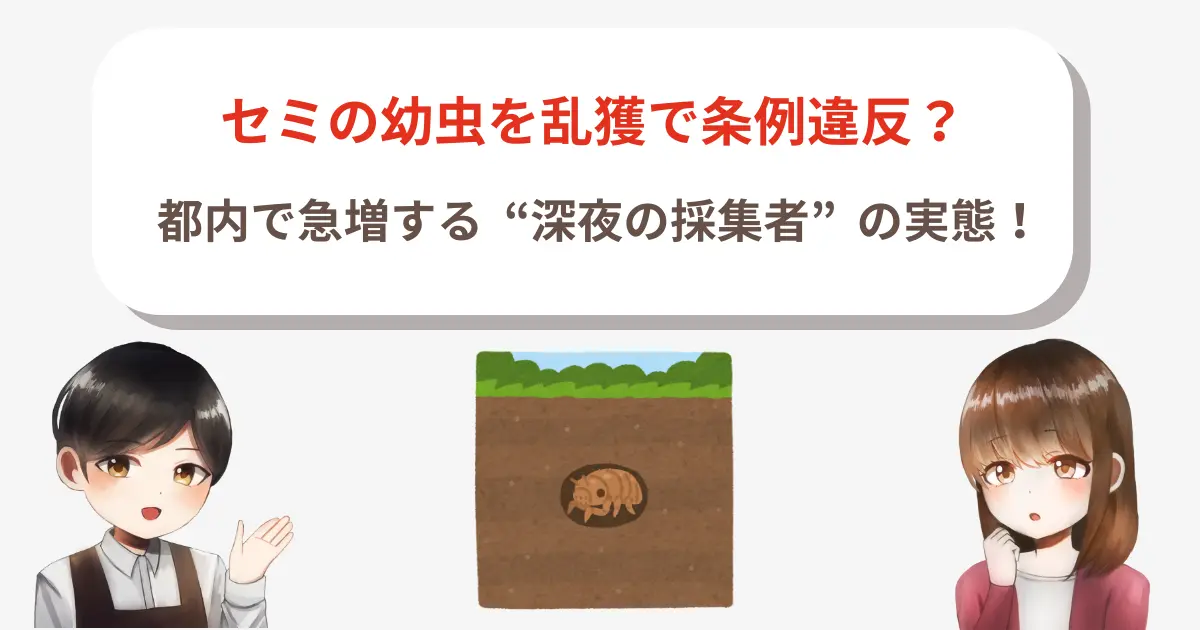
2025年7月、東京の公園に「セミの幼虫を採らないでください」という張り紙が急増中。
しかも、注意書きには中国語も。
夜になると現れる“謎の採集者”の存在が、住民の間で不安を広げています。
こうした採集行為の背景には、中国での“高級食材”としての需要と、そこに目をつけた一部の外国人による“深夜の乱獲”という実態が隠れていました。
この記事では、都内で実際に起きている乱獲の現場とその経済的背景、さらに法律のグレーゾーンや、公園管理者が抱えるジレンマまでを徹底的に掘り下げます。
 よーかん
よーかん誰もが訪れる身近な公園で、今なにが起きているのか…。
その全貌をお伝えしますね!
- なぜ都内の公園で「セミの幼虫・採取禁止」の張り紙が増えているのか
- 採集の背後にある中国の昆虫食文化と経済的動機
- 昆虫採集をめぐる法的グレーゾーンと公園管理者の対応
- セミの幼虫の栄養価や食用としての価値、そして乱獲による生態系への影響
セミの幼虫を乱獲で条例違反?「採取禁止」張り紙の裏側に迫る
2025年7月、都内の公園に突如として現れた「セミの幼虫 採取禁止」の張り紙。
そこには、日本語だけでなく中国語や英語も併記されていて、SNS上では「なんで中国語?」「誰が採ってるの?」と疑問の声が爆発的に広がりました。
一見ただの昆虫採集に見える行為が、なぜ“乱獲”という深刻な言葉で語られるようになったのでしょうか?



ここでは、その始まりとなった事例と背景を、時系列で整理しながら見ていきますね!
張り紙が立てられた理由とは?過去の騒動を振り返る
「セミの幼虫 採取禁止」の張り紙が立てられるようになったのは、実はここ数年の話ではありません。
最初の騒動は2018年、埼玉県川口市の公園で「夜中に大量のセミの幼虫を採っている人がいる」と住民から苦情が出たことがきっかけでした。
その後、2020年には東京都杉並区の公園でも同様の事態が起こり、「明らかに子どもの虫取りとは違う」「食用目的では?」という声が相次ぎました。
そして最近では、江東区の猿江恩賜公園での“深夜の採集者”が話題となり、SNS上で拡散。
張り紙には「子供たちがセミを楽しみにしています」といった感情的な訴えも記され、X(旧Twitter)では数万回もシェアされるほど注目を集めました。
ここまで問題が広がった理由は、大人がビジネス目的で何十匹もまとめて採集していたこと。
市民感覚では“度を超えている”と映ったため、公園管理者が警告に踏み切ったのです。



次は、この“乱獲”を引き起こす最大の理由――セミの価値と採集者の目的に迫っていきます。
「違法なの?」条例と法律のグレーゾーンを解説
結論から言うと、セミの幼虫を公園で採ることは完全な違法行為とは言い切れないんです。
その理由は、多くの自治体の条例が「鳥獣魚貝の捕獲を禁止」としているものの「昆虫」が明記されていないからなんですよね。
たとえば東京都の公園条例も、鳥や魚はダメと書かれているけど、セミのような昆虫はグレーゾーンに入ってしまうんです。
実際に東京都建設局の見解でも、「節度を守った昆虫採集は問題ない」という立場が取られていて、小学生が夏休みにセミを数匹捕まえるくらいはOKとされています。
ただし、何十匹もまとめて、しかも夜中に採るような行為は、たとえ法律上は違反でなくても、公園の秩序や自然環境を乱す行為として、管理者が問題視するのは当然ですよね。
そのため「法律ではグレーだけど、マナー的にはアウト」といった状態が、張り紙の設置につながっているんです。



次は、なぜそんなグレーな行為がエスカレートするほど行われているのか、そして“深夜の採集者”たちの目的に迫ります。
なぜ乱獲が起こるのか?“深夜の採集者”とその裏にある目的
条例のグレーゾーンをすり抜けるようにして、夜の公園に現れる“セミハンター”たち。
では、なぜ彼らはそこまでしてセミの幼虫を大量に採集するのでしょうか?
子どもの虫取りとはまったく違う、大人の本気度には、実は“お金”と“文化”という深い背景があります。



ここでは、乱獲が起きる本当の理由について、経済と食文化の視点から掘り下げていきますね。
乱獲の動機は“食”?“転売”?知られざる経済的背景
実は、セミの幼虫には驚くほどの市場価値があるんです。
中国では、セミの幼虫は「唐僧肉(タンツォウロウ)」と呼ばれる高級食材。
500gあたり約180元(日本円で3,700円相当)という高値で取引されていて、1匹40円という単価もザラ。
中には、セミの養殖だけで年収2,000万円を超える「セミ長者」もいるんです。
そんな価値を知っている人にとって、日本の公園は“無料の金脈”みたいなもの。
日本では特に規制もなく、誰でもアクセスできる環境なので、わざわざ採集に来る人が出てきても不思議ではありません。
しかも、セミは期間限定で地上に出てくるうえ、大量発生する場所もある。
そのチャンスを逃さず、一気に採って利益に変える…。
それが、乱獲の大きなモチベーションになっているんですね。



次は、なぜ採集者たちが“夜”を狙うのか、その行動のパターンを見ていきましょう。
なぜ夜に?セミ採集のピーク時間とその理由
セミの幼虫を狙う採集者が“夜”に現れるのは、実は理由があります。
結論から言うと、セミの幼虫が地上に出てくるのは夜だからなんです。
セミは地中で何年も過ごしたあと、羽化のために地上に出てくるタイミングを選びます。
そのピークが、日没後の午後6時半から8時頃なんですよ。
この時間帯になると、公園の地面には小さな丸い穴がポコポコと現れます。
これは幼虫が地上へ這い出る「羽化穴」で、このサインを見つけた場所には、まもなく大量のセミが出現する可能性が高いんです。
だから採集者たちは、セミが木に登り始める夜のゴールデンタイムを狙って行動しているんですね。
しかも、夜は公園の利用者も少なく、目立たずに採集できるというメリットも。
このように、セミの生態を知り尽くした“プロ”のような動きが、深夜の採集を生んでいるんです。



次は、よく話題になる「張り紙の中国語」について、その背景と意味を見ていきましょう。
張り紙に中国語?外国人と食文化との関係
張り紙に中国語が併記されている理由は、セミの幼虫を採っている人の多くが中国語話者だからです。
実は、中国ではセミの幼虫を食べる文化が昔から根付いていて、特に山東省などでは夏の風物詩として楽しまれているほど。
「唐僧肉(タンツォウロウ)」というニックネームが付くほどで、見た目はちょっとアレでも、ナッツのような香ばしさと高タンパクな栄養価から、“高級珍味”として人気なんです。
だから、日本に住んでいる人や観光客の中には「これ、食べてもいいじゃん?」という感覚で採ってしまう人もいます。
もちろん、文化の違いは悪いことではないんですが、日本ではセミを食べる文化がないので、見た目のインパクトや“乱獲”という行動が問題視されやすいんですよね。
公園管理者としても、誰に向けて注意すべきかを考えたうえで、中国語の表記を加えたというわけです。
言葉で直接伝えられない分、多言語の張り紙は最低限の“伝える努力”でもあるんですね。



次は、実際にどうやってセミの幼虫を見つけているのか、採集テクニックを見ていきましょう。
セミの幼虫はどこにいる?見つけ方と採集テクニック
セミの幼虫は地中に何年もいるって、みなさんも聞いたことがきっとあるでしょう。
「じゃあ、どうやって地面の中から見つけ出すの?」って疑問、すごく自然だと思います。
実はセミの出現にはわかりやすい“サイン”があるんです。



ここでは、公園でセミの幼虫を見つけるための基本の観察ポイントから、採集者たちが使っているであろうちょっとした裏ワザまで紹介していきますよ!
出た後の“穴”はヒント?羽化のサインを見極める
セミの幼虫を見つけるカギは、地面にぽっかり空いた小さな穴にあります。
それは「羽化穴」と呼ばれるもので、セミの幼虫が地上に出てきた跡なんです。
この穴は直径1センチ前後で、まるで指で押したように丸く、深さも比較的浅め。
こういう穴が複数見つかる場所は、“今夜大量にセミが出てくるかも!”というサインになります。
つまり、穴を探す=セミの出現スポットを探すってことなんですね。
特に、日中によくセミが鳴いている木(例えば桜の木やケヤキの木)の根元周辺に注目。
そこに羽化穴が多いと、その日の夜はチャンス大です。
また、地面が乾燥しているよりも、前日や当日に少し雨が降ったあとの湿った土のほうが穴を見つけやすいですよ。
こうして、羽化の予兆を読み取ることができれば、夜の採集で「ここだ!」というポイントを絞ることができるんです。



次は、実際に地中や木の上からセミの幼虫を見つけ出す、ちょっとマニアックな採集テクを紹介します。
地中からどうやって見つける?採集者が使う裏ワザ
セミの幼虫を地中から見つけ出す方法が実はちゃんとあるんです。
その中でも特に有名なのが「水攻め」と「誘い出しテクニック」。
まず水攻め。これは羽化穴に水を注ぎ込むという方法です。
地中の幼虫は酸素が足りなくなると苦しくなって、自分から地上へ出てこようとします。
子どものころ遊びでやった人もいるかもしれませんが、意外と効果的なんですよ。
次に誘い出し。これは細い枝やストローみたいなものを穴にそっと差し込んで、幼虫に掴ませて引き出すテクニックです。
虫釣りみたいな感じで、慣れるとけっこう成功率が高いんです。
さらに、一部の採集者は木の幹にラップを巻いて、登ってきた幼虫を足止めする「ラップトラップ」を使うことも。
ただし、公園によっては工作物の設置は禁止されていることもあるので要注意ですね。
こういった裏ワザは、生態をよく理解している人だからこそ使えるものでしょう。



次は、そんなセミの幼虫が実は“食べられる”って知ったときの驚きと、その味や見た目について紹介していきます。
気持ち悪い?おいしい?セミの幼虫の味・見た目・調理法
「えっ、セミの幼虫って食べられるの!?」と思った人も多いことでしょう。
虫=苦手というイメージを持っている人にとっては、ちょっと勇気がいりますよね。
でも実は、セミの幼虫って、栄養価が高くて味も“意外といける”と話題になっているんです。



このパートでは、気になるフォルムや食感、そして実際の味についてもリアルにお届けします!
セミの幼虫の気になるフォルムと食感
セミの幼虫の見た目や食感が気になる…その気持ち、めちゃくちゃわかります。
セミの幼虫は、地中にいるあいだは白っぽくて土にまみれています。
でも、地上に出てきたばかりのタイミングでは、体がふっくらしていて茶褐色、羽化直前で“プリッ”としてるんです。
触感は、外は柔らかくて弾力があり、中はトロっとクリーミーとも言われています。
まさに「虫版エビフライの中身」みたいなイメージですね。
さらに、火を通すことで外側がサクッと、中がもちっとした独特の食感になるので、食べてみると「ナッツっぽい」と感じる人が多いみたい。
とはいえ、羽化が始まって背中が割れた個体は、動かすと失敗しちゃうので採らないのがマナーなんですよ。



次は、そんな“見た目と触感のギャップ”を楽しめる、セミ幼虫のおすすめ調理法をご紹介します!
ナッツ風味で高タンパク!おすすめ調理法も紹介
セミの幼虫は、実は高タンパクすぎて驚くほどの“食材力”があるんです。
その理由は、栄養バランスの圧倒的な優秀さ。
下の表を見れば、普段よく食べる肉や大豆よりも、はるかに高い数値なのがわかります。
| 栄養素 | 乾燥セミ幼虫(タイ産) | 鶏むね肉(皮なし・生) | 牛もも肉(赤身・輸入) | 大豆(乾燥・国産) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) | 451 | 105 | 136 | 372 |
| タンパク質 (g) | 71.1 | 23.3 | 21.2 | 33.8 |
| 脂質 (g) | 13.8 | 1.9 | 5.5 | 19.7 |
| 炭水化物 (g) | 10.6 | 0.1 | 0.5 | 29.5 |
この表からも分かるように、セミの幼虫は鶏肉の約3倍、大豆の2倍以上のタンパク質を含んでいるんです。
しかも味は「ナッツっぽくて香ばしい」と評判で、ピーナッツやアーモンドが好きな人にはハマるかも。
おすすめの食べ方は、塩を振って素揚げが定番。外はカリッと、中はもちっとしていて、クセになる食感だそうです。
他にも天ぷらや甘酢炒め、燻製なんかも人気で、おつまみにも合うらしいんですよ。
調理前は、しっかり下ゆで(2〜3分)するのがポイント。
アレルギーがある人は注意が必要ですが、安全に調理すれば栄養満点のスーパーフードになるようです!(僕は食べたことはありません。笑)



次は、こうした“乱獲ブーム”が都市の自然にどんな影響を与えるのか、深掘りしていきます。
セミの(幼虫)乱獲で都市の自然が壊れる?私たちが守るべきこと
「食べられる」とわかると、どうしても気になるのが“採りすぎ”による影響です。
セミは街の自然に欠かせない存在ですが、乱獲が進めばそのバランスは簡単に崩れてしまいます。
ここでは、都市公園や野生動物への影響、さらには実際に起きている事例をもとに、僕たちが気をつけるべき“セミ採集の境界線”について考えていきましょう。
セミの幼虫を乱獲するとどうなる?都市の自然への影響
セミは、都市の自然において“縁の下の力持ち”のような存在です。
普段は気づかれにくいですが、セミの幼虫が大量に採られてしまうと、さまざまな形で都市の生態系に影響を及ぼします。
たとえば、セミは多くの野鳥にとって重要なエサ。
特に夏場は、ヒヨドリやムクドリなどがヒナに与える栄養源としてセミの幼虫を狙っています。
この供給が断たれると、野鳥の繁殖にも悪影響が出る可能性があるんです。
また、セミの幼虫が地中にいる間に掘る穴や通路は、土壌に空気や水が通る“通気孔”のような役割を果たしています。
乱獲によってこの働きが減ると、地面の保水力や植物の根の成長にも影響が出ると考えられます。
さらに、生態系全体のバランスが崩れると、思わぬ現象が起きることも。
北海道・知床半島では、ヒグマがセミの幼虫を掘り返して食べるという行動が観察され、その結果、根を傷つけられた木々の生育が悪化したという報告もあります。
東京の公園にヒグマはいませんが「一つの種を極端に減らす」ことが、予期せぬ連鎖反応を引き起こすという良い例です。
だからこそ、セミを採るときには「どこまでがOKなのか」を自分で判断することが求められます。



次のパートでは、その“線引き”の考え方として注目されている「思慮深い採集」という新しいアプローチをご紹介します。
これからのセミ採集と“思慮深い共存”の視点
セミの乱獲に対しては「全面的に禁止すべきだ」という声と、「文化や食の多様性を尊重すべきだ」という声がぶつかり合っています。
でも、そのどちらか一方に振り切るだけでは、根本的な解決にはつながりません。
重要なのは、自分が自然からどれだけ得るかだけでなく「他の生き物や未来の利用者に、どれだけ残せるか」という視点に立った採集スタイルです。
たとえば
- 採りすぎない
- 羽化直前の個体はそっと見送る
- 公園のルールを守り、他の利用者の迷惑にならないよう配慮する
そうした小さな配慮が、都市の自然との“穏やかな共存”を生み出します。
これはただのマナーではありません。
都市に住む僕たちが自然とつながるための、ひとつの考え方と言えるでしょう。
そして、それは子どもたちが生き物とふれあい、自然への敬意を学ぶ大切な機会にもなり得ます。
僕も子供の頃に虫取り網を片手にセミを捕まえたことがありますが、こういった子供の楽しみや自然との触れ合いの機会を奪ってしまうことはやっぱり良くないですもんね。



だからこそ「ダメだからやめよう」ではなく「どうしたら続けられるか」を一緒に考えていく姿勢が、今こそ求められているのではないでしょうか。
セミの幼虫はなぜ乱獲されるのか? 都内で起きる深夜採集の実態と私たちの選択肢
都内の公園で相次ぐ「セミ幼虫の採取禁止」張り紙。
その背後には、中国人による“食用目的の乱獲”という、これまで語られてこなかった実態が隠れていました。
この記事では、その背景や仕組みを明らかにしながら、都市で生きる僕たちがこの問題とどう向き合うべきかを探ってきました。
以下に要点を整理します。
- セミ幼虫の深夜採集が、都内の複数の公園で問題化
- 張り紙には中国語も併記されており、外国人による大量採取が主な発端
- 中国ではセミの幼虫が「高級食材」として高額で取引されており、経済的な動機が背景にある
- 乱獲の行動には文化的背景もあるが、日本の都市公園では秩序や生態系を乱す行為として受け止められている
- 法的にはグレーゾーンであり、現場では“お願いベース”の対応が限界となっている
- 今後は「文化の尊重」と「資源管理」のバランスをどうとるかが課題
見慣れた夏の風景の裏で進む“静かな乱獲”に、私たちはどう向き合うべきか。
一律の禁止か、共存の工夫か…。



いま都市の緑地に求められているのは、“見て見ぬふり”をやめることかもしれません。
コメント