【完全版】ケアマネの性格が悪いと感じたら読むべき対処ガイド
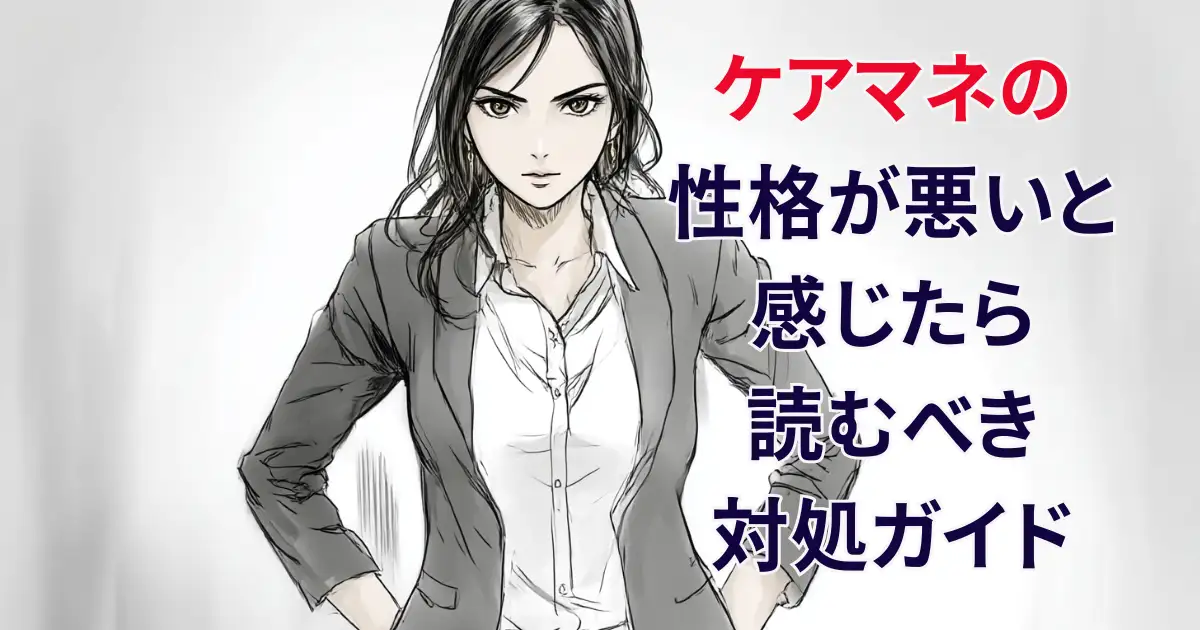
介護に関わる中で、「ケアマネの性格が悪い」と感じたことがある方もいるかもしれませんね。
僕自身、現場で長年ケアマネとして働く中で、利用者さんや家族から「前のケアマネと喧嘩をしそうになった」「関係がぎくしゃくしてしまった」というような声を聞いた経験もあります。
また、「ケアマネの態度が悪い」と感じられても仕方がない対応を目の当たりにしたり、実際にそのようなケアマネと研修などで出会ったりという場面も多くありました。
中には、「ケアマネは何様なのか」と思わずにはいられない対応をする人や、「もうケアマネなんていらない」と利用者さんに言われてしまうケアマネージャーも残念ながら存在します。
「ケアマネってそんなに偉いのか」と疑問に思う気持ちが芽生えることも、珍しいことではありません。
この記事では、現場で実際に寄せられた「ケアマネへの苦情事例」をもとに、「悪いケアマネージャーとはどのような人か」を具体的に解説していきます。
また、「ケアマネに腹立つ」と感じたときに冷静に対応する方法や、「ダメなケアマネの特徴は?」という視点から見た注意点も整理しています。
 よーかん
よーかん介護の現場で悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- ケアマネの性格が悪いと感じる原因や背景を理解できる
- ケアマネと喧嘩せずに冷静に対応する方法がわかる
- ダメなケアマネの特徴や苦情事例を知ることができる
- ケアマネ交代を検討すべきタイミングを判断できる
ケアマネの性格が悪いと感じたときの対処法


- 筆者が実際に出会った性格の悪いケアマネ
- ケアマネの態度が悪いと感じる原因とは
- ケアマネに何様と思う背景を解説
- ケアマネがいらないと感じたときの考え方
- ケアマネってそんなに偉いのかを検証
筆者が実際に出会った性格の悪いケアマネ


筆者である僕自身も、研修やサービス提供者側にいた際に、「この人性格悪いなぁ」と感じるケアマネと出会ったことがあります!
ここでは、実際に僕が出会った「性格が悪いと感じたケアマネ」について具体例をお伝えしますね。
自分の担当ケースを取られたと言う
特別養護老人ホームの施設ケアマネをしていたとき、入居の申し込みされていた利用者の順番が回ってきたので、担当のケアマネに連絡を取りました。
そうしたら「え!?もう入居させてしまうんですか?私のケースが減っちゃうんですけどそういうこと考えてくれないんですか?」と言い返されたんです。
利用者や家族の状況を考えると在宅介護が限界になってきていたので、特養への入居は妥当と判断できるのですが、自己の利益のみでこういう発言をする人なんだなぁとがっかりしました。
そして更に、先日、僕が地域包括支援センターに異動した際にはそのケアマネが営業に来て「ぜひ、新しい人がいましたら紹介してください。」と今度は手のひら返したようにペコペコしてるんですよね…。
さすがに唖然としてしまいました。
利用者や家族の悪口や不満を言い続ける
ケアマネは研修でよくグループワークを行います。そこで意見交換するのですが、ある年配女性のケアマネは利用者やその家族の悪口や不満を延々と漏らすんですよね。
確かに、相談支援の仕事なのでストレスも溜まるのは分かるのですが、利用者や家族の個人情報に当たる部分までもを第三者に漏らすことは守秘義務違反にも当たります。
「守秘義務違反なので気をつけてくださいね」と注意させていただきましたが、不満そうな顔をされていました。
とにかく自己判断
ケアマネは利用者の病状を含む色々な情報や人生史、取り巻く環境などを総合的に把握し、その人の生活を良くするために業務を行います。
そして、それぞれの専門職の意見に基づいて考えた結果、現状のベストは何かという判断を下します。
例えば、療養上のことは医師の意見を参考にしたり、骨折後の身体の動きのことなどを理学療法士に意見をもらったりして、判断していきます。
ところが、根拠も無く自己判断のみで生活上の課題や目標を決めてしまい、更にはサービスまでも自分で決めてしまう人がいるのです。
介護保険サービスは利用者が自己選択することが原則なので、僕らケアマネはその判断がしやすいよう、その人の課題に応じたサービスを情報提供することが役割です。
ここを履き違えて、自分の気に入っている、懇意にしているサービスを提案するケアマネは、基本理念も理解できていない自己中心的と言わざるを得ません。
ましてや利用者本人や家族の意見や真の困りごとを聞かないなんて言語道断。



このように同じくケアマネの僕から見ても性格悪いと感じる人がいるので、利用者や家族からしたらもっと強くそう感じていることと思います…。
ケアマネの態度が悪いと感じる原因とは
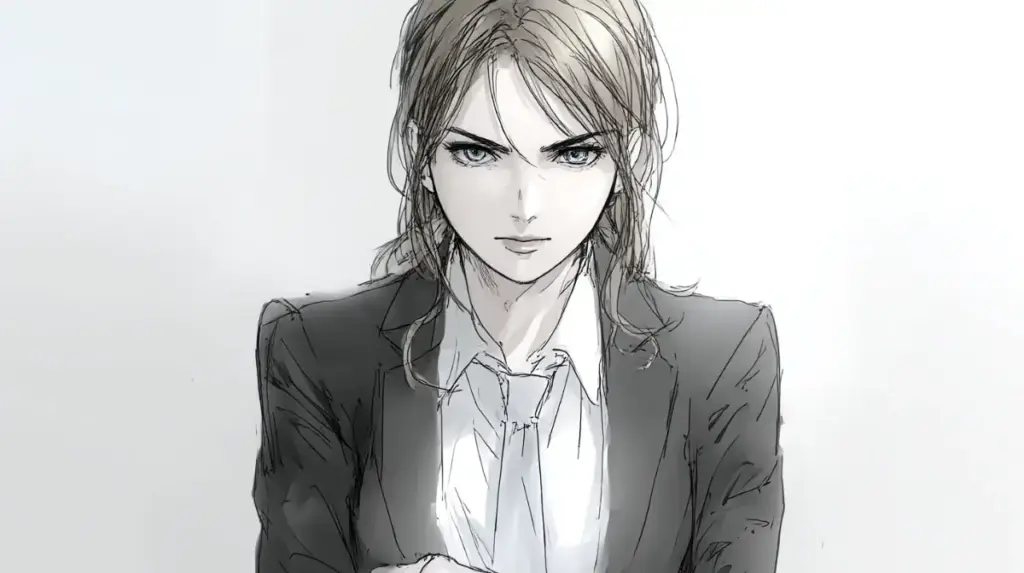
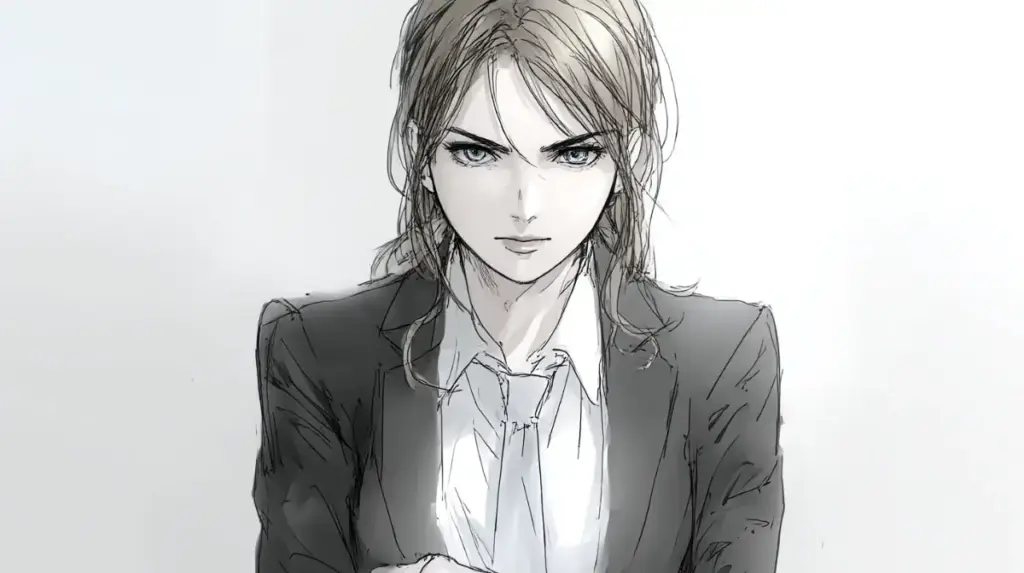
ケアマネージャーの態度に違和感や不快感を抱くとき、そこにはさまざまな背景が存在します。単に性格の問題ではなく、業務環境や制度上の制約など、複合的な要素が影響していることを理解することが大切です。
最も多い原因のひとつは、業務過多による余裕のなさです。
ケアマネージャーは、一人で40件以上の利用者を担当することもあり、モニタリングや書類作成、関係各所との調整に追われています。
僕自身、特別養護老人ホームでは80人を1人で受け持ちました。
また、現在は地域包括支援センターの主任ケアマネとして60人の担当に加えて、地域から寄せられた相談や課題のある高齢者の対応等も行っています。
何か対応をすれば、都度、記録や書類の作成が必要となるので、件数が増えれば増えるほど業務量もどんどん増えてしまいます。
ケアマネはこのように業務過多で時間に追われやすく、利用者とのやり取りがどうしても事務的になり、結果として「冷たい」「高圧的」と受け取られてしまうことがあるのです。
また、専門職としてのプライドが高すぎるケースもあります。例えば、介護保険やサービス内容に詳しいことを背景に、利用者の希望に耳を傾けず、自分の判断だけで物事を進めようとするケアマネも存在します。
このような態度は、利用者や家族に「自分たちの意見を軽視された」と感じさせ、強い不満を生じさせる原因となるでしょう。
さらに、個人の人間性の問題も無視できません。中には、利用者を下に見るような価値観を持っているケアマネも一定数存在します。
例えば、認知症の高齢者に対して、無意識に馬鹿にするような態度を取る人もおり、こうした対応が積み重なることで、信頼関係は大きく損なわれてしまいます。
このように考えると、ケアマネの態度が悪く見える背景には、単なる性格だけでなく、環境要因や制度的な問題も複雑に絡み合っていることがわかります。



性格や価値観によるものはもちろんありますが、精神的な余裕がないことも性格が悪いと感じられてしまうような態度につながってしまうこともあるんですよね。
ケアマネに何様と思う背景を解説


ケアマネージャーに対して「何様なの?」という感情を抱くことは、珍しいことではありません。この背景には、ケアマネという職種が制度上持つ特別な役割と、コミュニケーションのあり方が深く関係しています。
まず、ケアマネージャーは介護保険制度において、ケアプランを作成する唯一の権限を持っています。(一応、利用者自身がセルフプランで作成することもできますが、稀です。)
利用できるサービスや支給限度額の範囲を調整する役割を担うため、利用者や家族から見ると、ケアマネが「サービスの可否を決める立場」にあるように映るでしょう。
これが、「上から目線だ」と感じさせる要因の一つです。
一方、コミュニケーション不足もこの感情を助長します。
例えば、「制度上できないこと」を説明する際に、理由を丁寧に伝えず、ただ「できません」とだけ答えた場合、利用者は自分たちの希望が一方的に否定されたと感じてしまいます。
このとき、ケアマネへの不信感は一気に高まり、「何様だ」といった強い感情が生まれるのです。
さらに、現場の文化にも要因があります。古くから一部の地域や事業所では、ケアマネを特別視する風潮が根付いていることがあります。
福祉用具業者や施設関係者が、営業上の都合からケアマネに過剰にへりくだることで、本人が無意識に「自分は偉い」と錯覚してしまうケースもあるのです。
あと、実際に僕もよく体験するのですが、なぜか利用者自身がケアマネに対して「先生」と呼ぶことがあるんですよね。こういったことも、ケアマネの勘違いを助長させる要因ではないかと思います。
このような背景を踏まえると、ケアマネージャー自身が意図せず「何様」と思われてしまう構造が存在しているといえます。しかし、利用者にとって重要なのは、支援の中身と誠実な対応です。



もし、態度に納得できないと感じた場合には、具体的な希望を伝え、必要であれば担当者変更を検討しましょう!
ケアマネがいらないと感じたときの考え方


介護に関わる中で、「もうケアマネなんていらない」と感じる場面に直面することもあるでしょう。特に、信頼関係が築けないケアマネージャーに当たった場合、強いストレスを感じるのは自然な反応です。
しかし、ここで一度冷静に立ち止まり、「本当にケアマネそのものが不要なのか」考えることが大切です。
多くの場合、不満の対象はケアマネージャー個人に向けられており、ケアマネという役割そのものを否定すべきかは別問題だからです。
ケアマネージャーの本来の役割は、介護保険サービスを適切に組み合わせ、利用者ができる限り自立した生活を送れるよう支援することにあります。
煩雑な介護手続きや制度利用のサポートを担うことで、利用者や家族の負担を大きく軽減してくれる存在のはず。このため、適切なケアマネと出会えれば、介護生活は格段にスムーズになります。
一方、担当者との相性が悪かったり、対応に不満がある場合には、「いらない」と感じるのも無理はありません。このときには、ケアマネージャーの交代を検討することが賢明です。
現在の担当者にこだわらず、より信頼できるケアマネを探すことで、介護環境そのものを改善できる可能性があるでしょう。



ケアマネがいらないと感じたときこそ、役割と個人を切り分けて考えるべきです。焦ってすべてを否定してしまわずに、まずは交代という選択肢を検討してみてください。
ケアマネってそんなに偉いのかを検証


介護現場では、「ケアマネってそんなに偉いの?」という疑問を持つ方が少なくありません。この感情は、ケアマネージャーの発言や態度に違和感を覚えたときに、特に強く芽生えるものです。
まず知っておきたいのは、制度上ケアマネージャーは偉い立場には位置づけられていないということです。
ケアマネは、あくまで利用者に最適な介護サービスを調整するコーディネーターであり、サービスを提供するために必要な橋渡し役を担っています。
つまり、利用者や家族、そして各サービス事業者と「対等な関係」で協働することが本来のあり方なんです。
しかし実際には、介護保険制度上、ケアプランの作成権限を独占しているため、利用者側から見ると「選ばれる立場」ではなく「選ぶ立場」のように映ることがあります。
このため、説明不足や高圧的な態度が少しでも見られると、「偉そうだ」という印象を持たれやすいのです。
さらに、事業者側が営業的な理由からケアマネに過剰な気遣いをする場面もあり、結果としてケアマネ本人が無意識に優越感を持ってしまうケースも見受けられます。
サービス事業所からすると、ケアマネから利用者が紹介されるため、持ち上げるような発言をする人がいるんですよね。
ただし、これは個人の資質の問題であり、すべてのケアマネージャーが該当するわけではありません。
こう考えると、ケアマネという職種そのものが偉いのではなく、態度や振る舞いによって印象が大きく左右されることがわかります。
本来は利用者に寄り添い、支援する立場であることを忘れずに、対等な関係を築こうとするケアマネこそが理想的な存在と言えるでしょう。



初心忘れるべからずです。僕もこの基本を常に見失わないように日々、反省するようにしています。
ケアマネってそんなに偉いのかと疑問に思う方へ。こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
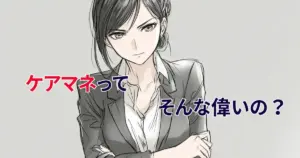
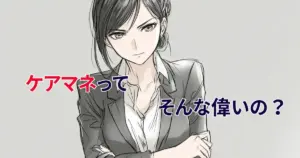
ケアマネの性格が悪いときに知っておくべき知識


- ケアマネの苦情事例から見る典型パターン
- 悪いケアマネージャーとはどんな人か
- ケアマネに腹が立つときの冷静な対応方法
- ダメなケアマネの特徴は?チェックリスト
- ケアマネ交代を検討すべきタイミング
ケアマネの苦情事例から見る典型パターン
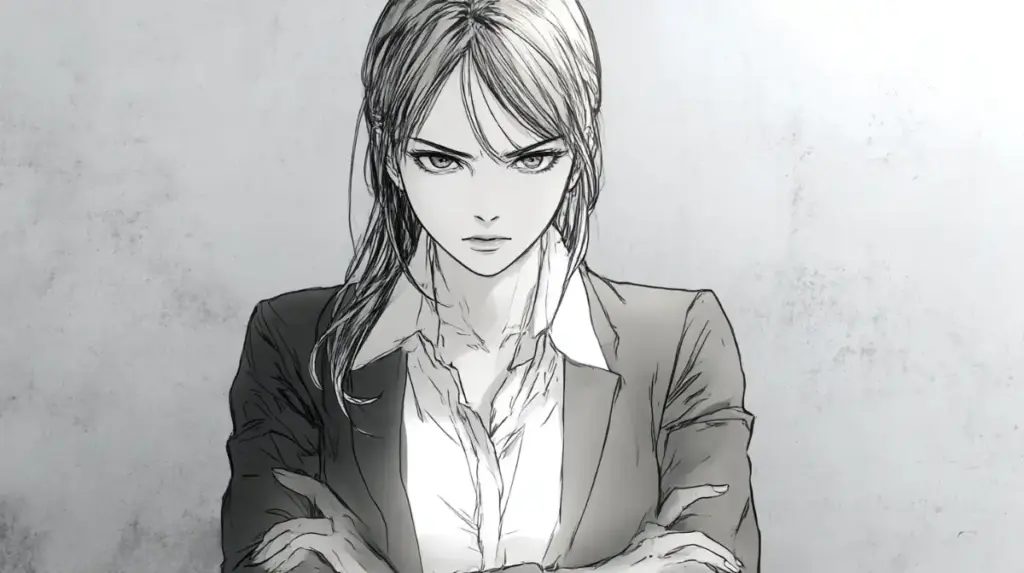
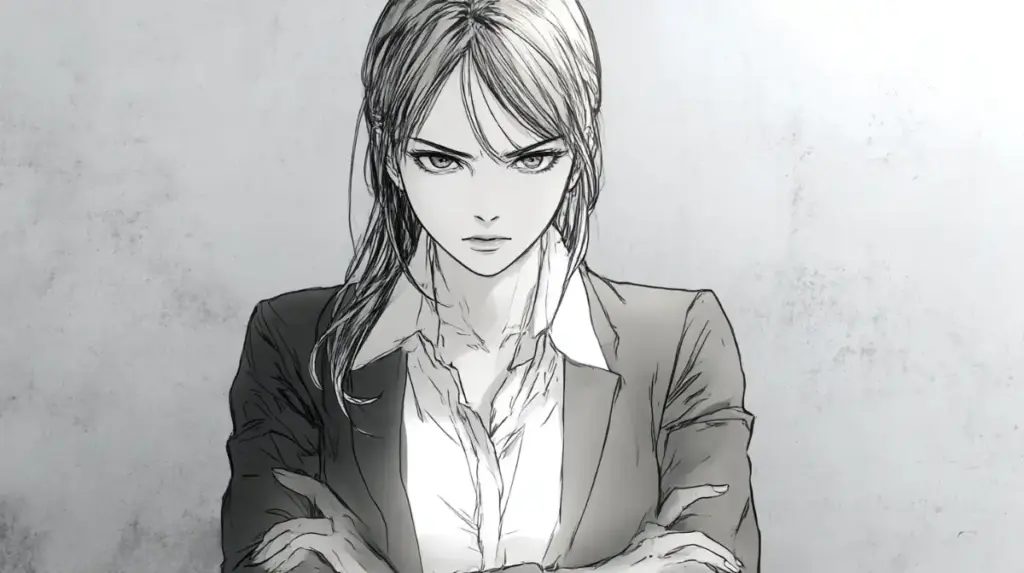
ケアマネージャーに対する苦情は決して少なくありませんが、その内容には一定のパターンがあります。ここでは、典型的な苦情事例を紹介しながら、どのような点に注意すべきかを整理していきます。
まず最も多いのが、説明不足に関する苦情です。例えば、「サービス内容について十分な説明がなかった」「ケアプランが一方的に決められた」という声は頻繁に聞かれます。
僕自身、部下の他ケアマネのこのような配慮不足でのクレーム対応やケアマネ交代を何度も経験してきました。同様の理由での、他の事業所からのケアマネ交代も経験しています。
利用者側は納得していないにもかかわらず、手続きが進められてしまうと、後になって大きな不満やトラブルへと発展しがちです。
次に、高圧的な態度に関する苦情も多く寄せられています。これは、ケアマネが自分の考えを押し付けるような言動を取ったり、質問に対して不機嫌な対応をしたりすることで生じます。
このような態度は、利用者や家族に強いストレスを与え、信頼関係を一気に崩すことに。
これも、自分が正しいと思い込んで自己判断のみで走りがちなケアマネによくあることです。
さらに、連絡不備に関する問題も見逃せません。例えば、急ぎの相談をしても折り返しがない、月1回の定期訪問が形だけで終わるなど、連絡体制に不安を感じるケースです。
ケアマネージャーは利用者の生活を支える重要な存在であるため、連絡が取りにくいことは、サービス全体への不信感にもつながります。
訪問やサービス担当者会議などで外に出ていることも多いですが、連絡が取りにくいと利用者やその家族に思わせないような工夫が必要だと僕は思っています。
これらの典型パターンを踏まえると、ケアマネに対して違和感を覚えた場合には、早めに記録を取り、冷静に相談することが重要です。



問題が改善しない場合は、事業所に申し出たり、担当者を変更するなどの対策を検討すべきでしょう。
悪いケアマネージャーとはどんな人か
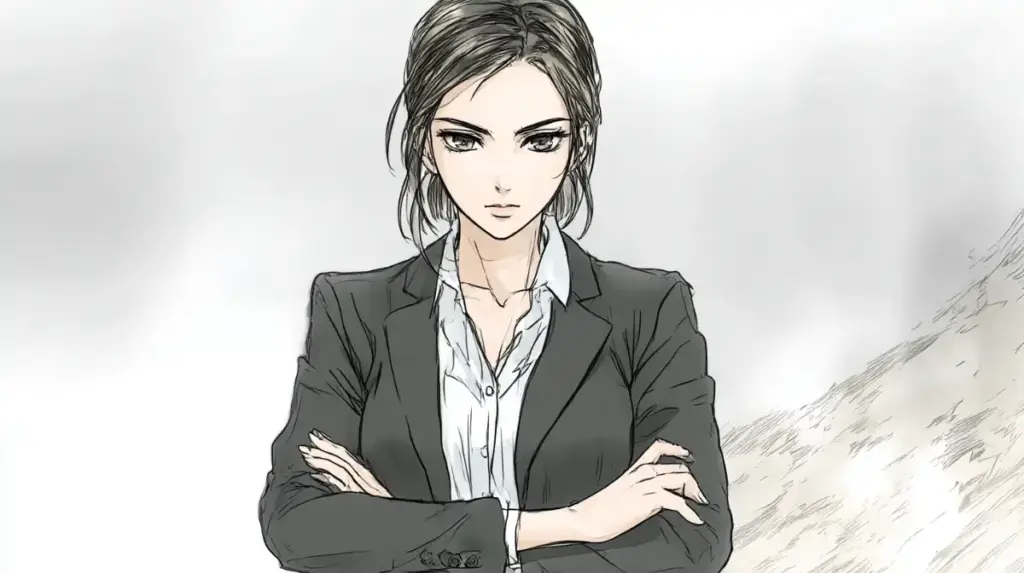
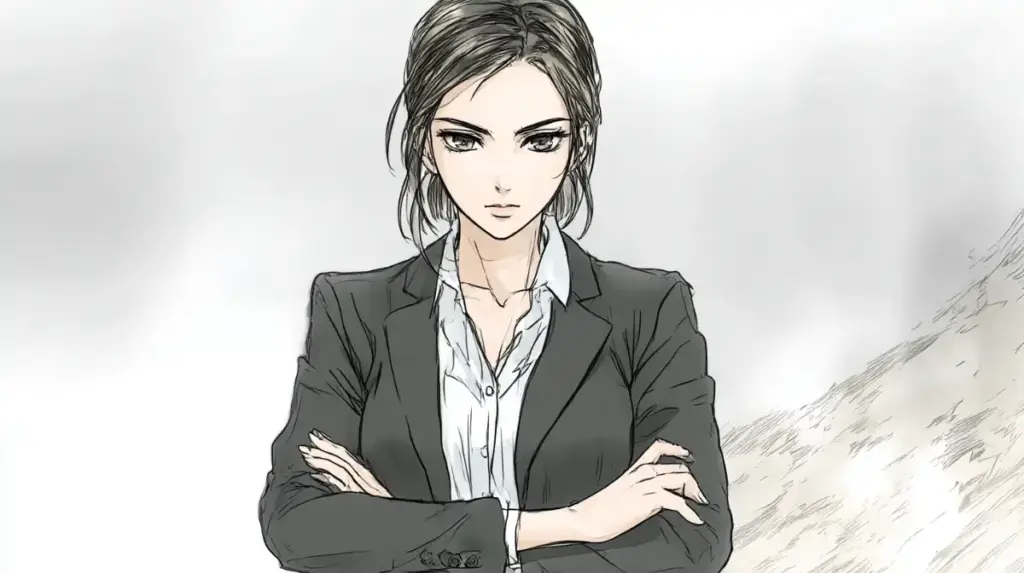
ケアマネージャーに対して「この人、問題があるのでは」と感じることは珍しくありません。では、具体的に悪いケアマネージャーとはどのような特徴を持つのでしょうか。
高圧的な態度
まず最もわかりやすい特徴は、利用者や家族に対して高圧的な態度を取ることです。例えば、要望に対して「それは無理です」と一方的に断ったり、説明もなく自分の考えだけで物事を進めるような対応をするケアマネが該当します。このような言動は、利用者の尊厳を損ない、支援者としての信頼を大きく損なう要因となるでしょう。
コミュニケーションが不十分
次に、コミュニケーションが不十分な人も注意が必要です。例えば、質問しても曖昧な返答しかしない、折り返しの連絡がない、サービス内容を詳しく説明しないといったケースです。利用者や家族にとって、ケアマネとの情報共有は安心材料となるもの。これが欠けると、サービスそのものへの不信感に繋がってしまいます。
自分本位なプランニング
また、利用者本位ではなく、自分本位なプランニングを行う人もいます。例えば、自分が付き合いのある業者を優先して紹介したり、利用者のニーズをきちんと聞き取らずに、画一的なケアプランを押し付けるケースです。こうした態度は、介護支援専門員としての倫理観に大きく反しています。
人間性や価値観に課題がある
さらに、人間性そのものに課題があるケースもあります。認知症の利用者を内心で軽視したり、個人情報管理への意識が低いケアマネも、残念ながら存在するのが事実です。こういったケースでは、表面上は問題がなさそうに見えても、実際には大きなリスクを抱えている可能性が高いといえます。
このように、悪いケアマネージャーには明確な特徴があります。少しでも違和感を覚えたら、我慢せずに冷静に状況を整理し、必要であれば交代や相談を検討することが、自分自身や家族を守るために重要です。



まずは担当ケアマネ事業所の苦情相談窓口へ連絡してみましょう。難しければ、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターに相談してみてください。
ケアマネに腹が立つときの冷静な対応方法


介護を続けていると、ケアマネージャーの対応に腹が立つ場面も出てくることがあるでしょう。しかし、感情的になってしまうと、状況を改善するどころか、かえって支援が受けにくくなるリスクもあります。だからこそ、冷静な対応を心がけることが非常に大切です。
まず、怒りを感じたときはすぐに反応せず、一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせましょう。そして、「何が、なぜ嫌だったのか」を具体的に整理してみることをおすすめします。
例えば、「説明が曖昧だったから」「こちらの話を遮られたから」といった具合に、原因を明確にすることで、対策が立てやすくなります。
次に、直接話をする際には「私」を主語にして伝えることが効果的です。例えば、「あなたは説明不足だ」ではなく、「私は説明が少ないと不安に感じます」という言い方を心がけます。
こうすることで、相手が防御的にならず、こちらの気持ちを受け止めてもらいやすくなります。
また、できるだけ感情的な言葉を使わず、事実と要望を具体的に伝えることが重要です。
例えば、「〇月〇日に依頼した件について、進捗を教えてほしい」といった具合に、冷静で明確なコミュニケーションを取るようにしましょう。
さらに、どうしても感情をコントロールできない場合は、無理に直接やり取りせず、第三者を介して相談するのも一つの方法です。
例えば、事業所の管理者や地域包括支援センターに間に入ってもらうことで、冷静な話し合いの場を設けることができます。



このように、ケアマネに対して腹立たしい思いを抱いたときこそ、冷静に、そして具体的に対話を試みることが、問題を前向きに解決するための鍵となります。
ダメなケアマネの特徴は?チェックリスト
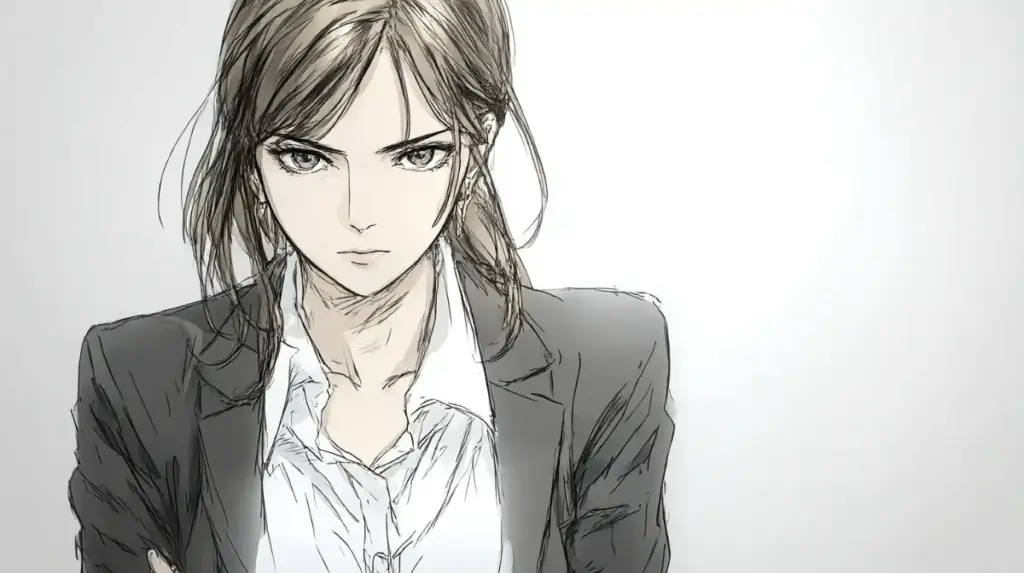
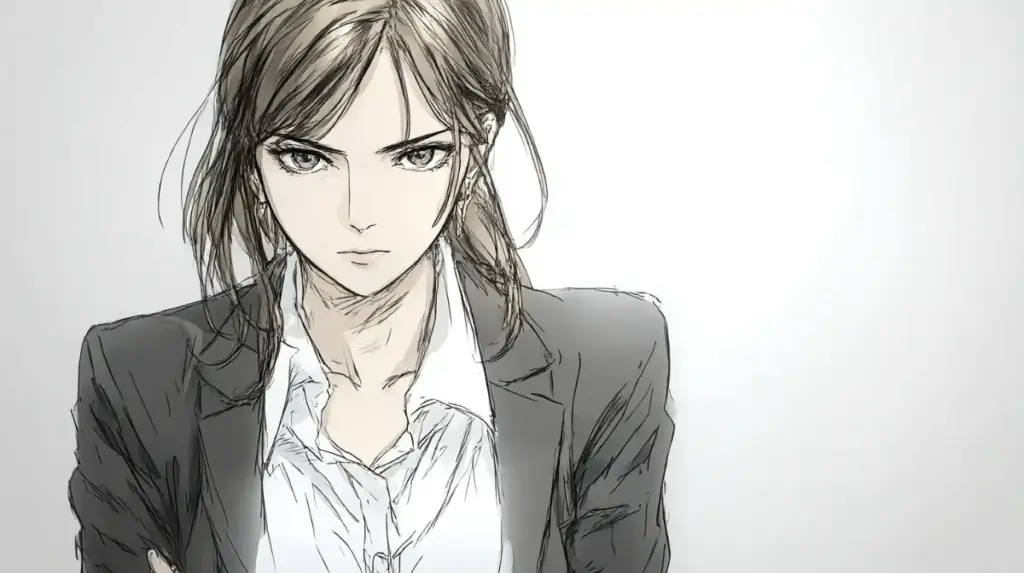
ケアマネージャーとの付き合いが始まると、最初は誰もが「きっと良い人だろう」と期待してしまうもの。しかし、関わりが深まる中で、「この人、本当に大丈夫だろうか?」と不安を感じる場面が出てくることもあります。
ここでは、ダメなケアマネの特徴をチェックリスト形式で整理しました。
- 連絡がつきにくい(折り返しがない、返事が極端に遅い)
- 説明がわかりにくい、専門用語を多用する
- 利用者や家族の意見を軽視する
- 自分の考えを一方的に押し付ける
- 高圧的な態度や見下した話し方をする
- ケアプラン作成に誤字脱字やミスが多い
- 希望に沿った必要なサービス調整ができていない
- 特定の事業者を露骨に勧めてくる
- 利用者への配慮や共感性が乏しい
- 個人情報管理がずさん
これらの特徴が複数当てはまる場合、そのケアマネとは早期に距離を取ることも選択肢に入れるべきです。違和感を覚えたら、遠慮せずに周囲に相談してみることをおすすめします。



あなた自身や大切な家族のためにも、より良い支援体制を築くための一歩を踏み出しましょう。
ケアマネ交代を検討すべきタイミング


ケアマネージャーとの関係に違和感を覚えたとき、すぐに交代を決断すべきかどうか迷う方も多いでしょう。ここでは、ケアマネの交代を真剣に検討すべきタイミングについて整理しておきます。
まず、「こちらの話をきちんと聞いてくれない」と感じたときは、交代を考えるサインです。希望や不安を伝えても軽く流されたり、話を遮られたりする場合、信頼関係を築くのは非常に難しいといえます。
次に、「対応が遅い」「連絡が取れない」状況が続く場合も要注意です。介護は日々状況が変化するため、迅速な対応が求められます。対応が遅いケアマネでは、安心して介護生活を任せることはできません。
さらに、「説明不足で不安になる」場面が続くなら、それも交代のタイミングです。サービス内容や手続きについて曖昧な説明しかされないと、利用者や家族は常に不安を抱えることになります。
本来ケアマネは、その不安を取り除く立場にあるはずです。
また、「ケアプランが希望と大きくズレている」「本人や家族の意向を反映してくれない」といったケースも深刻です。
このような状況が続く場合は、ケアマネ自身の価値観を押し付けている可能性が高く、支援の質に大きな問題があると考えた方がよいでしょう。
一方で、相手の態度が一時的に悪かっただけ、単なる行き違いだった、というケースもあります。
交代を考える前に、一度冷静に話し合いの場を持ち、それでも改善が見られない場合に交代を検討するのが現実的なアプローチです。
このように、ケアマネ交代を検討すべきタイミングにはいくつかの明確なサインがあります。



あなたや家族の介護生活を守るためにも、違和感を抱えたまま我慢せず、必要な行動を取ることが大切です。
ケアマネの性格が悪いと感じたときに知っておくべきこと
この記事のポイントをまとめます。
- ケアマネと喧嘩にならないためには冷静な対話が必要
- アイメッセージを使うことで対立を避けやすくなる
- 問題点を整理してから話し合いに臨むとよい
- 必要に応じて第三者を交えた話し合いが有効
- ケアマネの態度が悪く見える背景には業務過多がある
- 専門職のプライドが高すぎると利用者の意向が軽視される
- 利用者を見下す価値観を持つケアマネも存在する
- ケアマネに何様と思う原因は制度上の立場と説明不足にある
- 営業上の関係性がケアマネの勘違いを助長することがある
- ケアマネの役割と個人の問題を分けて考えることが重要
- ケアマネは利用者と対等な立場であるべき存在である
- 苦情事例では説明不足と高圧的態度が多く見られる
- 悪いケアマネは高圧的かつ自己中心的な態度を取る
- 連絡がつかないケアマネは早めに見直しを検討すべき
- 担当ケアマネへの違和感は無視せず早めに相談するべき


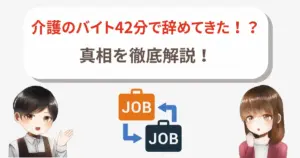





コメント