【必見】夜勤明けにずっと寝てるのは体に悪い?4つの理由と対処法
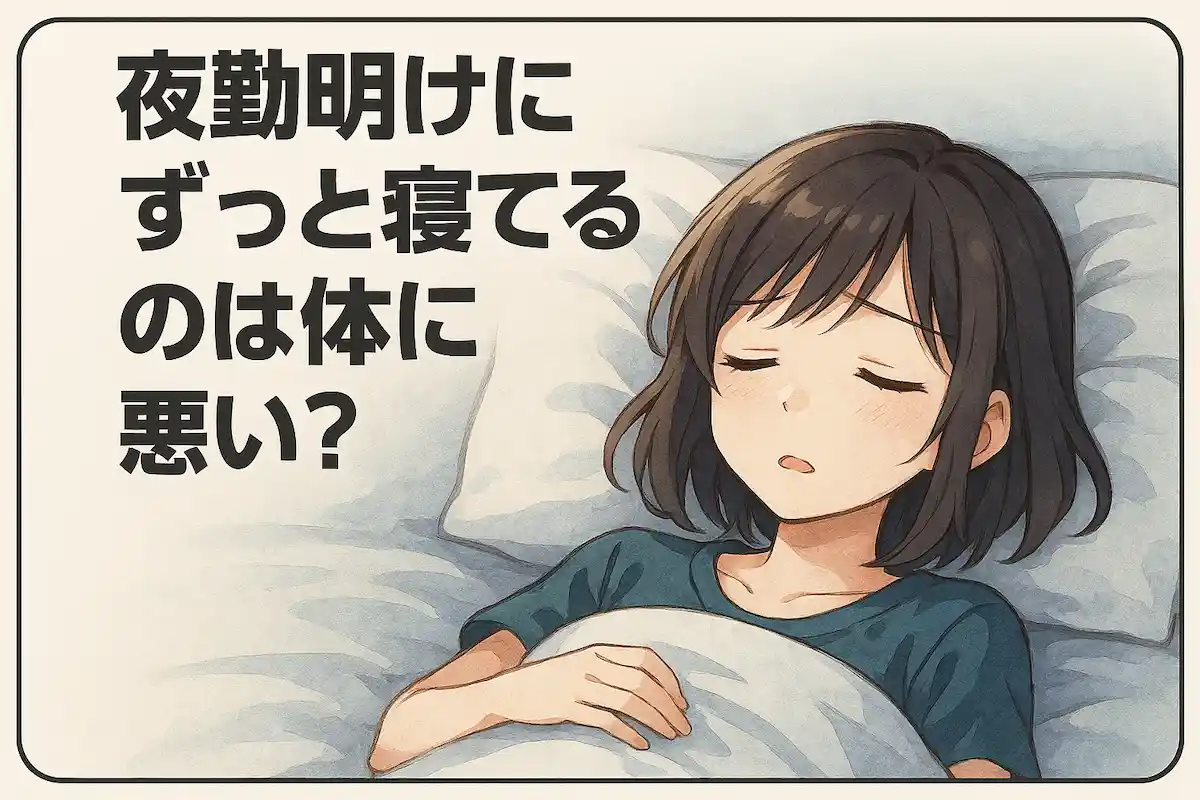
 あんこ
あんこ夜勤明けにずっと寝てしまう…。これって自分だけ?
こんな思いで不安になっていませんか。
介護の仕事は本当に過酷で、夜勤明けは心も体もボロボロになるのが普通です。
実は僕も長年、現場で夜勤を経験してきました。 何度も「ずっと寝てしまった…」「なんで自分だけ?」と悩んだことがあります。
こうした疑問やつらさに、僕自身の体験を交えながら、やさしく答えていきますね。
この記事では、夜勤明けに寝すぎてしまう原因や対策、 そしてそれでも改善しない時には“働く環境”そのものを見直す選択肢も提案しています。
この記事を読めば、「自分だけじゃない」と安心できて、 少しラクな明日を迎えるヒントがきっと見つかるはずです。



夜勤でがんばるあなたのために書きました。ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
- 夜勤明けにずっと寝てしまうのはなぜか、その原因を知ることができる
- 寝すぎることで起こる体調や生活リズムへの影響を理解できる
- 夜勤明けの過ごし方や回復のための具体的な工夫を学べる
- つらさが続く場合に働く環境を見直す重要性に気づける
夜勤明けにずっと寝てるのは普通?原因と対処法を解説
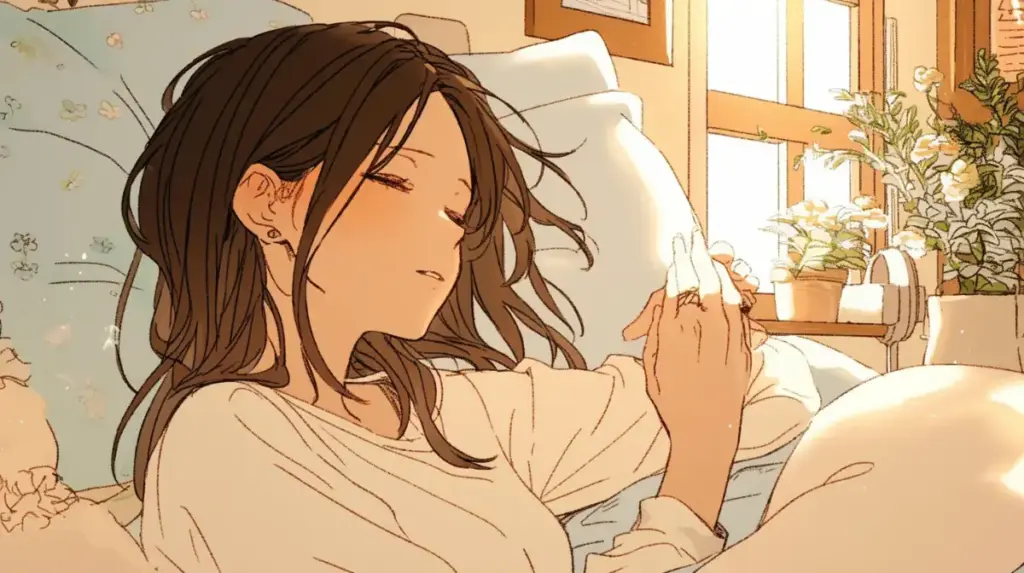
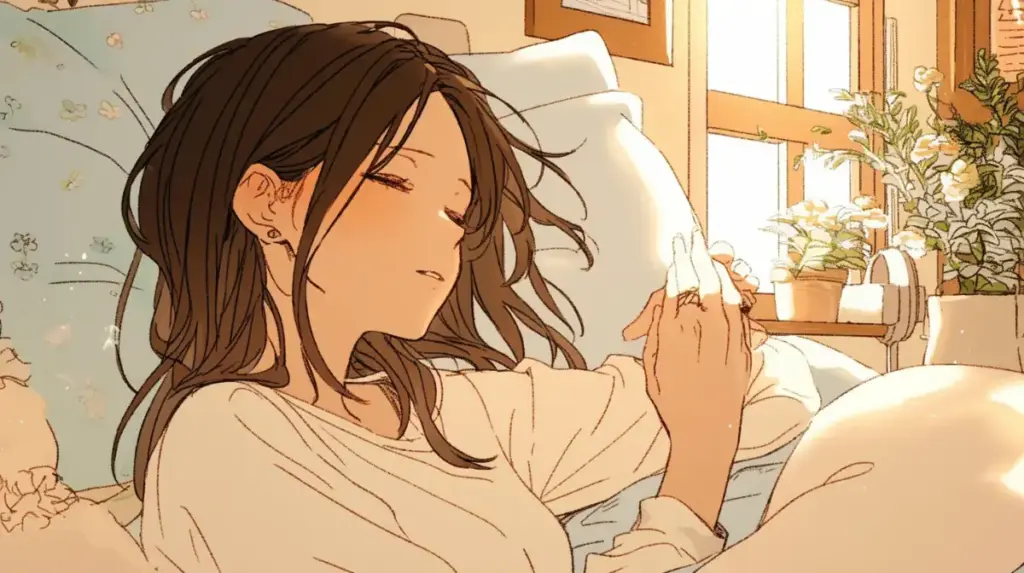
夜勤明けにずっと寝てしまう…。でもそれって、実はとっても自然なことなんです。
特に介護の現場で働いていると、心身ともにヘトヘトになるのは当たり前。
ここでは、夜勤明けの「寝すぎ」に悩む方に向けて、その原因と対処法を、僕自身の経験も交えて、わかりやすくご紹介していきますね。
原因①:身体が限界を迎えている
夜勤明けにずっと寝てしまう理由のひとつは、身体が本当に限界を迎えているからです。
介護現場では、利用者さんのナイトケア、急変対応、見守りなど、夜間も常に気が張っていて神経が休まりません。
そのため、夜勤が終わる頃には、頭も体もクタクタに疲れ切っているんですよね。
16時間以上の長時間労働が当たり前という現場では、「寝ないと回復しない」のがむしろ自然です。
僕自身も、夜勤明けは帰宅後すぐにベッドに倒れ込むようにして寝ていました。
だからこそ、「寝すぎかも」と悩む前に、「それだけ頑張ってる証拠だ」と受け止めてあげることが大切です。



まずはご自身を責めずに、「お疲れ様」と声をかけてあげてくださいね。
原因②:ホルモンと体内時計の乱れ
人間の体は、本来は夜に眠って、朝に起きるリズムが備わっています。
それをガラリと逆転させてしまう夜勤では、メラトニンやコルチゾールといったホルモン分泌も乱れがち。
このホルモンバランスの乱れが、「眠っても眠ってもスッキリしない」「寝だめしたい」と感じさせる原因になります。
特に、体温や血圧、消化の働きまでが影響を受けるので、全身のだるさや疲労感が残りやすくなります。



朝に光を浴びる、仮眠の取り方を見直すといった工夫で、少しずつ体内時計を整えることが回復の第一歩になりますよ。
原因③:生活リズムが崩れている
夜勤→明け→日勤といったシフトが続くと、もはや生活リズムはジェットコースター状態。
起きる時間も寝る時間もバラバラで、食事もタイミングがズレがち。
そんな中で「寝すぎた!」と焦っても、それは当然の結果です。
大事なのは、「いつ寝るか」よりも「生活のルールを一定に保つこと」なんです。



たとえば、夜勤明けは◯時まで仮眠して、夜はしっかり寝るなど、自分に合った“マイルール”を作ってみましょう。
原因④:職場の勤務体制が過酷すぎる
そもそも、あなたが働いている夜勤シフト自体が過酷すぎるという可能性もあります。
僕が働いていた小規模多機能ホームでは、16:00〜翌9:30というシフトで、丸2日分の業務を一晩でこなしていました。
一人夜勤なので当然、休憩や仮眠が取れない日もあって、翌朝はまさにゾンビ状態…。
こうした“構造的な疲労”に対して、いくら体調管理を頑張っても限界があります。
夜勤明けにずっと寝てしまうのは、「あなたが弱い」からではなく、「勤務形態がブラック」なせいかもしれません。



環境を変えることで、体も心もラクになるかもしれませんね。
自分の働いている環境がブラックかどうか他と比べてみたいという方はこちらの記事もご覧ください。


夜勤明けに寝すぎてしまう人の悩みと心理
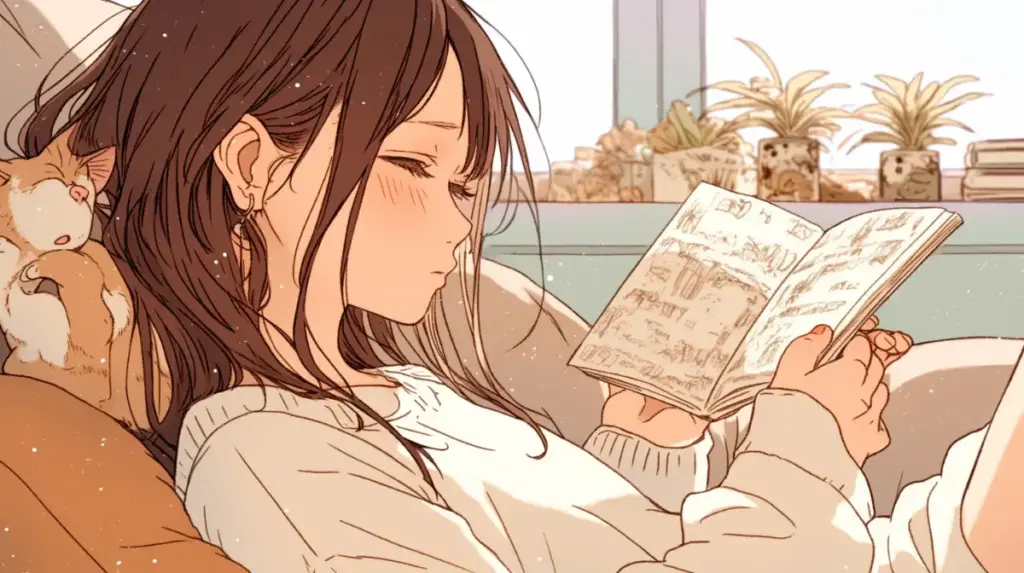
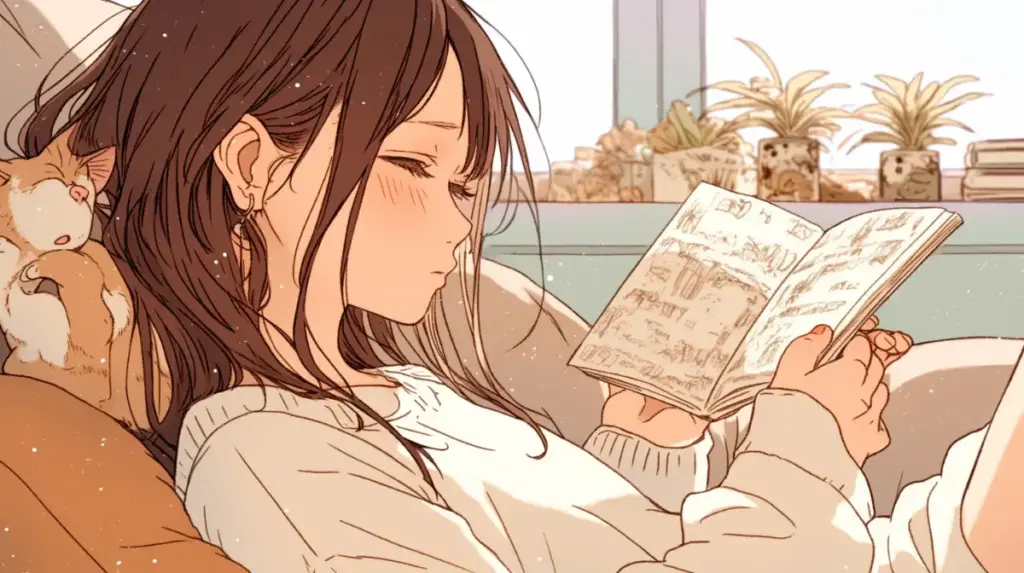
夜勤明けにたくさん寝てしまった後、ふと感じる“罪悪感”や“後悔”。
周りと比べて自分だけダメなんじゃ…と不安になってしまう方も多いんです。
でも、実はそれ、あなただけじゃないんですよ。
このパートでは、そんな心のもやもやを一緒に整理していきましょう。
もやもや①:罪悪感を感じる理由
「寝すぎてしまった…」と思った瞬間、なんだかダメな人間になった気がしませんか?
それ、罪悪感が原因なんです。
夜勤明けに寝るのは当然なのに、「もっと何かしなきゃ」「時間をムダにした」と思ってしまう。
でも、それって、他人の生活リズムと比較してしまってるからなんですよね。
大丈夫。あなたはちゃんと頑張っているし、必要な休息を取っているだけです。



罪悪感よりも、「よくやった、自分」と労わる気持ちを持ってあげましょう。
もやもや②:他人と比較して落ち込む
「あの人は夜勤明けでもジムに行ってるらしい…」
そんな話を聞くと、「自分はダメだ」と感じること、ありますよね。
でも、人によって体力や体質はまったく違うんです。
僕も同じように、自分と他人を比べて落ち込んでいた時期がありました。
でもある日、「他人と同じじゃなくてもいい」と気づいてから、ずいぶん楽になりましたよ。



あなたのペースで、あなたのリズムで、無理せずやっていきましょうね。
もやもや③:慢性的な疲労がある
夜勤を続けていると、「ずっと疲れてる気がする…」という状態に。
睡眠を取っても回復しない感覚、ありますよね。
それはもう、疲れが蓄積して“慢性疲労”になっているサインかもしれません。
回復するには、まず“疲れている自分”をちゃんと認めることから。



そして、「十分に寝る=悪いことじゃない」と思えるようになると、心も軽くなりますよ。
もやもや④:休日がつぶれてしまう
夜勤明けがそのまま“休み扱い”になっていて、実質、自由な時間がない。
そんな働き方、していませんか?
寝て起きたら夕方。何もできずに1日が終わってしまう…それ、かなり損してる気分になりますよね。
この「時間が消えた」感覚が、ストレスや自己否定につながりやすいんです。
まずは、“夜勤明けは休みではなく回復日”と捉えること。



そこから、少しずつ生活設計を見直していきましょう。
夜勤明けの寝すぎが招くリスクとは?


「たくさん寝たはずなのに、逆に調子が悪い…」
それは、寝すぎがもたらす“隠れたリスク”が原因かもしれません。
この章では、夜勤明けに寝すぎることで起こりやすい身体的・精神的な問題について、現場視点からご紹介していきます。
リスク①:生活リズムの乱れ
夜勤明けに爆睡してしまうと、その日の夜に眠れなくなり、生活リズムが崩れてしまいます。
「朝起きて、夜眠る」サイクルが崩れると、体内時計も大混乱。
とくに次の夜勤までの間隔が短いと、リズムを整える時間がなく、体も心もどんどん不調に傾いていきます。
僕も夜に寝付けず、深夜までスマホを見てしまうことが増え、疲れがどんどん蓄積していきました。



無理なく戻せる“リズムの基本”を意識して、短時間でもリセットする時間を意図的に作るようにしましょう。
リスク②:メンタルヘルスへの影響
寝すぎる → 何もできない → 自己嫌悪…そんな悪循環にハマっていませんか?
実はこのサイクル、うつ傾向を悪化させる要因にもなると言われています。
「世界保健機関(WHO) 職場のメンタルヘルス対策 ガイドライン(厚生労働省)」においても、夜勤や交代勤務における過酷なスケジュールはメンタルヘルスに影響リスクがあると指摘されています。
「何もしていないのに疲れている」自分を責めることは、メンタルにとって大敵です。



まずは自分をいたわって、必要な休息だったと肯定してあげましょう。
リスク③:食生活の不規則化
寝すぎた日は、朝ごはんも昼ごはんもタイミングがずれてしまいます。
結果として、1日1食になってしまったり、深夜に食べたりと、食生活が乱れてしまうんですよね。
こうなると栄養バランスも崩れやすく、体調不良の原因になってしまいます。
僕は寝過ごした日、夕方にコンビニで菓子パンとコーヒーだけ…なんて日もありました。



せめて「起きたら軽く何か口にする」を意識するだけで、健康への影響はかなり変わりますよ。
リスク④:人間関係への影響
夜勤明けに寝続けてしまうと、家族やパートナーとの時間が持てなくなり、コミュニケーションも減ってしまいます。
特に小さい子どもがいる方や、パートナーとのすれ違いが増える方も多いのではないでしょうか。
「家にいても寝てばかり」と思われてしまうと、心の距離もできてしまいがちです。
そうなる前に、「夜勤明けはこう過ごしたい」「この時間は一緒にいたい」と伝えることで、関係も少しずつ変わっていきます。



お互いのリズムを理解し合う工夫、大事ですね。
夜勤明けの上手な過ごし方・ルーティン5選
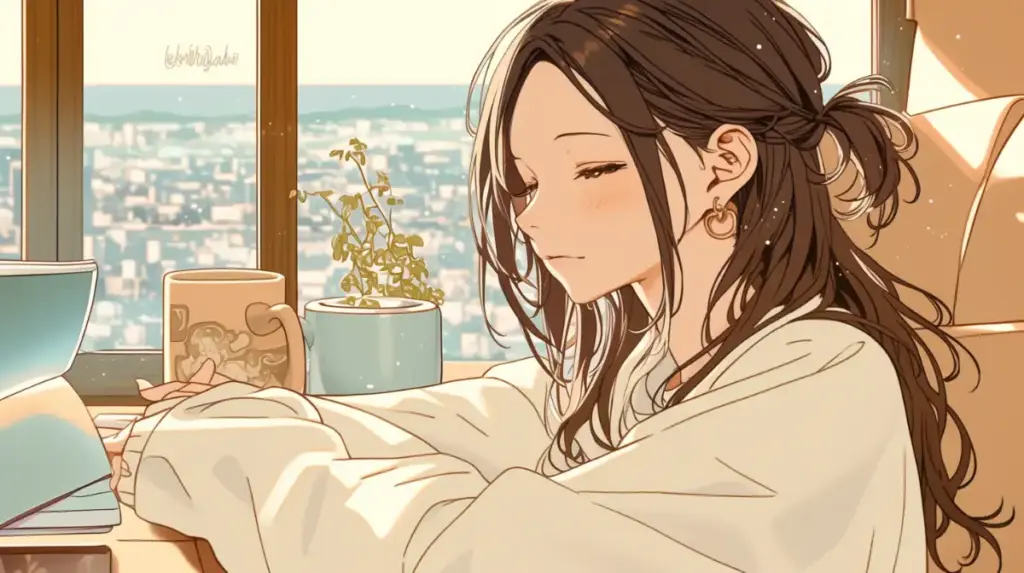
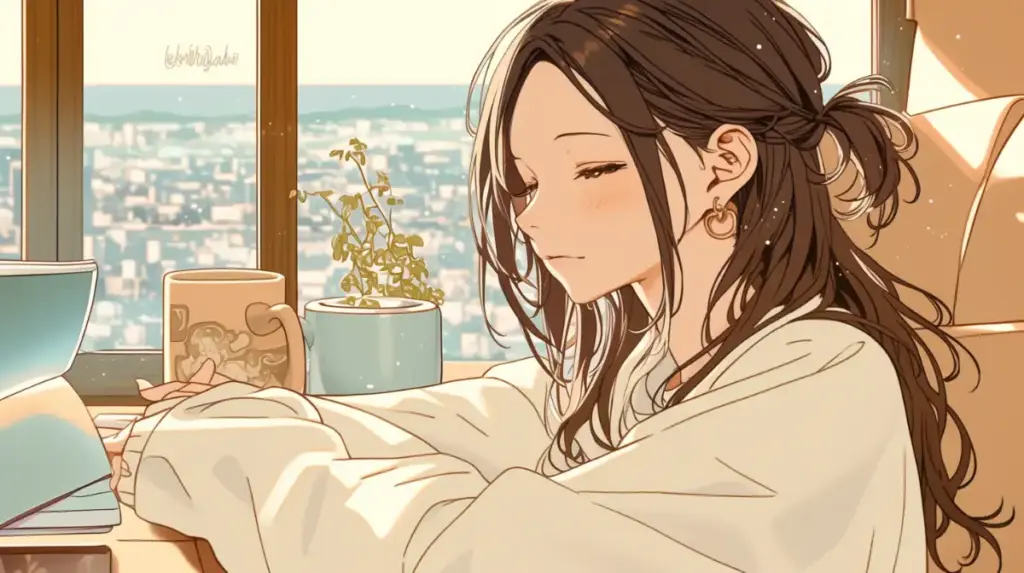
夜勤明けって、体も頭もクタクタで何も考えられないですよね。
でも、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、回復度合いが全然違ってきます。
ここでは、僕自身がいろいろ試して「これはよかった!」と思ったルーティンを5つご紹介します。
①:シャワーを浴びてリセット
夜勤明け、まずやるべきことは「シャワー」です。
汗やにおいを流すだけじゃなくて、頭をリセットして心を切り替える意味でも効果絶大。
僕は帰宅してすぐにぬるめのシャワーを浴びることで、体のこわばりがほぐれて一気にリラックスできました。
その後の睡眠の質もグンと上がりますよ。



熱すぎるお湯は逆に目が覚めてしまうので、ぬるめの温度がおすすめです。
②:軽めの食事で回復サポート
お腹がすいている時でも、夜勤明けは「軽めの食事」にしておくのがポイント。
重たいものを食べてしまうと、体が消化にエネルギーを使ってしまって、逆に疲れちゃうんですよね。
僕は、ゆで卵とおにぎり、バナナにヨーグルトあたりを常備して、さっと食べられるようにしていました。
たんぱく質と炭水化物をバランスよくとると、回復力もアップしますよ。



水分も忘れずにしっかりとりましょうね。
③:仮眠で疲労コントロール
ずーっと寝るのではなく、「仮眠」として短時間だけ眠るのもひとつの手です。
30〜90分を目安に眠ることで、深い眠りに入りすぎず、目覚めもスッキリしやすくなります。
僕はだいたい11時くらいに布団に入り、13時前には起きるようにしていました。
仮眠に加えて、夜しっかり眠ることで、生活リズムを戻しやすくなるんです。



スマホのアラームをセットして“寝すぎ防止”するのがコツです!
④:カフェインは使いすぎない
夜勤中にたくさんコーヒーを飲んでいた人は、明け方のカフェイン量が多くなりがちです。
そのまま帰宅してまたカフェインを取ってしまうと、せっかく眠りたいのに目が冴えてしまうことも…。
僕も以前は家に帰ってコーヒーを飲むのが日課でしたが、眠れなくて後悔したことが何度もありました。
夜勤明けは、ノンカフェインのハーブティーや白湯に切り替えると、自然と眠りに入りやすくなりますよ。



カフェインは“使いどころ”が大事なんです。
⑤:帰宅後のルーティンを固定する
夜勤明けは疲れすぎて、行動も頭もバラバラになりがち。
だからこそ、「ルーティン」を決めてしまうのがすごく有効です。
僕のルーティンは「帰宅→シャワー→軽食→仮眠→午後は自由時間」と決めていました。
これを“毎回同じ流れ”にすることで、体も心もスムーズに休息モードへ入っていけたんです。



習慣化って、本当に強い味方になりますよ。
夜勤明けがつらいあなたへ。改善が難しいなら環境を見直そう
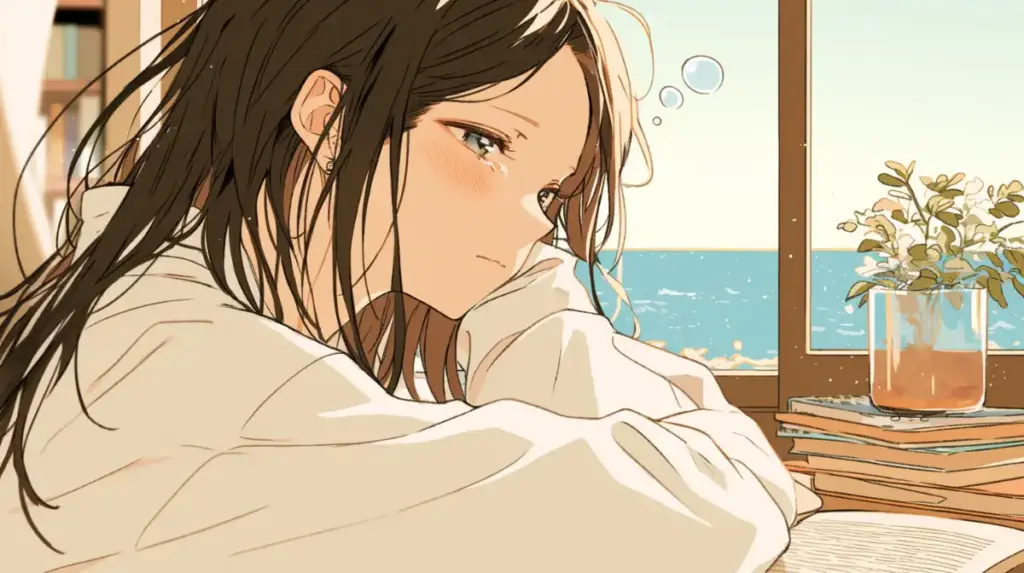
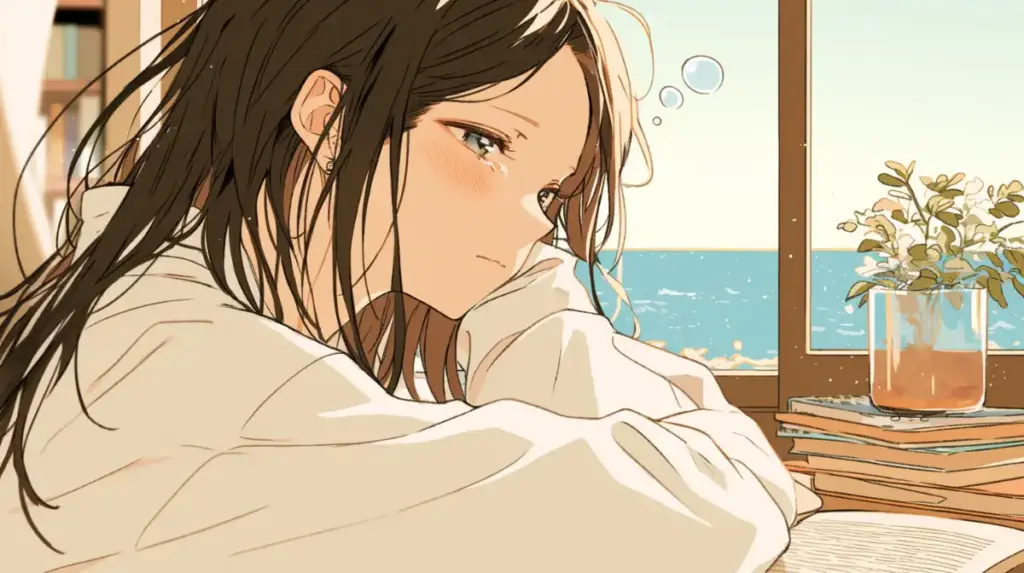
夜勤をがんばって続けてきたけれど、どうしても疲れが取れない。
頑張ってリズムを整えようとしても、体がついてこない。
そんな状態がずっと続いているなら…。少しだけ視点を変えて、「働く環境」を見直してみませんか?
ここでは、夜勤がつらすぎる人に向けて、前向きな“転職”という選択肢をそっとお届けします。
①:疲れが取れないのはあなたのせいじゃない
「休んでも疲れが取れない」「なんで自分だけ…?」って感じたこと、ありませんか?
でもそれ、あなたの体力や気合いの問題じゃなくて、環境の問題かもしれないんです。
僕も以前は「気合いが足りないのかな…」って落ち込んでました。
でも、環境を変えたら自然と体がラクになって、夜勤明けもずいぶん過ごしやすくなったんです。



つらいのは、あなたが弱いからじゃない。そう思ってくださいね。
②:夜勤の少ない職場もある
「介護=夜勤が当たり前」だと思っていませんか?
実は、夜勤のない職場や、日勤中心の施設もたくさんあるんです。
たとえば、デイサービスや訪問介護、小規模な有料老人ホームなどは、夜勤が少なめだったり、全くなかったり。夜勤自体の業務負荷が軽い職場もたくさんあります。



選べる働き方が実はもっとあるんですよ。
③:体質や年齢に合った働き方を選ぶ
20代の頃は夜勤明けでも元気だったけど、30代・40代になるとそうはいかなくなってきますよね。
年齢や体質に合わせて働き方を見直すのって、すごく大事なこと。
僕自身、若い頃は「夜勤も慣れだ」と思ってましたが、年齢を重ねるごとに「そろそろ無理かも」と感じるように。
無理せず、自分の体に合った働き方を選ぶことは、長く仕事を続けるためにも必要なんです。



“がんばりすぎない”って、大事なことだと思います。
④:思い切って転職して職場環境を変える
「環境を変えるのもアリかも…」と思った方へ、ここでこっそりオススメを紹介します。
僕がこれまでの経験や調査をもとにまとめた、「介護職向けのおすすめ転職エージェント10選」という記事です。
転職することによって、実際に夜勤から解放されたという口コミや、条件に合った職場を探せたという声も、それぞれのサイトに多く寄せられてます。
気になる方は、ぜひ下記リンクからチェックしてみてくださいね。





あなたにぴったりの職場が、きっと見つかりますように。
まとめ:夜勤明けにずっと寝てる自分を責めないで
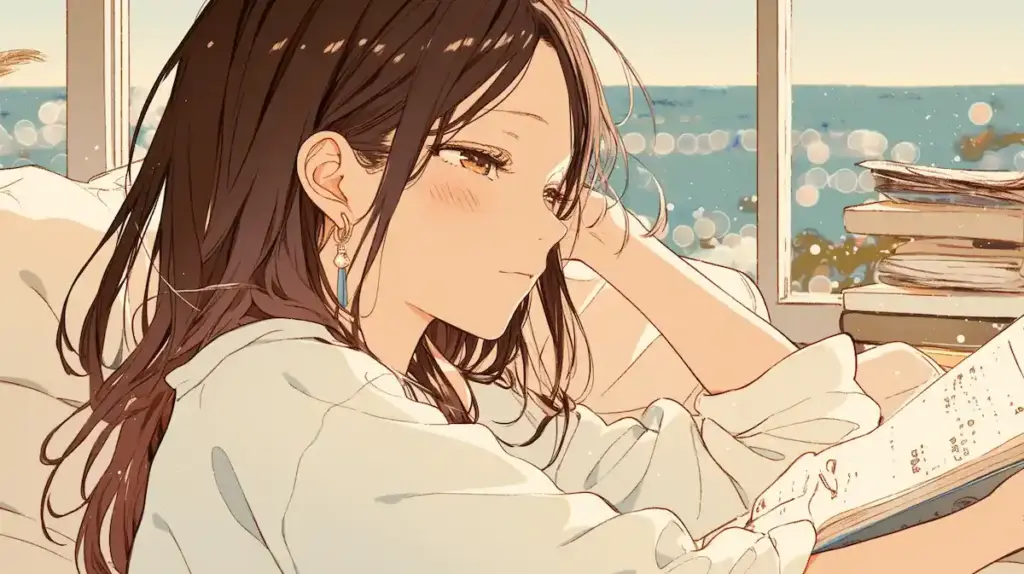
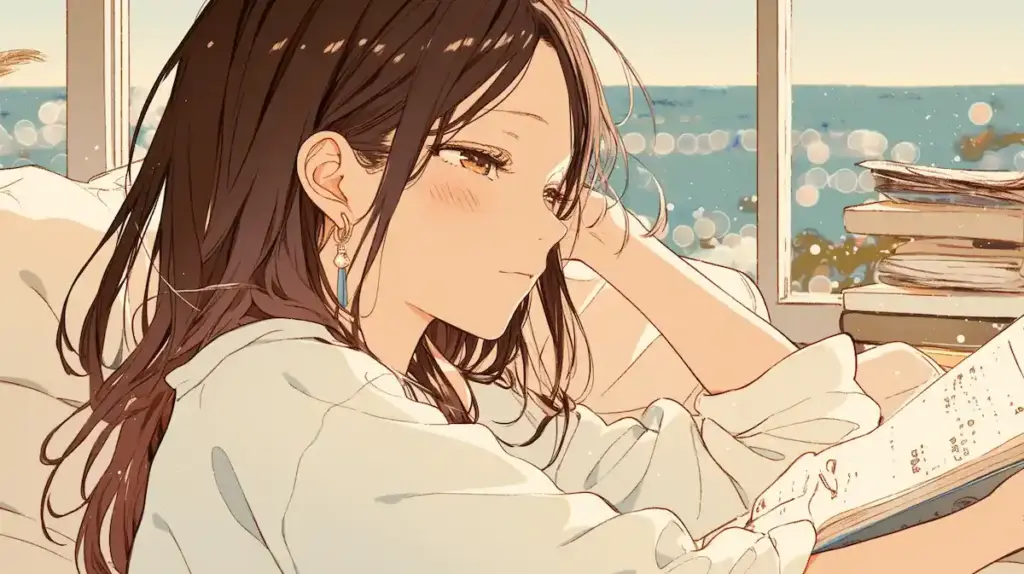
この記事のポイントをまとめます。
- 夜勤明けにずっと寝るのは身体の限界による自然な反応である
- ホルモンバランスと体内時計の乱れが寝すぎの原因となる
- シフトの不規則さが生活リズムを大きく乱す
- 過酷な勤務体制そのものが疲労の主因である
- 寝すぎによる罪悪感や自己否定感に悩む人が多い
- 寝すぎが続くとメンタルや人間関係にも悪影響が出る
- 少しの工夫で夜勤明けの疲れを軽減する方法はある
- 年齢や体質によって夜勤の負担は変化する
- 無理のない働き方を選ぶことが長く働くために必要である
- 環境が合わないなら転職という選択肢も前向きに考えるべきである
今回は「夜勤明けにずっと寝てしまう」という悩みに寄り添いながら、その原因や対処法をお伝えしてきました。
夜勤のある介護の仕事は、本当に体力も精神力も必要です。
僕自身も長く現場で働いてきたからこそ、みなさんのつらさがよくわかります。
たくさん寝てしまうのは、あなたの弱さじゃありません。 むしろ、それだけ頑張っている証なんです。
今回紹介した過ごし方や考え方を少しずつ試してみてください。
そして、「それでも限界かも」と感じたときは、 無理せず、働く環境を変えるという選択肢も持っていてほしいなと思います。
あなたにとって、もっと心と体が楽になれる場所が、きっとあります。
ほんの少しでも気持ちが軽くなっていたら嬉しいです。



今日も、本当におつかれさまでした。
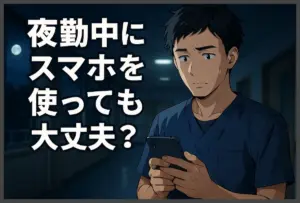
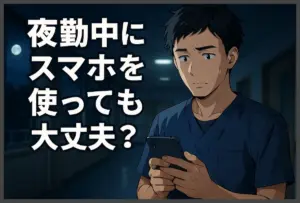

コメント