老人が口を鳴らすのはなぜ?介護のプロが原因と対策を徹底解説!
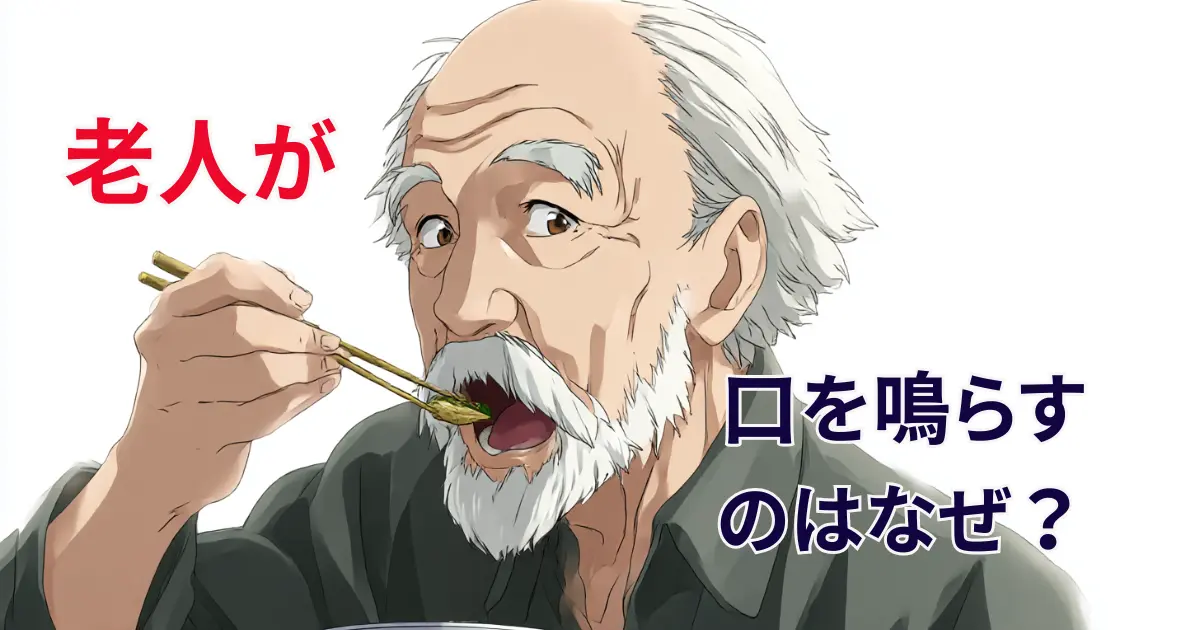
高齢の家族が突然「口を鳴らす」ようになったり、「口をくちゃくちゃと鳴らしてうるさい」と感じた経験はありませんか?
また、「くちゃくちゃ食べる音が気になる」「口をぴちゃぴちゃ鳴らすのは何かの病気?」と心配になることもあるでしょう。
こうした現象の背景には、単なるマナーの問題だけでなく、高齢による口腔機能の低下や、認知症による無意識な動作、そして病気の可能性まで、さまざまな要因が絡んでいる場合があります。
本記事では、老人が口を鳴らす原因を丁寧に解説するとともに、くちゃくちゃ音の理由や「チッチッ」と舌を鳴らす癖、さらには「クチャラー」と呼ばれる状態についても詳しく紹介。
介護の現場で実際に見られる事例を踏まえながら、認知症で口を鳴らすことがあるケースや、口をぺちゃぺちゃ鳴らす病気の可能性にも触れていきます。
 よーかん
よーかん不快に感じる音の背後には、気づいてあげるべきサインが隠れていることがあります。この記事を通じて、原因を正しく理解し、無理なくできる対策を一緒に探していきましょう!
- 老人が口を鳴らす主な原因とその背景
- 認知症などの病気によって口を鳴らすことがある理由
- 口腔機能の低下や入れ歯の影響による口音の発生要因
- 口を鳴らす癖に対する具体的な対策や対応方法
- 周囲が不快に感じるくちゃくちゃ音への心理的反応と配慮の方法
老人が口を鳴らすのはなぜ起こるのか


- くちゃくちゃ食べる音の原因とは
- クチャラーと加齢の関係性について
- 認知症で老人が口を鳴らすことがある
- チッチッと舌を鳴らす癖の正体
- くちゃくちゃ音がうるさいと感じる理由
くちゃくちゃ食べる音の原因とは
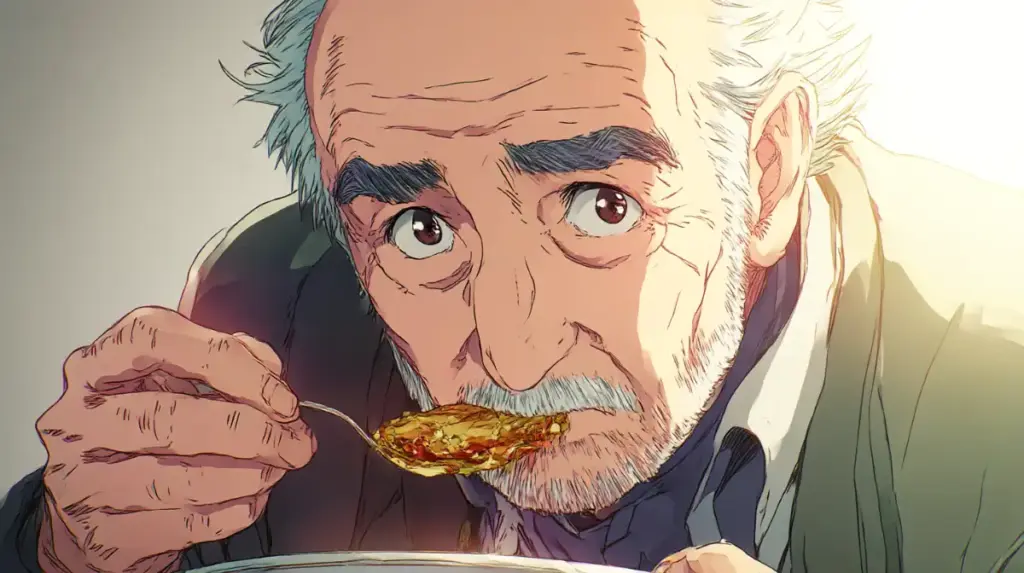
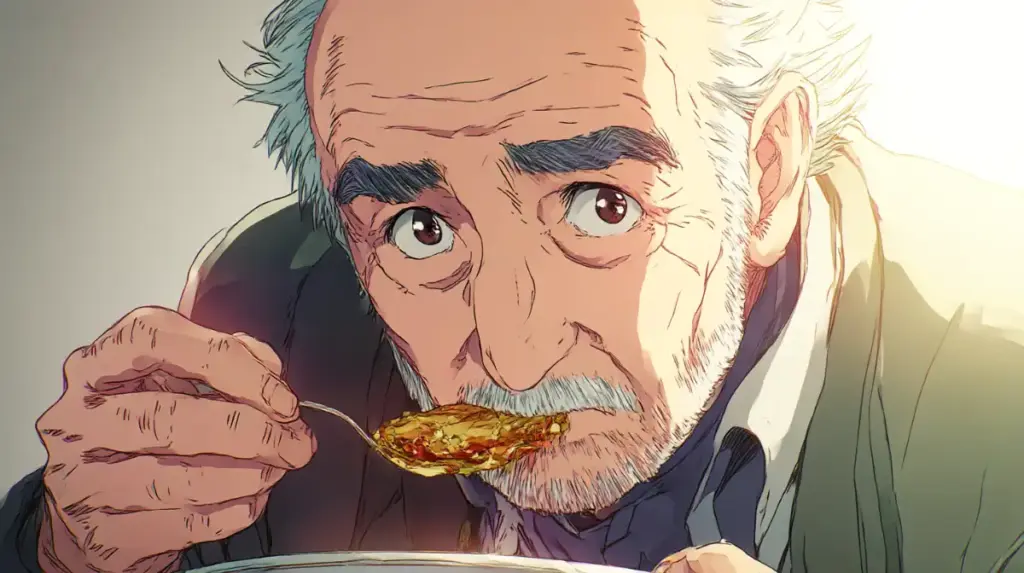
くちゃくちゃと音を立てて食べる行為には、いくつかの要因が絡んでいます。
口を閉じずに咀嚼する
最も多い原因の一つは、口を閉じずに咀嚼していることです。これは子どもの頃に食べ方のしつけが十分に行われなかったケースや、年齢を重ねて口の周りの筋力が衰えたことによるものです。
歯の状態が悪い
また、歯の状態が悪いことも大きな理由。入れ歯が合っていなかったり、歯が抜けたままで咀嚼が不十分だったりすると、口の動きが不自然になり、音が鳴りやすくなります。歯茎で噛むような動作は、どうしても強めの口音を伴いがちです。
口腔内の状態
他にも、唾液の分泌量の変化や、舌の使い方の癖も関係。高齢になると唾液が減少し、口内が乾燥しやすくなるため、食べ物をうまくまとめて飲み込めず、モグモグと長く噛み続ける傾向が出ます。このとき舌が上手く使えていないと、余計な音が出やすくなるのです。
食事中の姿勢
さらに、食事中の姿勢や顎の動かし方にも注目が必要。前かがみになったまま食べていると、咀嚼の際に口が開きがちになり、音が漏れやすくなります。これらの習慣が重なって、「くちゃくちゃ食べる」という状態を引き起こしているのです。
このように、「くちゃくちゃ音」の背景には、身体的・習慣的な要因が複雑に絡んでいます。食事のマナーという一言では片づけられない、高齢者特有の問題とも言えるでしょう。



原因を正しく理解し、適切な対応を取ることが、本人にも周囲にもストレスを減らす第一歩になりますね!
クチャラーと加齢の関係性について


クチャラーという言葉は、食事中に口を開けたまま咀嚼し、くちゃくちゃと音を立てる人を指します。一般的にはマナーの問題と見なされがちですが、高齢者に多く見られる場合には、加齢による身体機能の変化が背景にあることが多いのです。
口腔機能の低下
まず注目すべきは、口腔機能の低下です。加齢に伴い、口周りの筋肉が衰えると、しっかりと口を閉じて食べることが難しくなります。特に唇を閉じる「口輪筋」が弱くなると、無意識のうちに口が開いてしまい、咀嚼音が外に漏れやすくなります。本人にその自覚がないことも少なくありません。
歯のトラブル
また、歯の喪失や入れ歯の不具合も、クチャラーの原因になり得ます。歯が少なくなると、咀嚼するために顎を大きく動かす必要があり、その動きによって音が生まれやすくなるのです。さらに、入れ歯が合っていないと違和感が強くなり、噛むたびに音が響くことがあります。
聴力の低下
さらに、聴力の低下も一因です。高齢になると自分の咀嚼音が聞こえづらくなり、「どのくらい音を立てているか」に気づきにくくなります。そのため、周囲が不快に感じるほどの音を立ててしまっても、本人はまったく無自覚というケースがあるのです。
このように、クチャラーとされる高齢者には、マナーの問題というよりも、身体的な変化に伴うやむを得ない理由が隠れていることが多くあります。単に指摘するのではなく、背景を理解した上で、専門家のサポートや口腔ケアを取り入れることが求められるでしょう。



僕が仕事していた特養でもこのクチャラーの方は多数いました。要介護3以上ともなると、歯や口の機能もかなり衰えているので仕方ないんですよね。
認知症で老人が口を鳴らすことがある


認知症の進行に伴い、「口を鳴らす」という行動が見られることがあります。これは本人が意図しているわけではなく、認知機能の低下や脳の指令の乱れによって引き起こされる無意識の反復行動の一つです。
例えば、「チッチッ」や「ぴちゃぴちゃ」「くちゃくちゃ」といった音を繰り返し出す行為は、認知症の中期以降によく見られます。理由として、脳内での記憶や感覚の処理機能が低下し、「口を閉じる」「舌を動かす」などの動作の調整が難しくなってくるためです。また、不安感や落ち着かなさを紛らわすために、無意識に口を動かすという行動に至ることもあります。
さらに、幻覚や妄想の影響で、口の中に何かがあると感じてしまい、それを取ろうとするように舌や唇を動かす動作が表れることもあります。こうした行動が繰り返されることで、結果的に口を鳴らすような音が生じるのです。
ただし、こうした行為が見られたからといって、すぐに認知症と決めつけてはいけません。加齢に伴う口腔機能の低下や、歯の不具合なども同様の動作を引き起こすことがあるため、総合的な観察と医師の判断が必要でしょう。
このように、認知症の進行によって見られる口の動きや音には、本人のコントロールを超えた原因があります。周囲の人が「気持ち悪い」「うるさい」と否定するのではなく、医療や介護の視点から適切に対応することが求められます。



本人も好んで音を鳴らしているわけではないので、理解と支援の姿勢で、本人の尊厳を守ることも大切でしょう。
チッチッと舌を鳴らす癖の正体
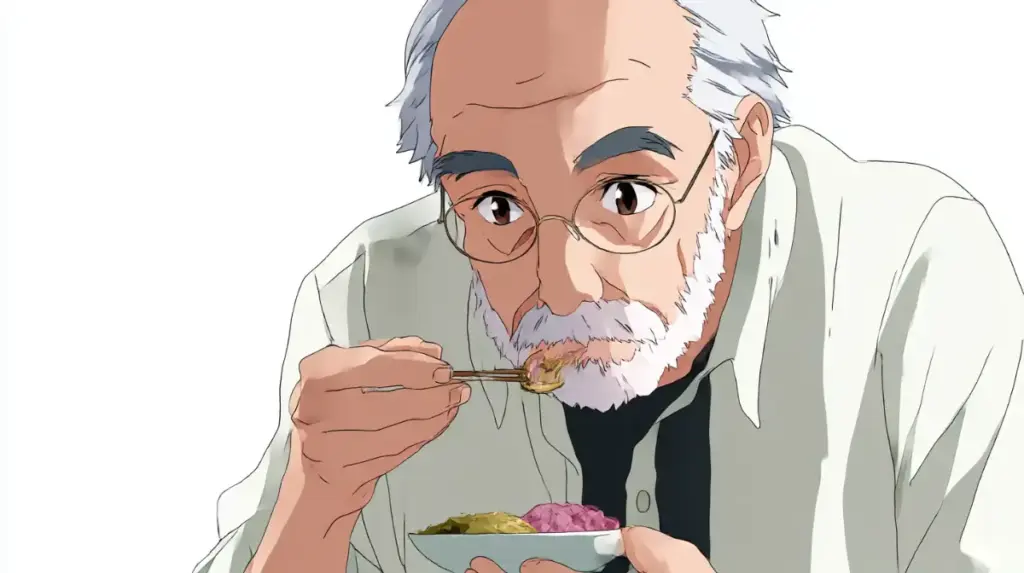
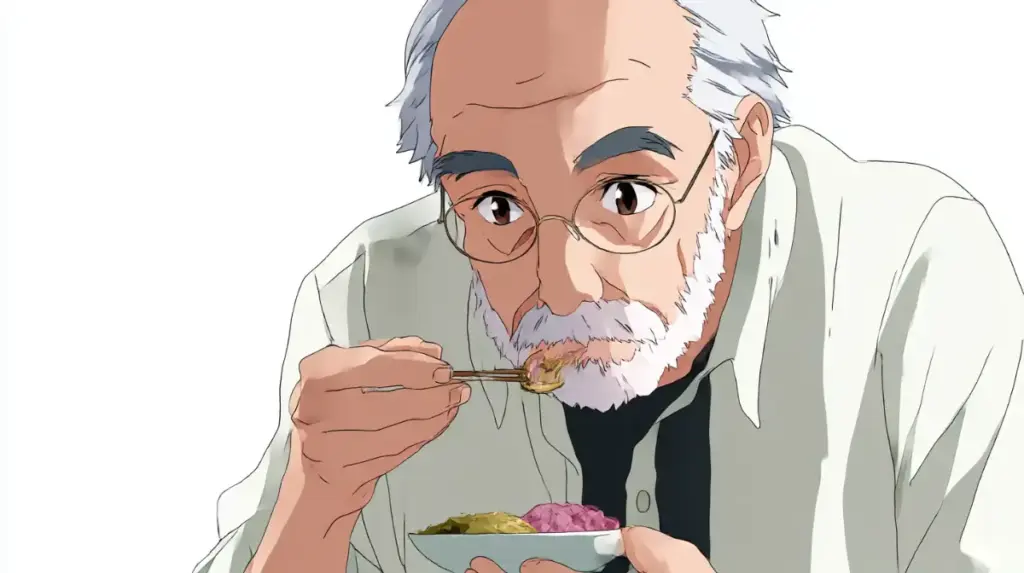
舌を「チッチッ」と鳴らす癖には、いくつかの異なる背景があります。一見するとただの癖のように思えますが、高齢者の場合は身体的な要因や無意識の動作が関係していることもあるため、慎重な観察が必要です。
まず考えられるのが、歯の間に食べ物が詰まっている場合です。高齢になると、歯の本数が減ったり、歯と歯の間にすき間ができたりすることで、食べ物が挟まりやすくなります。このとき、舌で取り除こうとすると、舌が歯や上あごに当たり、「チッチッ」という音が自然と発生します。これは特に入れ歯が合っていない場合や、歯周病などで歯茎が後退している方に多く見られる傾向です。
一方で、認知症の初期症状や常同行動の一種として、このような音を繰り返すこともあります。周囲の状況に関係なく舌を鳴らし続けるような場合は、口腔内の異常というよりも、精神的な落ち着きのなさや不安感が原因となっている可能性があるでしょう。本人はその行動に自覚がないため、注意を促すだけでは改善が見込めないこともあります。
また、単なる癖として定着しているケースも無視できません。長年の習慣で無意識に舌を鳴らしてしまう人もおり、この場合は加齢とは関係なく若年層にも見られます。しかし、高齢者の場合は加齢に伴う口腔機能の衰えや、感覚の鈍化が拍車をかけている可能性があります。
このように、「チッチッ」という舌打ちのような音には、歯のすき間の詰まりから来る実用的な動作、認知機能の変化による反復行動、そして単なる習慣と、さまざまな理由が隠れています。



音の頻度や場面を観察することで、背景を見極め、適切な対応につなげることが大切。必要に応じて歯科や医療の専門職に相談することで、症状の軽減や改善も期待できるでしょう。
くちゃくちゃ音がうるさいと感じる理由


「くちゃくちゃ」という咀嚼音は、特に静かな場面では非常に耳につきやすく、多くの人が不快に感じる音の一つです。これは単なるマナーの問題として片づけられがちですが、実際には人間の聴覚や心理的反応とも深く関係しています。
人はある特定の音に対して過剰に反応してしまう性質があります。たとえば、食事中のくちゃくちゃ音や、指で机をトントン叩く音など、反復性の高い生活音に対して「イライラする」「鳥肌が立つ」と感じる人は少なくありません。これは「ミソフォニア(音嫌悪症)」と呼ばれる心理的反応とも関連しており、音自体よりもその音を出している行動に対して強く嫌悪感を抱くケースが多いのです。
さらに、くちゃくちゃという音は「無自覚にマナー違反をしている人」を象徴する行為と見なされがちであり、それが他者への怒りや不快感を助長します。特に公共の場や家族の食卓など、音が共有される場面ではストレスの原因になりやすく、人間関係にまで影響を及ぼすこともあります。
また、同じ空間で生活する高齢者がこのような音を繰り返している場合、注意することが難しい状況もあるでしょう。身体的な機能低下が関係していると分かっていても、毎回くちゃくちゃと音を立てられると、気になってしまうのは自然な反応です。
こうしてみると、「うるさい」と感じるのは単に音量の問題ではなく、「その音が持つ意味」による心理的な反発が大きいといえます。相手を傷つけずに配慮するには、まずは本人の身体的・心理的背景を理解し、そのうえで必要に応じて医療・福祉の専門職と連携を取ることが望ましいでしょう。



音の問題は繊細なテーマですが、適切な理解と対応によって、共に過ごす時間をより穏やかなものにすることができます。
老人の口を鳴らす問題とその対策法


- 口をぺちゃぺちゃ鳴らす病気の可能性
- 口をぴちゃぴちゃ鳴らす原因と対処
- 口腔機能の衰えによる影響とは
- 口腔ケアと清潔保持でできる対策
- 医療機関の受診が必要なケースとは
口をぺちゃぺちゃ鳴らす病気の可能性


高齢者が無意識に「ぺちゃぺちゃ」と口を鳴らす場合、単なる癖や加齢による変化にとどまらず、病気の可能性も考慮する必要があります。特に、認知症やパーキンソン病など、脳機能や神経系に関わる疾患が関係しているケースもあります。
認知症の中には、落ち着きのない口元の動きや、意味のない繰り返し動作を伴うことがあります。これは「常同行動」と呼ばれ、同じ動作を何度も無意識に繰り返す症状です。口をぺちゃぺちゃと動かす行為もその一つであり、本人にその自覚がない場合が多く、周囲が異変に気づくことで初めて問題として浮かび上がります。
また、パーキンソン病では、口唇の動きに異常が出ることがあります。これにより、意図しない筋肉の収縮が起こり、唇や舌が震えるような動きを見せることがあります。その結果として、ぺちゃぺちゃと音が鳴ってしまうのです。
このような口の動きが見られる場合には、一度医療機関での診察を受けることをおすすめします。特に、「動作が以前と比べて増えた」「食事中でないのに口が動いている」といった変化に気づいたら、早めに神経内科や認知症専門のクリニックなどを受診することが望ましいでしょう。



パーキンソン病では飲み込みの機能にも影響が出ることがあるので注意が必要ですよ。
口をぴちゃぴちゃ鳴らす原因と対処


「ぴちゃぴちゃ」という口音は、食事中だけでなく普段の会話や休憩中にも聞かれることがあります。これは主に、唾液の動きや口の開閉の仕方に関係している音です。
高齢者では、加齢によって口腔機能が衰えると、唇をしっかり閉じる力や舌をうまくコントロールする力が弱まります。その結果、唾液が溜まりやすくなり、無意識に飲み込む動作や舌の動きが音として表れることがあります。特に、唾液の分泌が増えている人や、反対に口の中が乾燥しやすい人にも起こりやすいです。
また、入れ歯を使用している場合にも注意が必要。入れ歯と粘膜の隙間に空気や唾液が入り込むと、「ぴちゃぴちゃ」という音が出やすくなります。入れ歯が合っていないと、口の中の圧力が変わり、咀嚼や会話のたびに音が鳴ることがあります。
こうした音を減らすためには、まず口腔環境を整えることが大切。歯科で定期的に口の状態をチェックしてもらい、入れ歯の調整を行うだけでも改善が期待できます。さらに、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングや、唾液のコントロールを意識することで、自然と音が減ってくる場合もあります。



身近な人が音に気づいた際は、本人に直接指摘するのではなく、医師や歯科衛生士などの専門職を通じてさりげなくサポートしていくとよいでしょう。
口腔機能の衰えによる影響とは


加齢に伴って現れる「口腔機能の衰え」は、見過ごされがちな変化ですが、生活の質に直結する深刻な影響を及ぼします。口腔機能とは、噛む、飲み込む、話す、唾液を分泌するなど、口を使った一連の動作全体を指します。
口腔機能が衰えることで、日常生活に以下のようなさまざまな困難が生じるのです。
食事のしづらさ
まず大きな影響として、食事のしづらさが挙げられます。咀嚼力が低下すると硬いものを避けるようになり、柔らかい物ばかり食べるようになりがち。その結果、栄養が偏りやすくなり、筋力や体力の低下にもつながります。さらに、飲み込む力が落ちると「誤嚥(ごえん)」のリスクが高まり、誤嚥性肺炎など命にかかわる病気を引き起こす恐れもあるでしょう。
発生や会話のしづらさ
また、口腔機能の低下は発声や会話にも影響します。口や舌の動きが鈍くなると、言葉がはっきり出せず、聞き取りにくい話し方になってしまいます。これが周囲とのコミュニケーションの障害となり、外出や人との関わりを避けるようになれば、孤立感やうつ状態を招くこともあるのです。
ドライマウス
加えて、唾液の分泌が減少することによって、口内が乾燥しやすくなります。唾液には自浄作用や殺菌作用があるため、虫歯や口臭、口内炎といったトラブルも増えやすくなるでしょう。
このように、口腔機能の衰えは見た目以上に多くの影響を及ぼし、放置しておくと心身ともに大きな負担になります。



早めに気づき、適切な対応を取ることが健康寿命を延ばすためにも非常に重要ですね。
口腔ケアと清潔保持でできる対策


高齢者の口のトラブルや音の問題を改善するうえで、日常的な「口腔ケアと清潔保持」はとても効果的です。特別な道具が必要なわけではなく、毎日のちょっとした習慣の積み重ねが、口の健康を守る第一歩となります。
まずは歯磨きやうがいを丁寧に行うことが基本です。特に夜間のケアは重要で、就寝中は唾液の分泌が減るため、口腔内が細菌の温床になりやすくなります。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシや舌ブラシを使って細かい部分まで清潔に保つように心がけましょう。
また、入れ歯を使用している方は、毎日の取り外しと洗浄が不可欠です。入れ歯の内側や金具の部分に汚れがたまりやすいため、放っておくと口臭や炎症、誤嚥性肺炎の原因にもなります。就寝時は必ず外し、水または専用の洗浄液につけておくことが推奨されます。
よく、入れ歯をつけっぱなしの人がいますが、きちんとケアをしないとトラブルになってしまうので、僕もよく「入れ歯のケア」についてアドバイスしています。
清潔保持に加えて、口周りの筋肉を意識的に動かすことも大切。例えば、「パタカラ体操」や、頬をふくらませる・すぼめるといった簡単な動作を繰り返すだけでも、口輪筋や舌の筋力アップにつながります。こうしたトレーニングは、咀嚼音や舌打ち音の改善にもつながる可能性があり、介護の現場でも日常的に行われていますよ。
さらに、水分をこまめに取ることや、唾液の分泌を促すためのガムやタブレットの活用も有効。これらを取り入れることで、口腔内の乾燥や粘つきによる不快音の予防にもつながります。
このように、日々の口腔ケアは病気の予防だけでなく、音の問題や見た目の清潔感、コミュニケーションのしやすさにも良い影響を与えます。



大げさな対策ではなく、毎日できる小さな工夫から始めてみましょう。職員や介助者も一緒に楽しみながら、口腔体操やトレーニングを行うと毎日続けやすいですね!
医療機関の受診が必要なケースとは


口から異音がする、または口の動きに違和感がある場合、すべてが年齢による自然な変化とは限りません。中には、医療機関での診察が必要なケースも存在します。早期に対応することで、生活の質の低下や重症化を防ぐことができるでしょう。
まず注意すべきは、音の変化が急に現れた場合です。特に今までなかった「チッチッ」や「ぺちゃぺちゃ」といった音が突然増えた場合、脳神経に関わる疾患や、歯・口腔内の異常が隠れている可能性があります。
飲み込みの機能に問題が見られるときも要注意。むせやすくなった、食べ物が口に残る、飲み込むのに時間がかかるといった症状がある場合、嚥下機能の低下や誤嚥のリスクが疑われます。これを放置すると、誤嚥性肺炎といった重篤な病気に発展する可能性もあるため、専門の医師に相談することが大切です。
また、認知症の可能性がある場合も、専門機関の受診が必要でしょう。口を常に動かしている、食事以外の場面で舌を動かしている、話しかけても反応が鈍いなど、日常生活に支障が出るような行動があれば、神経内科や認知症外来での診察が有効です。
このように、口のトラブルが単なる癖や老化現象と片付けられない場合には、早めに医師や歯科医師の判断を仰ぐことが安心につながります。



どの診療科にかかればよいかわからない場合は、地域のかかりつけ医や僕らケアマネに相談してみるのも一つの方法ですよ。
老人が口を鳴らす原因と対策を総まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 口を閉じずに咀嚼することで音が出やすくなる
- 歯の欠損や入れ歯の不具合で咀嚼音が発生しやすくなる
- 加齢により口周りの筋肉が衰えると口が開きやすくなる
- 唾液の量の変化が口の中の音に影響を与える
- 舌の動かし方の癖が余計な音を生むことがある
- 姿勢や顎の動かし方が音の発生に関係している
- 聴力の低下により自分の音に気づきにくくなる
- 認知症により無意識に口を鳴らす行動が現れることがある
- 歯のすき間に挟まったものを舌で取ろうとして音が出ることがある
- 咀嚼音に対する不快感は心理的な要因とも関連する
- 入れ歯と粘膜の隙間から音が出ることがある
- パーキンソン病など神経疾患が原因の場合もある
- 口腔機能の衰えは食事・会話・健康全般に影響を及ぼす
- 毎日の口腔ケアで咀嚼音や不快音の予防につながる
- 異変がある場合は歯科や医療機関の受診が望ましい

コメント