介護職があほらしいと感じたら読む記事|20年働いてる僕のリアル
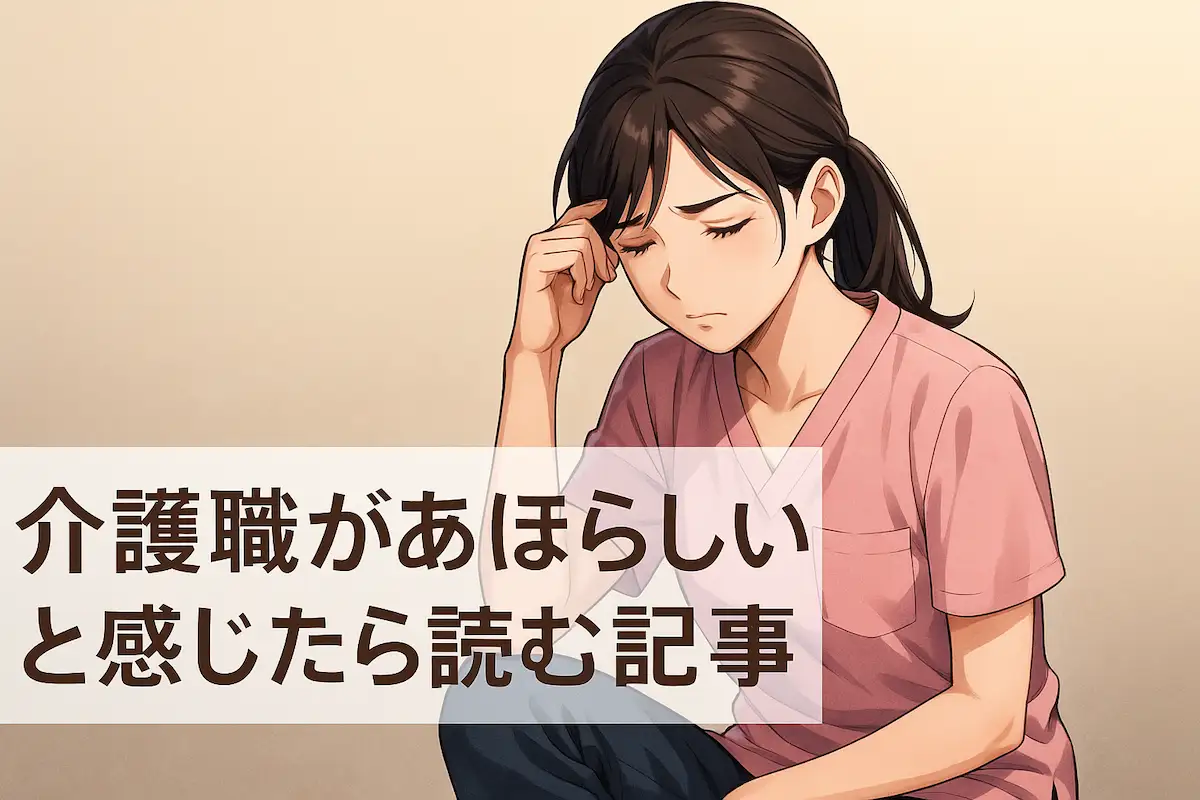
 あんこ
あんこ「介護職、なんだかもうバカバカしい…」
そんな気持ちを抱えながら、今日も出勤していませんか?
誰かのためになる仕事。やりがいのある仕事。そう信じて飛び込んだはずの現場で、
- 感謝されない
- 理不尽な人間関係
- 暴言や暴力
- がんばっても評価されない
こんな毎日に心がすり減って、「自分の人生、これでいいのか?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
僕も、そんな想いを何度も経験してきました。
介護歴20年、ケアマネ13年。現場で噛まれ、理不尽に怒鳴られ、やるせなさに涙が出そうになった夜もありました。
この記事では、そんな僕のリアルな体験をもとに、「介護職があほらしい」と感じたとき、どうすればいいのか?
その答えを、同じ業界で働くあなたに向けて、心を込めて書きました。



誰にも言えない気持ちを、少しだけ、ここで吐き出してみませんか?
- 「あほらしい」と感じるのは自然なことで、自分がおかしいわけではない
- 現場には理不尽や不公平が多く、それが多くの人の悩みになっている
- 介護職を辞めるだけでなく、経験を活かした転職も現実的な選択肢
- 心を守るための行動は甘えではなく、自分を大切にする判断
介護職があほらしいと感じたあなたへ|共感と解決策を語ります


「介護職 あほらしい」と検索した方は、きっと今、精神的にも肉体的にも限界を感じているのではないでしょうか。
ここでは、そんなあなたの気持ちにとことん寄り添いながら、少しでも心が軽くなるような視点と、現実的な選択肢をお伝えしていきます。



それでは順に見ていきましょう。
①「介護職 あほらしい」と検索したあなたの本音とは?
誰にも言えないけど、「なんでこんな仕事やってるんだろう…」と感じた瞬間、きっとあると思います。
それを「甘え」や「弱音」と言う人もいるかもしれませんが、僕は断言します。それは心が出している“正直なサイン”です。
介護の現場は、理不尽なことだらけです。感謝もされない、報われない、暴力を受けても守ってくれる人はいない。そんな中で「頑張り続けろ」なんて、無責任すぎますよね。
あなたが「介護職をあほらしい」と思ったのは、“ちゃんと感じる力が残っている証拠”です。



そしてこの記事は、その声を無視しません。一緒にその気持ちを見つめ直していきましょう。
②あほらしいと感じるのはあなただけじゃない
実はこの言葉、現場経験者の多くが心の中でつぶやいたことがあるフレーズなんです。
僕自身、20年この業界にいて、現場のリアルをたくさん見てきましたが、「これ、あほらしすぎるだろ…」と感じる場面は1つや2つじゃありませんでした。
詳しくは後述しますが、例えばこんなあほらしいと思う瞬間がありました。
- 一人夜勤で仮眠も取れず、掃除が甘いと怒られる
- ミスをしたときだけ、全職員の前で怒鳴られる
- 処遇改善加算は介護職だけ。ケアマネには一切恩恵なし
- 利用者に噛まれて出血→謝罪もケアもゼロ
こんな毎日を過ごしていたら、「なんで自分ばっかり?」と思って当然です。
あなたが感じている“あほらしさ”は異常じゃなく、むしろ「正常な感覚」です。



本音を出していいんです。それを否定する人からは、少し離れてみましょう。
たとえば、入浴介助ばかりというように偏った業務ばかりをやらされることも、「あほらしくてやってられない」と思ってしまいますよね。
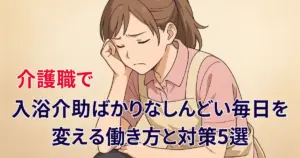
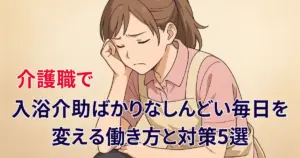
③辞めたいのに辞められない…その理由を整理しよう
「もう限界」「でも辞められない」この気持ちの板挟み、苦しいですよね。
なぜ辞められないのか?その理由を一緒に整理してみましょう。
- 次の仕事が見つかるか不安
- 資格や経歴が他の業界で通用するか不安
- 周囲に「逃げ」と思われるのが怖い
- 生活費が必要。とりあえず働き続けるしかない
どれももっともな理由ですし、僕も同じように感じていました。
でも、立ち止まって考えてほしいのです。「これ以上、ここにいて自分は幸せになれるか?」と。



それが「NO」なら、選択肢を増やすことを考えてもいいと思うんです。
④「甘えじゃない」プロの視点から見た“普通の反応”
「辞めたい」「つらい」「なんで私だけ…」そんな気持ちを持つのは、何もおかしいことではありません。
むしろ、介護の現場で“あほらしい”と思うのは、感受性がしっかりしている証拠なんです。
僕は管理職も経験しながら、何人もの職員の面談や退職相談に乗ってきました。
「やる気が出ない」「朝が怖い」「誰にも感謝されない」…。こういう相談は、本当に多いんです。
心が壊れる前に、「あほらしい」と気づけたあなたは、ちゃんと“ブレーキ”が効く人です。
その感覚、どうか大切にしてください。壊れるまで働かなくていいんです。



そして、必要ならこの記事の後半で紹介する“抜け出す選択肢”も参考にしてくださいね。
介護職をあほらしいと感じたリアルな現場体験


僕が20年の介護キャリアの中で「これはさすがにあほらしい」と感じた瞬間は、一度や二度じゃありません。ここでは、実際にあった4つの出来事を共有します。
現場のリアルな理不尽さや、心がすり減る出来事。それを「そんなの普通だよ」と言われたとき、本気でこの業界に絶望しそうになりました。
でも今では、「誰かにこの気持ちをわかってほしい」「これからこの道に進もうとする人に知っておいてほしい」と思えるようになったんです。



それでは順番にご紹介します。
①新人時代に理不尽ないじめを受けた話
これは僕が老健で新人として働き始めた頃の話です。
僕は当時、右も左もわからないまま現場に飛び込んで、理学療法士のおばさん職員と一緒になる機会が多かったんですね。
最初はあいさつも交わしていたんですが、徐々に明らかな“無視”が始まりました。
そのうち、社内メールでの名指し指摘、みんなの前で大声でミスを叱責されるなど、あからさまな“イビリ”に変わっていったんです。
周囲も見て見ぬふり。僕は完全に孤立しました。



僕よりも20歳近く上の人だったので「大の大人が何やってんだよ…」と思ったとき、心の中で“あほらしい”という言葉がはっきり浮かびました。
このときの体験談はこちらの記事で詳しく紹介しているので読んでみてください。
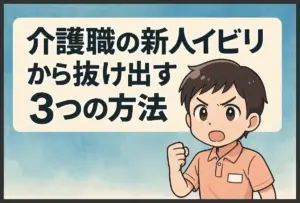
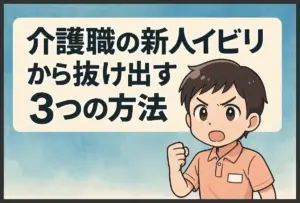
②夜勤での掃除ストレスと小姑職員
小規模多機能ホームで夜勤に入っていたときのことです。
夜勤中は一人体制。仮眠もほとんど取れず、介護記録・見回り・トイレ介助・急変対応まで全部自分でやらなきゃいけない。
それに加えて「水回り掃除」も業務に入っていたんですが、ある日ちょっと手を抜いたんです。正直、意識がもうろうとしてたんですよ。
そしたら朝に早番で来たおばさん職員に、洗面台の水垢やら排水口の汚れやら、こと細かく指摘されました。
「小姑かよ…」って、正直思いました。
そのとき感じたのは、「一人夜勤で必死に回して、命のケアもして、それでも水垢一つで文句言われるなんて…」という徒労感。



掃除よりも大切なやるべきことはたくさんあるだろうって思いました。まさに、バカバカしい、あほらしい、の極みです。
長い経験の中で、おばさん職員との付き合い方や、安全な夜勤の手の抜き方などを考えて実践してきました。こちらの記事でそれぞれまとめてあるので、ご覧ください。


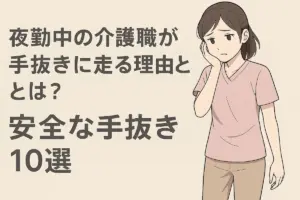
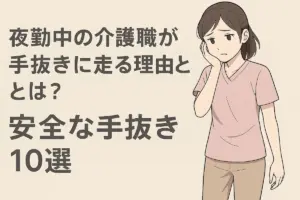
③ケアマネは給料面で割に合わない現実
僕は今、ケアマネとして働いていますが、給料の面だけを見ると「あほらしいな」と感じることが多いです。
介護職員には処遇改善加算がつき、ここ数年で確実にベースアップが進んできました。夜勤手当や資格手当なども含めると、かなり手厚くなってきています。
でもケアマネには、その恩恵がほぼないんです。
責任は重い。制度は複雑。書類は膨大。地域連携も求められる。
昔は介護職からステップアップという位置づけにあったケアマネが、給料で逆転されてしまう現実。
「じゃあ誰がケアマネなんてやるんだよ?」って、思いませんか?



好きだから続けてますが、冷静に考えればこの職種、完全に割に合ってないんですよね。実際にケアマネ不足も深刻です。
④噛まれたのに誰も守ってくれなかった話
老健で働いていた頃、男性の利用者に腕を噛まれたことがありました。
認知症の方でしたが、脳血管性で、判断力は残っているタイプ。つまり、明らかに“わざと”だったと思います。
僕の腕は出血し、外来で受診するレベルのケガでした。
当然、家族からの謝罪も、本人からの一言もありませんでした。
それ以上にショックだったのが、上司たちの対応。「まあ、気をつけよう」で終わりです。
職員が被害に遭っても、施設は守ってくれない。
このとき僕は、「ああ、この業界、マジであほらしいな」と心底思いました。



感情より先に、スーッと冷めたような、諦めの感覚があったのを覚えています。
なぜ介護職はここまで“あほらしい”と感じさせるのか?


ここでは、僕が長年この業界で働いてきて、ずっと感じてきた「構造的な問題」について触れていきます。
誰か一人が悪いとか、個人の問題ではなく、仕組みや文化そのものに原因がある。そう感じる場面が本当に多かったんです。
「なんでこんなことが当たり前のように放置されているんだろう?」と、呆れたり怒ったりしながら、でも誰も声を上げないから変わらない。
その“終わらないあほらしさ”の正体を、4つの視点から整理してみます。



1つずつ、詳しく解説していきます。
①制度の不備が職員にしわ寄せされる構造
介護保険制度は、ある意味すごくよくできています。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、サービスを細かく分類して、給付管理まで一元化されています。
でも、現場からするとこの制度、あまりにも現実とズレすぎてるんです。
例えば「訪問は20分未満だと点数がこれだけ」とか、「モニタリングは月に1回必須」とか、書類の山をこなすための形式主義が蔓延していて、本当に必要な支援に時間が割けないことも多いです。
そして結局、現場で働く人間が、無理な運用や理不尽なスケジュールを押しつけられる構造になっている。



制度の穴を現場の努力でカバーすることが“美徳”になってるのって、あきらかにおかしいですよね。「あほらしい」と感じるのも当然なんです。
②人間関係が仕事の本質を壊している
介護って、本来は「人を支える」素晴らしい仕事のはずなのに、現場の人間関係の悪さでその魅力が台無しになってしまうことがよくあります。
僕も理不尽ないじめや、上下関係のきつい空気、派閥争いに巻き込まれたことがあります。
一人がミスをすれば、「あの人は仕事できない」と陰口をたたかれ、気がつけば孤立してる。
新人が育たないのは、環境が悪いせいなのに、「最近の若い子は根性がない」と言われて終わる。
まるで“昭和の部活”のような体質が残ってる現場も少なくありません。



人を助ける仕事なのに、職員同士が消耗しあってる…。やっぱりあほらしいと感じて当然なんです。
③がんばっても報われない評価システム
どれだけ熱意を持って働いても、誰かのために時間をかけても、給料はほとんど変わりません。
僕がケアマネとして経験したのは、たとえば「独居で複雑なケース」でも「家族との調整が大変なケース」でも、月に担当している人数が同じなら、報酬は一律ということ。
介護職員も、利用者対応や家族対応を頑張っても、業務評価はほぼなし。ミスやトラブルがあると減点されるけど、プラスの評価はない。
つまり、「頑張った分だけ得をする」じゃなくて、「頑張っても何も変わらない」構造なんですよね。



この評価の仕組みそのものが、働く人のやる気を削ぎ、心をすり減らす大きな原因になってると思います。
④介護職の「やりがい信仰」がプレッシャーになる
介護の業界には、昔から「やりがいがあるからやってるんでしょ?」という文化があります。
僕も新人の頃、「給料じゃない、気持ちでやるんだよ」と先輩から言われたことがあります。
でも今ならハッキリ言えます。 やりがいだけじゃ、人は働き続けられない。
命を預かる仕事。暴力や暴言にさらされることもある。体を壊すリスクもある。
それでも「感謝されるから」「人の役に立てるから」と、気持ちだけで我慢し続けることが美徳にされている。
それが結果的に、職員が声をあげられなくなる空気をつくり、離職を加速させていると思うんです。



「あほらしい」と感じるのは、心が壊れかけているサインでもあるけど、本当はすごく健全な感覚だと思っています。
それでもあなたにできる“あほらしいから抜け出す選択肢”とは?


ここまで読んでくれたあなたは、きっと今、すごく疲れていると思います。
「あほらしい」と感じる職場に、毎日足を運んでいること自体が、すでにものすごく頑張っている証拠です。
でも、「辞める=逃げ」ではありません。
むしろ、“次の一歩”を考え始めた時点で、あなたはすでに前に進んでいるんです。
この章では、僕自身も考えたり使ってきた「抜け出すための選択肢」を、4つの視点からご紹介します。
①辞める前に考えるべき「逃げではない」判断
「辞めたいけど、自分が甘えてるだけじゃないか」「もっと頑張ってる人がいるのに…」
そんなふうに自分を責める気持ち、僕も何度も感じたことがあります。
でも、介護の現場って、そもそも心と体をすり減らしやすい構造になってるんですよ。
逃げるんじゃなく、“安全な場所に移動する”だけです。「根性がない」とか「甘え」じゃないんです。
あなたが「無理だ」と思ったときは、それが心の限界が近いサイン。



そこから抜けることは、勇気ある判断なんです。
②他職種への転職で介護経験を活かす道
介護職の経験って、実はすごく他業界でも評価されるスキルなんです。
たとえばこんなスキルが、実は高く評価されています。
- コミュニケーション力(相手の気持ちを汲み取る力)
- 調整力(家族・医療・多職種連携など)
- 体力・メンタルの強さ
- 計画的に動く力(ケアプラン・スケジュール管理)
これらは、福祉業界に限らず、たとえば
- 一般企業の受付・事務
- 医療事務やクリニックスタッフ
- サポートセンター・カスタマー対応
- 福祉用具の営業・管理職
- 障害福祉や就労支援系の仕事
など、多くの業種で歓迎されているスキルです。
僕の知人でも、「介護職しかやったことない」と言っていた人が、今では法人事務職や福祉用具の営業などで活躍しています。



介護しかできない、なんて思い込まなくて大丈夫です。
③今すぐ使える転職支援サービスの活用方法
僕が本気でおすすめしたいのは、介護系に強い転職エージェントの活用です。
というのも、ハローワークや自力検索だと、どうしても“同じような職場”を選んでしまいがちなんですよ。
でも転職エージェントを使えば、以下のようなサポートが受けられます。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 非公開求人紹介 | 条件の良い求人はネットに出ていないことが多い |
| キャリア相談 | 自分の強みを一緒に整理してくれる |
| 面接サポート | 面接で言うべきこと、避けるべきことも教えてくれる |
| 給与交渉 | 自分から言いづらいことも代行してくれる |
もちろん、必ず転職しなければいけないわけじゃないんです。
「情報だけ聞いてみる」「今の職場と比べるために相談だけしてみる」
まずはそれだけでも全然OKです。



僕の友人も過去に利用して、「ああ、他にも道はあるんだ」と思えたことで心が楽になってました。
④まずは情報を集めて、自分を守る準備をしよう
いきなり辞める必要はありません。
でも、「いつでも動ける状態」を作っておくことは、心の余裕に直結します。
たとえば
- 履歴書や職務経歴書をざっくり作っておく
- 自分のスキルや経歴を棚卸ししてみる
- 気になる職場の口コミを定期的にチェックする
- エージェントにだけ登録しておく(求人だけ見る)
「辞める覚悟」じゃなくて、「選択肢を持っておく」ことで、驚くほど気持ちが楽になります。



いつでも逃げられると思えると、人は不思議と、そこまで追い込まれなくなるんです。
介護の転職エージェントは数も多く、どこに相談したら良いか悩んでしまうと思うので、おすすめをまとめておきました。ご覧ください。


最後に伝えたいこと|あほらしいと思うのは“当然”です


ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
もしあなたが「介護職なんて、もうあほらしい」と感じているのなら。それは、あなたの感受性が壊れていない証です。
「人のために」と思って入った世界で、自分がどんどん消耗していく。
それでも我慢して、「まだ頑張れる」「甘えちゃいけない」って、ずっと自分に言い聞かせてきたんじゃないでしょうか。



でももう、頑張らなくてもいいんです。
①心を壊す前に動いてください
介護の仕事って、まじめな人ほど、限界ギリギリまで頑張ってしまう傾向があります。
「あほらしい」と感じるのは、それだけの負荷が心にかかっている証拠。
それを見て見ぬふりしてしまうと、本当にある日ポキッと折れてしまうんです。
僕が知っている職員の中にも、「心が限界を超えてしまって、二度と現場に戻れなくなった人」がいます。
だからこそ、壊れる前に、一歩だけ動いてみてください。
情報を調べるだけでもいい。誰かに相談してみるだけでもいい。



その一歩が、あなた自身を守ることにきっとつながるはずです。
②あなたは十分がんばってきました
このページを読んでくれているあなたに、僕からひとつだけ伝えたいことがあります。
「もう、十分すぎるほどがんばってきましたよ。」
夜勤明けでフラフラになりながらも、ちゃんと記録を書いて。 利用者さんに怒鳴られても、笑顔で「すいませんね〜」と対応して。 理不尽なクレームを受けても、必死に飲み込んで耐えて。
そんな日々を積み重ねてきたあなたは、誰よりもプロフェッショナルです。
だからこそ、これ以上自分をすり減らすような働き方を続けないでほしい。



ほんの少しだけ、自分をいたわる視点を持ってあげてください。
③次の一歩は、あなた自身が決めていい
最終的にどうするかは、もちろんあなた自身が決めることです。
「しばらく休んでみる」でもいいし、「転職して環境を変える」でもいい。
あるいは、「自分の中で覚悟を決めて、この職場でもう少し頑張ってみる」それだって、立派な選択肢です。
大切なのは、自分の気持ちを置き去りにしないこと。
自分の本音と向き合って、ちゃんと「どうしたいか」を考えること。
この記事が、そのための“きっかけ”になれたなら、僕としてはとても嬉しいです。
どんな選択をしても、あなたは決して間違っていません。



必要なときには、いつでも逃げ道を確保しておいてくださいね。
介護職があほらしいと感じたときに知っておくべきポイントまとめ


この記事のポイントをまとめます。
- 「あほらしい」と感じるのは正常な感覚であり、感受性が壊れていない証拠
- 現場では理不尽な人間関係やいじめが放置されやすい構造がある
- 一人夜勤や過剰な掃除業務など、職務に見合わない負荷が日常化している
- ケアマネは責任が重いにも関わらず、給料や待遇が報われにくい
- 利用者からの暴力に対して、職員が守られないケースが少なくない
- 制度の不備や形骸化したルールが現場職員にしわ寄せされている
- 上司や組織はトラブルへの対応が形式的で、当事者意識に欠ける
- 「やりがい」だけを求める風潮が職員の心を追い詰めている
- 転職や職種変更は逃げではなく、自分を守るための戦略である
- 情報を集めて選択肢を持つことで、心の余裕と行動力が生まれる
介護職として働いていて、「あほらしい」と感じたことがある。それは、あなたの心がまだ健全で、感受性が生きている証拠です。
この記事では、僕自身の体験や、現場の理不尽さ、制度の矛盾、心がすり減っていく過程を正直にお伝えしてきました。
そして、「それでも、抜け出す道はある」ということも、具体的に紹介してきました。
大事なのは、自分の気持ちに正直になること。
介護の現場で感じる「あほらしさ」は、個人の問題ではありません。
でも、あなたの人生は、あなたにしか守れません。



どうか無理だけはせずに。 自分のために動いてあげられる、そんなあなたでいてくださいね。



コメント