夜勤中の介護職が手抜きに走る理由とは?安全な手抜き10選
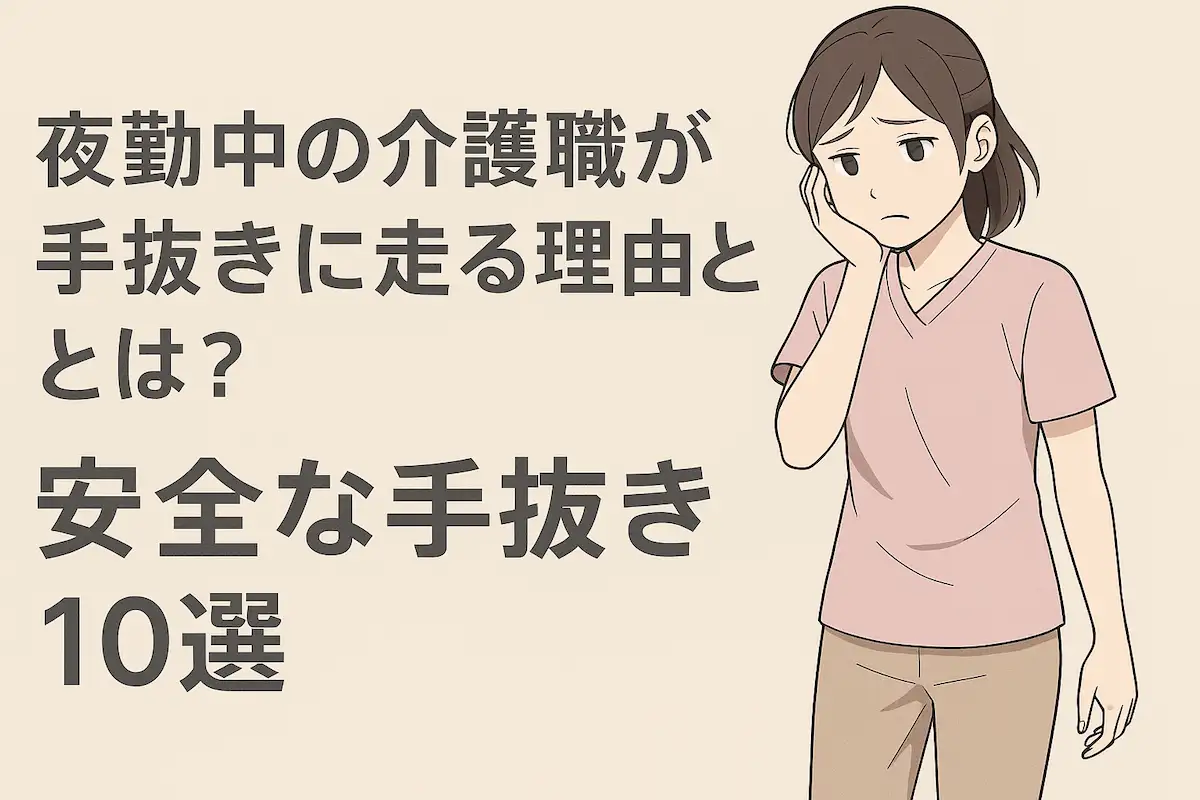
夜勤がつらい。でも誰にも言えないあなたへ。
 あんこ
あんこ「また夜勤か…」
「今日も眠れないし、休めない」
「もう、ちょっとくらい手を抜きたい…」
そんなふうに思ってしまった夜、ありませんか?
この記事にたどり着いたあなたは、きっと今、介護職として夜勤をがんばっている方だと思います。
でも、がんばるほどに疲れて、少しずつ笑顔が消えていって──気づいたら、「ちゃんとやること」がしんどくなっている。
僕もそうでした。老健、小規模多機能ホームの現場で夜勤を経験してきて、「これは人間の働き方じゃないかもしれない」と感じたことが何度もあります。
この記事では、「手抜き=ズル」ではなく、「自分を守る判断」としての“上手な手抜き術”をテーマに、 夜勤を乗り切るためのリアルな工夫や考え方、そして“逃げ道”としての転職という選択肢まで、 僕の経験をもとに正直にお話ししていきます。



読んだあと、少しでも「気持ちがラクになった」と思ってもらえたら嬉しいです。
- 夜勤中の介護職が手抜きをしたくなる具体的な理由
- 手抜きが許される場面と許されない場面の違い
- 安全に手を抜くための現場で使える実践テクニック
- 夜勤が無理な場合の転職や働き方の選択肢
介護職の夜勤がつらすぎる…。僕が見た“手抜きしたくなる現場”


「手抜きしたい」と感じるのは、甘えじゃない。 僕が現場で実際に経験した、過酷すぎる夜勤のリアルをまずお話しします。



それでは、僕の経験を元にリアルをお伝えしていきます。
①老健で36人を一人夜勤した話
僕が老健で夜勤をしていた頃、3階フロアで担当していたのは36人。
2階・3階・4階それぞれに介護職員が一人ずつ。看護師は全フロアを見回るけど、基本は連携がとりづらくて、自分の階のことはほぼワンオペでした。
夜勤の時間は22時〜翌朝7時半。仮眠なんて当然なし。というか、仮眠どころか座る暇もほとんどなかったですね。



「この人数を一人で回すって、そもそも無理でしょ」って何度も思いました。
②ナースコール地獄と夜勤中は仮眠ゼロの現実
ナースコールが頻回な利用者さん、いますよね。
僕の階では「またか…」ってなる人が4〜5人はいました。徘徊、不安、不眠、便意など理由はさまざま。
しかもタイミングが重なると、呼ばれた瞬間に他でもピンポン、ピンポンって。気が休まる暇もない。
一応「休憩時間」はあることになってたけど、正直その間も気が気じゃなくて、休憩室には行けませんでした。



これはもう、仮眠どころか精神的にも削られていく時間だったなと思います。
③起床介助+朝食準備の時間に追われる夜勤明けの朝
朝5時を過ぎると、地獄タイムの始まりです。
何が一番きついって、起床介助と朝食準備がほぼ同時に始まること。
パジャマの着替え、トイレ誘導、離床、朝食の準備などなど…。
それを時間内に終わらせなきゃいけない。
しかも僕の現場では、味噌汁を作る係も夜勤の仕事だったんです。ご飯の炊飯と味噌汁の準備、今思えば、詰め込みすぎですよね。



この時間は「絶対に誰かが手抜きしたくなる」っていうか、もはや手抜きしない方が異常なくらいです。
④小多機での深夜の捜索事件
小規模多機能ホームで夜勤してたときの話。
最大で9人を一人で見る体制で、日によっては4〜5人のことも。でも人数が少ない分、逆に油断できない。
ある夜、他の職員の夜勤中に利用者が施設を出てしまって、僕も深夜に呼び出されて一緒に捜索することになりました。
懐中電灯を持って周囲を探して…もう気持ちは焦りと恐怖でいっぱい。あれはほんとに怖かった。



「これ一人でやってたらヤバいよな」と思った経験でした。
⑤掃除の手抜きで泣かされた夜勤明けの一言
小規模多機能ホームでは夜勤の業務に掃除が含まれていました。
僕は正直、デイルームの床とか手すりの掃除は多少手を抜いてました。だってそれより優先する仕事が山ほどあったから。
でもある朝、早番のおばさん職員が来るなり洗面所の隅をチェックして「ここ、やってないわね」って言ったんです。
正直、イラッとしました。でも同時に、「あー、こうやって見られてんだな…」ってメンタルにきました。



本当は泣きたかった。でも現場って、誰も慰めてくれないんですよね。
おばさん職員って結構キツこと言うんですよね。おばさん職員との関係で悩む方にはこちらの記事をどうぞ。


介護職の夜勤で“手抜き”したくなるのは普通です


「完璧にやるのが当たり前?」そんなのは無理です。 夜勤がつらくて「もう無理…」と感じる理由は、ちゃんとあるんです。



「自分だけが弱いんじゃないか」と思っている人こそ、ぜひ読んでほしいです。
①夜勤で体力・集中力の限界が来る
夜勤って、ただでさえ生活リズムが狂いやすいんですよね。
日中と違って仮眠も取りづらく、体が自然と夜モードにならない。ましてや仮眠すら許されない現場も多い。
僕自身も、深夜2時〜3時あたりになると意識がもうろうとして、集中力もガタ落ち。ミスしそうになることが何度もありました。
こうなると、すべてを100%こなすなんて到底無理です。人間なんだから、どこかで力を抜かないと壊れます。



だから「手抜きしたくなる」っていうのは、体が自然に出してるSOSでもあるんですよ。
夜勤で生活リズムが乱れがちという方に向けて、関連する記事を書いているので気になる方はご覧ください。
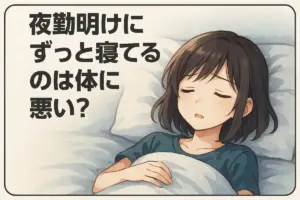
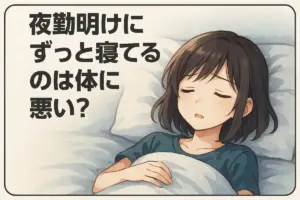
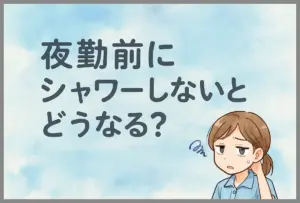
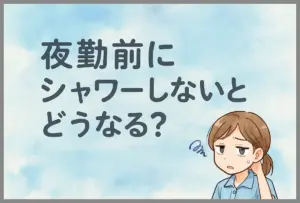
②夜勤業務の全部を完璧にこなすのは構造的に無理
夜勤って、任されている仕事量が多すぎるんです。
排泄介助、巡視、ナースコール対応、記録、起床介助、朝食の準備…これを一人で全部やれって、本当にムリゲー。
しかも「できて当たり前」みたいな空気がある。手が回らなければ「段取りが悪い」と言われる。でもそもそも、最初から破綻してるんです。
僕も夜勤初期の頃は、必死に全部やろうとしてパンクしました。やってもやっても終わらないし、ミスすれば自分の責任。



そんな構造じゃ、手抜きしたくなるのは当然です。
③「うまくやる人」が評価される現場の空気
現場では、「真面目に全部やる人」よりも「ほどほどに回せる人」の方が評価されたりするんですよね。
僕の周りにもいました。要領がよくて、テキパキ動いてるけど、よく見るとちょいちょい工程を“省いて”たりする人。
でも、それがバレない程度にやってるから、職員同士からも「デキる人」って評価されてたんです。
じゃあ真面目に全部やってる人はどうか?疲弊して、文句も言わず、体壊して辞めていく。
この構図、ほんとに多いです。



だから、必要以上に自分を責めなくて大丈夫。手を抜くことは、現場で生き抜くひとつのスキルでもあります。
介護職の夜勤でできる“安全な手抜き術”10選


やっちゃいけない手抜きと、やっても大丈夫な“うまい抜き方”があります。 僕が現場で編み出した10の工夫を、正直にお伝えします。
- 夜勤中は優先順位メモで後回しゾーンを見える化
- 夜勤の排泄ケアは濡れ方スコアで仕分け
- 夜勤中のバイタル測定は異常時だけ測定
- 夜勤中の記録は音声メモ→朝まとめ入力
- 起床介助は段階的にスタート
- 深夜のナースコールは“5秒ルール”で判断
- 仮眠ゼロでも意識保てるストレッチ術
- 夜勤明けの味噌汁はタイマーとポーションで時短
- 夜勤中の掃除は目立つとこだけ重点的に
- 夜勤中の事故報告はテンプレ事前作成で対処



それでは、順番に見ていきましょう。
①夜勤中は優先順位メモで後回しゾーンを見える化
僕が夜勤していたとき、一番しんどかったのが「何から手をつけていいかわからなくなる瞬間」でした。
ナースコール、排泄、記録、掃除、全部やらなきゃ。でも全部は無理。だから、やるべきことの“優先順位”をメモに書いていました。
今なら、スマホのメモアプリやリマインダーを使えばもっとスムーズに管理できると思います。
特に「後回しでも問題ない業務」を明確にしておくと、いざというときに焦らず対応できるようになります。



こういう“後回しゾーン”を自分なりに把握しておくことで、余計な焦りが減って動きやすくなるはずです。
個人的にはアリだと思っていますが夜勤中にスマホを使えるかどうかは職場のルールによって違います。こちらの記事をご覧ください。
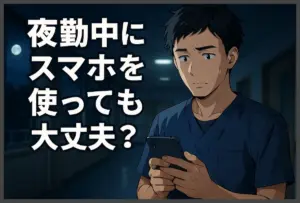
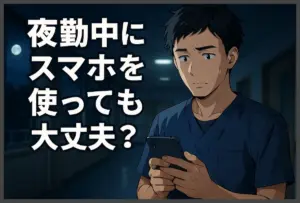
②夜勤の排泄ケアは濡れ方スコアで仕分け
排泄介助は夜勤中に避けて通れない仕事ですが、全員を毎回同じようにケアしていたらとてもじゃないけど持ちません。
僕がやっていたのは、「オムツの濡れ方」「皮膚トラブルの既往」「本人の不快訴え」などを点数化して、自分なりの“優先スコア”を作ることでした。
もちろん全員の排泄介助はしますが、優先順位の高い人から順に対応することで、効率は格段に上がりました。



排泄は優先順位をつけながら対応するという視点が大事です。
③夜勤中のバイタル測定は異常時だけ測定
「バイタル測定、全員やってましたか? 」僕の現場では、ルーチンでやってるところと、必要な人だけってところがありました。
重要なのは「基礎疾患」や「前日からの変化」。これらに該当する利用者さんだけを夜間にチェックして、他は日勤帯に任せる、という運用でも実は問題ありません。
バイタルの“やらなきゃいけない空気”に飲まれる必要はないんです。



今なら電子記録から過去データを一目で確認できる施設も多いので、異常時に集中するスタイルの方がミスも減ります。
④夜勤中の記録は音声メモ→朝まとめ入力
僕が夜勤してた当時は、音声メモなんて洒落た機能はなかったですね。メモ帳に急いで走り書き、朝に清書ってのが定番でした。
でも今は、スマホのボイスメモやICレコーダーがある。これ、使わない手はないです。
その場で一言「〇〇さん、1時に排尿。パッド軽度湿り」のように吹き込むだけで、朝になっても記録の精度はバッチリ。



僕が現役だったら、絶対使ってます。マジでおすすめです。
⑤起床介助は段階的にスタート
朝の起床介助、いちばんカオスですよね。僕は5時前からコールが鳴り始めて、6時には戦場状態でした。
そこでやってたのが、「元気な人」「すぐに動ける人」から先に動かす方法。段階的に起こして、混雑や重なりを避けてました。
体調や前日の様子も見て、「今日の最初組」と「ゆっくり組」を分けると、本当にラクになります。



流れを分散する、これ大事です。
⑥深夜のナースコールは“5秒ルール”で判断
ナースコールが連打されたとき、全部に飛びついてたらキリがない。僕は「鳴った直後の5秒間」で耳をすませて、音の傾向や利用者の癖を判断してました。
たとえば、よく徘徊する人のパターン、毎回トイレって決まってる人など、5秒で判断できる情報って案外あるんですよね。



全部すっ飛んでいくんじゃなくて、「様子見5秒ルール」。これ、心の余裕にもなりますよ。
⑦仮眠ゼロでも意識保てるストレッチ術
仮眠がない現場って、マジで過酷。僕のときもそうでした。
そんなときにやってたのが、短時間の“マイクロストレッチ”。椅子に座りながら首や肩、ふくらはぎを伸ばすだけで、かなりスッキリするんですよ。



1〜2分でも効果あります。意識が飛びそうになったときは、やってみてください。
⑧夜勤明けの味噌汁はタイマーとポーションで時短
夜勤の中で僕が一番理不尽だったのが、「味噌汁準備しておいて」ってやつ。おい、味噌汁って何だよと。
でも今なら、タイマー炊飯器とインスタントポーションがある。
時間ぴったりに沸かして放っておける。味も最近は悪くない。これを使えば、他の介助と被っても手が回ります。



とは言え、そもそも夜勤の仕事に味噌汁作りを入れちゃダメですよね…。
⑨夜勤中の掃除は目立つとこだけ重点的に
掃除も全部やろうとするとしんどいです。でも「水回りが汚れてる」と早番にチクられるのも嫌なんですよね。
だから僕は、“人目に触れるところだけ超キレイに”を徹底してました。洗面所の鏡、トイレの床、共用テーブルだけ重点清掃。



そこだけピカピカなら、意外と「ちゃんとやってる感」が出て、バランスが取れます。
⑩夜勤中の事故報告はテンプレ事前作成で対処
夜間の事故は本当に疲れる。ケガ対応して、家族に電話して、記録して…。
それで残業までつくと、「もうやってられないよ」ってなります。
だから僕は、よくある事故報告テンプレをWordで作ってました。あとは入力して印刷するだけ。



今なら電子記録の定型文機能もあるので、ぜひ活用を。
介護職の夜勤で“手抜き”してもいい場面・ダメな場面


「どこまでがOKで、どこからがアウト?」 判断に迷うラインを、具体的なケースごとに整理してみました。



“これはOK、でもこれはダメ”というラインを、僕の経験をもとに整理していきます。
①夜間の排泄介助のセーフ/アウトライン
排泄介助は、もっとも判断が難しい部分かもしれません。
僕が現場で意識していたのは、「本人が苦痛を感じるかどうか」「皮膚状態に悪影響が出るかどうか」の2点です。
軽度の湿りがある程度なら、利用者本人がぐっすり眠っているときに無理に起こしてまで交換する必要はないと思っていました。
逆に、下着やリネンまで汚染されている、異臭が出ている、褥瘡リスクが高いというケースでは、どんなに眠っていても対応必須です。



“手抜き”ではなく“優先判断”。これを意識することで、責任感と効率のバランスが取れるようになります。
②夜勤時の食事介助で省ける工程とNG行動
夜勤明けに食事介助が含まれるケースもありますよね。
僕も起床介助と同時進行でバタバタと食事の準備、配膳、服薬確認とてんやわんやでした。
その中で、“省ける”工程は「トレイの整え方」や「完璧な盛り付け」などの見栄え部分でした。
ただし、絶対にNGなのは、誤嚥リスクのある利用者への介助の省略、服薬の未確認です。
命に関わるところは手を抜いてはいけません。



忙しいからこそ、“安全第一”だけは死守する必要があるのです。
③深夜帯の記録業務はいつ・どこまでがOK?
記録については、僕の中では「リアルタイムで書けるならベスト、でも無理なら“メモ+まとめ書き”でOK」でした。
深夜帯に記録用紙と向き合ってる余裕なんてないときは、小さなメモ用紙にポイントだけ書いておいて、落ち着いたタイミングで清書。
ただし、“記憶頼り”のまとめ書きはNGです。



とくに事故や体調変化があったときは、時間と内容の記録が後々めちゃくちゃ大事になるので、そこだけはリアルタイムを意識していました。
④夜間の巡視・見守りの頻度はどう調整する?
僕の現場では「2時間ごとの巡視」がマニュアルになっていましたが、正直すべてをタイマーのようにやるのは難しい日もありました。
徘徊傾向がある方、不穏な様子がある方の部屋は頻度高め、落ち着いて寝ている方の部屋は間隔を広げる。
そういった“緩急のつけ方”で巡視の質を保ちながら、効率化もしていました。



すべての部屋を均等に回る必要はありません。“リスクの高い部屋ほど重点的に”が基本です。
⑤夜勤中の掃除の手抜きはどこまで許される?
掃除は“絶対にやらなきゃいけない業務”ではないけれど、やらなかったらやらなかったで朝に文句を言われる。
僕が実践していたのは、「人目に触れる場所だけは徹底的にやる」こと。
具体的には、共用の洗面所、廊下の手すり、食堂のテーブル。このあたりは手を抜かない。
逆に、誰も見ない倉庫の隅や備品棚の上などは、必要最低限だけで済ませるようにしていました。



手抜きじゃなく、“見せ場だけ押さえる”という意識です。これだけで印象がガラッと変わりますよ。
介護職の夜勤で“手抜き”したことによるリスクと後悔
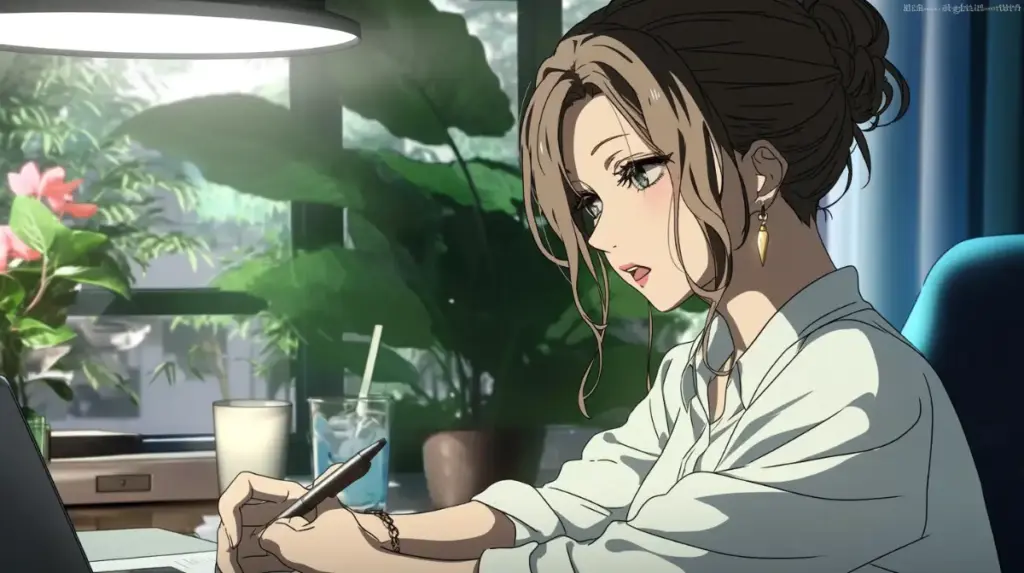
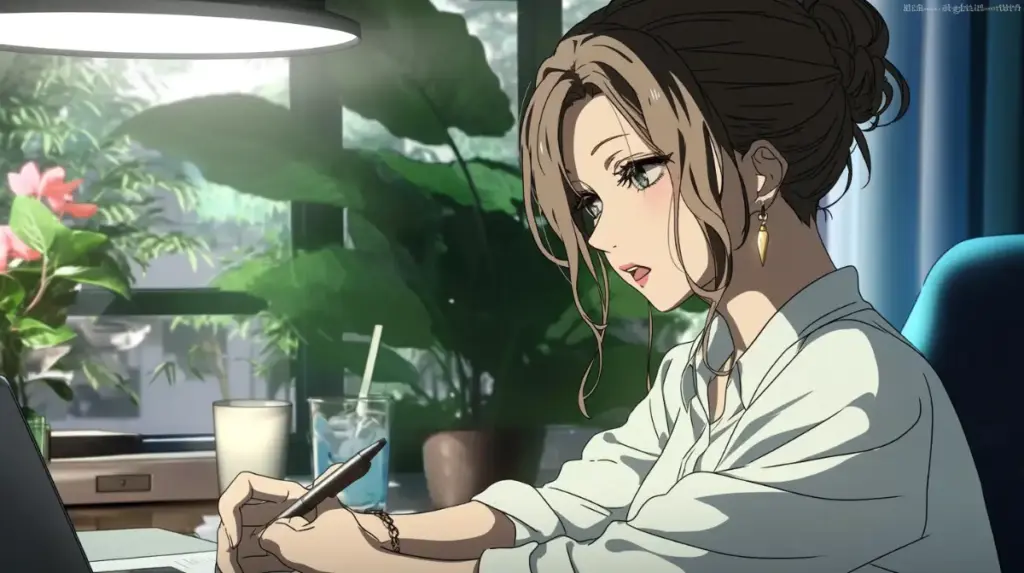
うまく抜くには、やりすぎないことも大切です。 僕の周囲で実際に起きた「やりすぎた結果の後悔」を紹介します。



ここでは“やりすぎた手抜き”が招く現実を、僕の経験や見聞きしてきたことを交えてお伝えします。
①手抜きがバレたときの信用喪失
手抜きって、バレなきゃOKって思いがちですが、介護の現場では意外と見られてるんですよね。
特に、早番や同僚職員は、ちょっとした変化に敏感です。
僕自身も掃除をサボったとき、「ここ拭いてないね」と朝一で指摘されて、地味に凹んだことがあります。
その一言が、信頼のヒビになることも。誰かが陰で「〇〇さん、最近手抜き多くない?」なんて言ってたりもします。



一度ついた“手抜きキャラ”は、なかなか取れません。
②チームワークの崩壊と孤立
手を抜いてることが周囲に伝わると、知らぬ間に孤立することもあります。
僕が以前いた現場でも、夜勤中の申し送りが雑になってきた人に対して、「あの人、ちゃんと見てるのかな?」って不信感が広がったことがありました。
最初は小さな違和感でも、それが積み重なると、報告・連携がうまくいかなくなってくるんですよね。
そのうち誰にも相談されなくなって、本人もどんどん黙りがちになって…見ていて辛かったです。



信頼の貯金って、少しずつ減っていくものなんだと実感しました。
③利用者との信頼関係にヒビが入る
介助のとき、明らかに雑に扱われたら、利用者だって当然気づきます。
ある職員が、忙しさのあまりオムツ交換を流れ作業でやってしまった夜がありました。
翌朝、その利用者さんがぽつりと「昨日は冷たかった」と言ったんです。
本人もショックを受けてました。「ちゃんとやってたつもりだったのに…」と。
利用者さんって、介助する側の“心の余裕”までちゃんと見てるんだと思います。



信頼って、築くのに時間がかかるのに、壊れるのは本当に一瞬なんですよね。
④最悪、法的トラブルになるケースも
介護業界で怖いのは、“過失”がそのまま“責任”になること。
たとえば、排泄介助を飛ばして皮膚トラブルになった、巡視を怠って転倒事故が起きた。
そんなとき、「なぜそれをやらなかったのか?」が問われます。
それが“意図的な手抜き”だと判断されれば、最悪、懲戒処分や訴訟につながるケースも。



だからこそ、「ここまでならセーフ」「これは絶対NG」のラインは常に意識しておく必要があるんです。
介護職の夜勤が無理なら、転職という選択もある
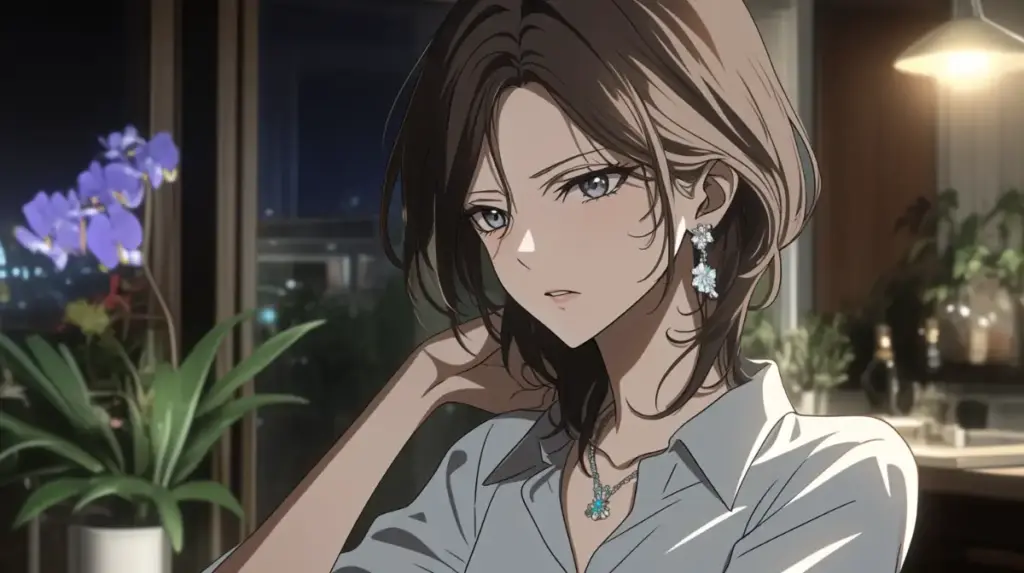
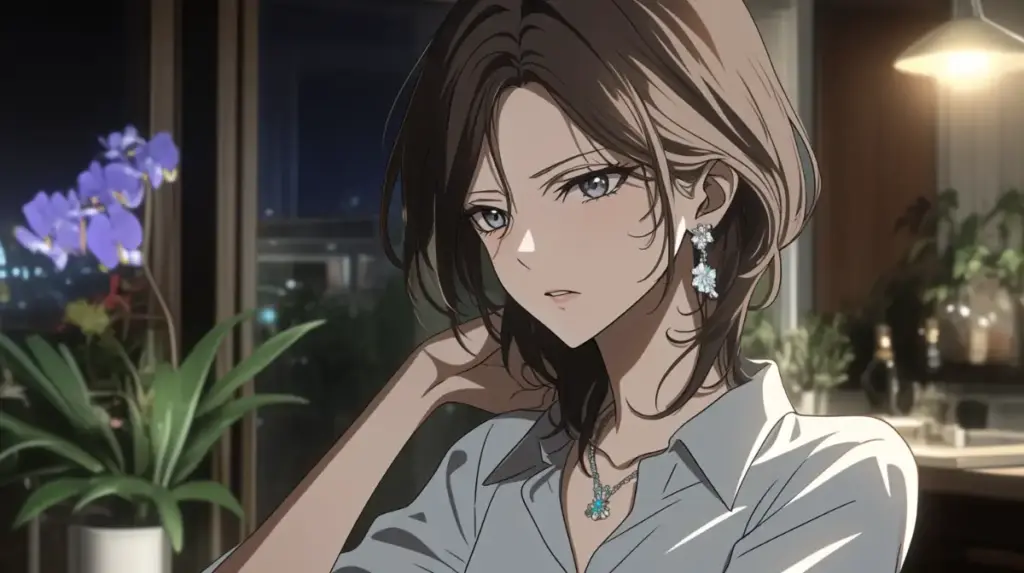
夜勤がしんどすぎるなら、無理に続けなくてもいい。 介護職でも、あなたに合った働き方はきっと見つかります。



「辞めたい」と思うほど辛いなら、今の職場がすべてではありません。 心と身体を壊してまで続ける必要はないんです。
①夜勤なし・日勤のみの介護職もある
「介護=夜勤ありき」と思っている人、多いですよね。僕もそうでした。
でも実際には、夜勤のない介護職もたくさんあるんです。
たとえば、デイサービス、デイケア、訪問介護など。
“生活リズムが整っていて、なおかつ対人支援ができる”という意味では、夜勤ナシ介護の方が合ってる人も多いと思います。



もし夜勤で限界を感じているなら、「同じ介護職の中で働き方を変える」ことも選択肢に入れてみてください。
②ケアマネや包括支援センター勤務という道
僕自身、介護の現場からスタートして、今は地域包括支援センターで主任ケアマネとして働いています。
現場時代と比べると、身体的な負担はかなり減りました。
もちろん仕事の内容は変わりますが、「人を支える」という軸は変わりません。
特にケアマネ業務は、現場経験がそのまま活きる仕事です。



「もう体力的にキツいけど、介護からは離れたくない」って人には、すごく相性のいいキャリアだと思います。
③介護職専門の転職エージェントを使うメリット
とはいえ、「どこに転職したらいいか分からない」「自分に合う職場が分からない」という人も多いですよね。
そんなときに便利なのが、介護職専門の転職エージェントです。
非公開求人を紹介してくれたり、「夜勤なし」「高収入」「人間関係良好」など、自分の希望に合った職場を一緒に探してくれます。
僕も周りで使ってた人を何人か知ってますが、「最初から相談すればよかった」って言ってました。



登録は無料だし、今の職場で悩んでる人は、選択肢のひとつとして持っておくと安心ですよ。
転職エージェントのことを知りたいという方に向けて、こちらの記事で解説しているので、ご覧くださいね。


介護職が夜勤で手抜きを考える背景と現場の実態まとめ


この記事のポイントをまとめます。
- 介護職が夜勤で手抜きを考えるのは構造的な業務過多が原因
- 施設によっては1人で多くの人数を担当するケースもあり身体的に限界を迎えやすい
- ナースコールの頻回対応により仮眠も休憩も取れず精神的に追い詰められる
- 起床介助と朝食準備が重なる朝方は特に余裕がなくなる
- 小規模多機能ホームでは利用者の夜間の外出など突発的な対応も多い
- 掃除や記録など後回しにしやすい業務が責められる要因になりやすい
- 夜勤の中で“要領よく抜く人”が評価される現場風潮が存在する
- 安全な手抜きには優先順位付けや工程の簡略化など工夫が求められる
- 手抜きが過ぎると信頼の喪失や法的リスクに繋がる可能性がある
- 夜勤が合わないなら転職や配置転換を考えることも前向きな選択肢である
僕も20年間、介護の世界でさまざまな現場を経験してきました。
夜勤の辛さも、手抜きをしたくなる気持ちも、そしてその後に押し寄せる罪悪感も、痛いほどわかります。
だからこそ、この記事を通して伝えたいのはただひとつ。
「あなたが今感じている疲れや迷いは、決しておかしなことじゃない」ということです。
“手抜き”は「ズル」ではなく、「工夫」と「判断」。
ちゃんと考えて、ちゃんと支えて、それでいて、自分の心と身体も守る。
そんな働き方が、もっと認められていいと僕は思っています。



読んでくださって、本当にありがとうございました。どうか、今日からほんの少しでも、心と体が軽くなりますように。
無理に頑張りすぎるよりも、自分に合う環境を探して、自分らしく笑顔で働けるようになった方が幸せだと思います。まずは、転職エージェントに相談してみましょう。



コメント