中国人留学生『18万円給付』は本当?制度の仕組みと誤解を徹底解説!
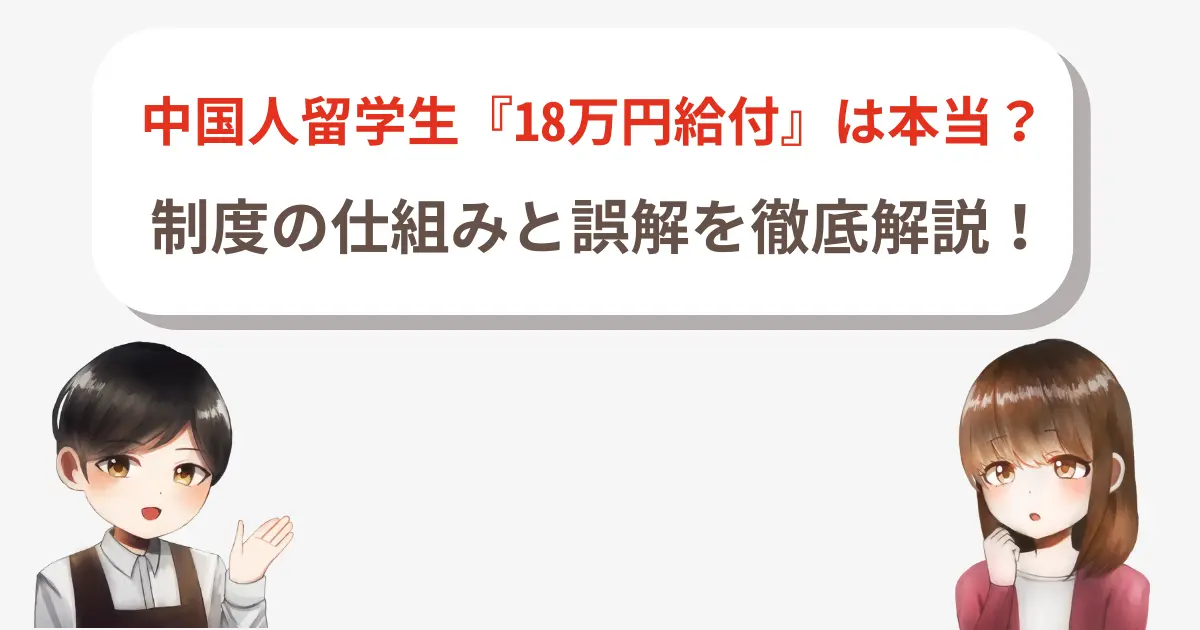
 あんこ
あんこ中国人留学生に毎月18万円支給されているのって本当?
SNSや知恵袋などで広がったこの話題、気になって調べた人も多いのではないでしょうか?
「そもそもそんなに給付する必要あるの?」「日本人にはもっと厳しいのに不公平じゃない?」
こんな疑問がネット上では次々と噴き出しています。
でも、この「18万円」という数字、実はとある特殊な制度だけを切り取った誤解に近い情報だったんです!
この記事では、給付の実態から制度の目的、他国との比較まで、正確なデータをもとにわかりやすく解説しています。



最後まで読めば、「18万円問題」の本当の姿と、日本が留学生に支援する理由がきっと見えてきますよ
- 「中国人留学生に18万円支給」という情報がどこから生まれた誤解なのかがわかる
- 国費と私費で支援内容が大きく異なる、留学生制度の全体像を理解できる
- 日本が留学生支援に力を入れる“国家戦略的な理由”が明らかになる
- 他国と比較しても突出していない、日本の奨学金制度の実態がわかる
📣 ちょっとだけオトクなお知らせ
「ニュースの裏側」や「制度の背景」をもっと深く知りたい人にピッタリなのが、今話題のAudible(オーディブル)。
実は今だけ、Amazon公式で90日間=3ヶ月無料キャンペーン中なんです!(7/31まで限定)
通勤や家事の合間のスキマ時間に“ながら聴き”するだけで、話題の社会・政治・経済系の本もスルスル頭に入るから、ネットの情報に振り回されず、自分の頭で考える力がグンとつきます。
🎧 実際に読まれてるジャンル
- 留学生制度・教育問題に関する本
- 社会のしくみや政策の裏側がわかる新書
- 世界の教養が身につくベストセラー多数
\90日無料は期間限定7/31まで/
途中解約OK。料金負担ゼロ!



僕もAudibleは通勤や移動中に愛聴しています。
こういう“知識の深掘り”、読んでるだけじゃもったいないから、“耳”で学ぶのもアリですよ!
中国人留学生「18万円給付」は本当?そのウワサの出どころとは?
最近SNSを中心に、「中国人留学生が毎月18万円ももらっている」という話題が一気に拡散しました。
でもこの話、本当に全員に当てはまる事実なのでしょうか?
最初に取り上げたメディア、そして「18万円」という数字の根拠をたどると、意外な誤解の連鎖が見えてきます。
ここではまず、このウワサの発端となった報道と、その後どのように広まっていったのかを解き明かしていきますね。



誤情報がどうやって一人歩きしたのかを知ると、もっと冷静に制度を考えられるようになりますよ。
TBS「報道特集」で何が報じられたのか
結論から言うと、「中国人留学生に月18万円支給」とTBSが断言したわけではありません。
TBSの「報道特集」では、ある中国人留学生が「月18万円の給付を受けている」と話す様子が放映されました。
ただし、これは特定の学生のケースであって、国の制度として「全員がもらえる」という話ではありません。
実際に報道では、制度の詳細や条件についての深い説明は省略されており、それが誤解の元となりました。
視聴者の一部がこの発言だけを切り取り、まるで“すべての中国人留学生”に適用されているかのような印象を持ってしまったのです。
このように、断片的な証言が全国放送で流れたことが、混乱の出発点だったといえますね。



次は、その「18万円」という数字がどこから出てきたのか、もう少し詳しく見ていきます!
「18万円」という数字が一人歩きした理由
実は「月額18万円」という給付額は、日本政府の国費外国人留学生制度の標準的な支給額とは異なります。
公式な支給額は以下の通りで、多くのケースで14万円台にとどまっています。
| 対象 | 月額奨学金 | 備考 |
|---|---|---|
| 学部留学生 | 117,000円 | 授業料免除・航空券あり |
| 修士課程 | 144,000円 | 授業料免除・航空券あり |
| 博士課程 | 145,000円(増額で150,000円) | 授業料免除・航空券あり |
| YLP(特例) | 242,000円 | アジア諸国の若手行政官向け |
ではなぜ「18万円」という数字だけがクローズアップされたのでしょうか?
主に3つの理由が考えられます。
- 東京など都市部での生活費が月18〜20万円という統計データが存在する
- 「ヤング・リーダーズ・プログラム(YLP)」や「SPRING」のような特例プログラムの金額が混同された
- SNSで断片的に切り取られた証言が拡散された
こうした要素が組み合わさることで、「18万円」という数字がまるで一般的な事実であるかのように広まってしまったのです。
制度の全体像を見ずに一部の数値やケースだけを取り上げてしまうと、誤解が一気に加速してしまいますね。



次は、その誤解がSNSを通じてどのように広がったのかを見ていきましょう。
SNSで拡散した誤解の構図とその影響
SNSでは、TBSの報道で紹介された「18万円発言」のクリップや要約が瞬く間に拡散されました。
「自分たちの税金で外国人が優遇されてる」といった怒りの投稿が次々に出てきて、一種のバイラル状態に。
特に「18万円支給」というインパクトのある数字が、見出しやサムネイルに使われたことで、多くの人が詳細を知らないまま印象だけを受け取る形になってしまったんです。
実際には、SNSで話題になった多くの投稿には、支給制度の対象や割合、条件などの詳細情報はほとんど含まれていませんでした。
その結果「中国人だけが特別扱いされているのでは?」という誤解や不満が一気に噴き出し、制度全体への偏った批判へとつながっていきました。



こうした流れを理解した上で、次章では実際の支給制度がどのように設計されているのかを、事実ベースで見ていきましょう!
実際はどうなの?国費外国人留学生制度の仕組みと支給額を徹底解説
「18万円支給」が話題になったことで「実際の制度ってどうなってるの?」と気になった人も多いと思います。
実は、日本が提供している国費外国人留学生制度は、めちゃくちゃ厳選されたエリート向けであり、支援内容も制度によって細かく異なるんです。



ここでは、奨学金の具体的な支給額、対象となる学生像、そして誤解の元になった特別制度まで、わかりやすく解説していきますね!
奨学金の支給額は月額いくら?課程ごとの違いとは
まず大前提として、「全ての中国人留学生が月18万円をもらっている」わけではありません。
国費留学生には、課程ごとに明確に支給額が設定されています。以下の表をご覧ください👇
| 課程 | 月額奨学金 | その他支援内容 | 代表的な対象者像 |
|---|---|---|---|
| 学部(大学) | 117,000円 | 授業料全額免除、往復航空券 | 成績優秀な学部留学生 |
| 修士課程 | 144,000円 | 授業料全額免除、往復航空券 | 研究力ある修士学生 |
| 博士課程 | 145,000円(増額で150,000円) | 授業料全額免除、往復航空券 | 将来有望な博士課程学生 |
| YLP(特例) | 242,000円 | 授業料全額免除、往復航空券 | アジア諸国の若手リーダー候補 |
このように、最も多いのは14〜15万円台。18万円には達していません。
しかも、これは日本全国すべてに共通する金額ではなく、札幌や仙台など寒冷地では最大3,000円が地域加算されることもあります。
つまり、東京在住の修士課程学生なら月14万4千円が基本。これが「全員に18万円」という印象と大きく食い違っているんです。



次に、この制度がいかに「選ばれた人」だけのものなのかを見ていきましょう。
どんな学生が対象?厳しい選考プロセスと倍率
国費留学生は、誰でも応募すれば通るというものではありません。
むしろ、世界中の優秀な学生の中から超狭き門をくぐったエリートだけが選ばれます。
主な選考ルートは以下の2つです👇
- 大使館推薦:在外日本大使館が募集・選考。筆記試験や面接を実施
- 大学推薦:日本の大学が提携校などから推薦
どちらも、学力・語学力・研究内容のレベルが相当高くないと通過できません。
さらにこの制度、中国人限定ではありません。
実際の国別データ(2021年)ではこんな感じです。
| 国・地域 | 国費留学生の割合 |
|---|---|
| インドネシア | 11.7% |
| 中国 | 8.9% |
| タイ | 7.0% |
中国は上位国のひとつではありますが、他の国々と同じように条件付きで選抜されているだけなんです。
つまり「中国人だけが優遇されている」という印象は、制度の実情からかけ離れていますね。



続いて、多くの人が「18万円の出どころ」として誤解している、特別な制度を見てみましょう!
誤解のもとになった「ヤング・リーダーズ・プログラム」とは
「じゃあ月に18万円以上もらってる学生って、存在しないの?」と思った方、例外的な制度があります。
それが「ヤング・リーダーズ・プログラム(YLP)」。
これはアジアの若手行政官など、すでに社会で活躍している人材を対象にした、1年間の超特別コースです。
このYLPでは、月額242,000円もの奨学金が支給されます。
ただし注意してほしいのは、この制度が
- 一般の大学生・大学院生とは完全に別枠
- 募集人数が非常に少なく、ほとんどが現職官僚などの社会人
という点です。
この制度の存在が「18万円支給」というイメージを生み出した大きな原因とされていますが、全体から見るとごくごく一部の特殊なケースにすぎません。



そして、もう一つ、18万円に関する誤解のもとになった制度があります。
SPRING(次世代研究者挑戦的研究プログラム)も誤解の一因に
「月18万円」の話題が広がった背景には、もう一つ誤解されやすい制度があります。
それが「次世代研究者挑戦的研究プログラム(通称:SPRING)」と呼ばれる、博士後期課程の学生を対象とした支援制度です。
この制度は、JST(科学技術振興機構)が2021年度から実施しており、優秀な博士課程の学生が研究に専念できるよう、生活費として年間180万円(月あたり15万円)以上+研究費の支給が行われています。
選抜された学生にはさらに、キャリア支援や国際性を高めるプログラムなども提供され、将来の科学技術人材としての育成が目的とされています。
報道によると、2024年度のSPRING受給者は約1万人。そのうち4,125人(約4割)が外国人で、中国人が2,904人と全体の3割近くを占めていたことが明らかになっています。
これが「税金で中国人留学生に多額の支援が行われている」と捉えられ、一部のSNSや番組で「18万円支給」という言葉だけが一人歩きする形になってしまったようです。
ただし、こうした制度は世界の研究先進国では当たり前のように存在しており、アメリカやドイツ、北欧などでも博士課程の学生には給与や給付型奨学金が支給されるのが一般的です。
むしろ日本がこうした支援を整え始めたのは遅れており、グローバルな研究競争力を維持するためにも必要とされている側面があるのです。
では、国費制度を受けていない、残り97%の留学生たちはどんな生活を送っているのでしょうか?



次の見出しでは、そんな「私費留学生」のリアルな現実に迫っていきます!
私費留学生のリアルな生活事情:97%の現実と「仕送り」への誤解
「留学する余裕があるなら親からの仕送りでいいのでは?」
そんな声もネット上ではよく見かけますよね。
でも実は、日本にいる外国人留学生の約97%は“私費”で来ていて、かなりギリギリの生活をしているってご存じですか?
ここでは、仕送りやアルバイトの実態、生活費と学費の内訳、そして「18万円」という金額が何を指していたのかを分かりやすく解説していきます。
私費留学生の収入源は?仕送りとアルバイトの実態
JASSO(日本学生支援機構)が公表した2023年度の調査によると、私費留学生の平均月収は17万円。
そして収入の内訳は、以下のようになっています👇
| 収入源 | 割合(目安) |
|---|---|
| 親からの仕送り | 約40% |
| アルバイト | 約45% |
| 奨学金(私費向け) | 約10〜15% |
つまり、「親から仕送りで生活してるんでしょ?」というのは半分しか合ってないんです。
実際、多くの留学生は生活費の半分以上を自分のバイトで賄っているのが現実。
そして、そもそも仕送りがゼロの学生も少なくなく、アルバイトなしでは成り立たないケースが多数あります。
このように、私費留学生は“余裕のある人たち”というより、むしろ「働かないと暮らせない」学生が圧倒的に多いんですね。



次は、そんな彼らが毎月どんな出費に追われているのかを見ていきましょう。
生活費・学費の内訳と「自転車操業」の実態
同じくJASSOの調査によると、私費留学生の平均支出も月17万円。
つまり、「収入=支出」で、貯金ゼロの自転車操業状態です。
支出の内訳は以下のとおり👇
| 支出項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 授業料(月割換算) | 約45,000円(国立大)〜それ以上(私立) |
| 住居費 | 約35,000〜60,000円 |
| 食費 | 約25,000〜40,000円 |
| 通信・交通・光熱費など | 約20,000〜30,000円 |
学費は自分で払って、家賃もかかって、さらに食費・交通費…。
正直、日本人の一人暮らしの大学生と比べても、生活水準はかなり厳しいです。
しかも、奨学金をもらえている人はごく一部。文科省の「学習奨励費」は月3万円〜4.8万円程度ですが、支給対象は全体の3割ちょっとしかいないというデータも。
つまり、ほとんどの私費留学生は「奨学金なしで、仕送りとバイトだけ」で17万円の出費を毎月しのいでいるわけです。



ここで改めて、あの「18万円」という数字の正体に戻ってみましょう!
月に18万必要なのは生活費?給付金との混同の真相
そもそも「18万円」という数字、実は“支給額”ではなく、“生活費の必要額”として出てくるケースが多いんです。
たとえば東京のような大都市だと、家賃も食費も高くつくため、学生の生活費が月18〜20万円程度になるのはよくある話。
つまり、この「18万円」という数字は
- 一部の特例制度(YLP)の給付額
- 大都市圏の生活費の平均
- 一部の留学生の証言(バイト+仕送り)
などが混ざり合って、あたかも“全員が支給されている”ような印象を与えてしまったのです。
でも実際は、私費留学生のほとんどが18万円分を自分の力でどうにかやりくりしているのがリアルなんですよね。



次は、そもそも「なぜ日本はここまで留学生を受け入れているのか?」という、制度の根っこに迫っていきます!
日本の国家戦略としての留学生支援制度:なぜ支給するのか?
「そもそも、なんでそこまでして外国人留学生を支援する必要があるの?」
多くの人が抱くこの疑問には、日本の未来に関わる深い国家戦略が関係しています。
留学生を支援することは、単なる“慈善”や“国際交流”ではなく、長期的に見て日本に大きな利益をもたらす国策なんです。



ここでは、その狙いや意図、他国との比較を通して、日本の奨学金制度の裏側を読み解いていきます!
💡留学生支援って、実は日本の“国家戦略”だった?
実はこのテーマ、もっと深く知りたい人にぴったりなのがAudible(オーディブル)です。
7/31までの期間限定で、いまなら3ヶ月間無料で聴き放題!
政策や国際関係に関する書籍も豊富で、スキマ時間に“学びの読書”ができ、効率や思考力がバク上がりします👇
\90日無料は期間限定7/31まで/
途中解約OK。料金負担ゼロ!
日本が優秀な人材を囲い込む理由とは?
今、日本の大学や政府が力を入れているのが「グローバル人材の獲得競争」。
実はこれは、経済成長と少子化による労働力不足という2つの問題を同時に解決しようとする取り組みでもあります。
文部科学省の資料によれば、日本は2008年から「留学生30万人計画」を掲げ、国際的な頭脳を呼び込む体制を整えてきました。
そして、優秀な学生を日本で学ばせ、卒業後に日本企業へ就職してもらうことで、将来的な戦力として活用しようとしているのです。
事実、2022年には約6割の大学卒業留学生が日本国内での就職を希望し、定住を視野に入れて動いています。
| 年度 | 留学生の日本企業就職率 |
|---|---|
| 2018 | 約54% |
| 2022 | 約62% |
支援することが、将来的には“投資回収”につながる――これが日本の本音なのです。



では次に、日本がなぜ「外国人に好印象を持たれること」にもこだわっているのか、その理由を見てみましょう。
外交とソフトパワーとしての「知日派」育成の狙い
国費留学生として日本で学んだ学生の中には、帰国後に自国の政府・大学・企業の幹部として活躍する人が多数います。
彼らは「日本で学んだ経験を持つ=知日派」として、日本との関係構築のカギを握る存在になります。
これこそが日本政府が掲げる「ソフトパワー外交」の柱。
たとえば、東南アジア諸国の中には、日本の大学に通った元留学生が大臣や外交官になっているケースも珍しくありません。
| 留学生の進路例 | 影響力のある役職 |
|---|---|
| インドネシアのYLP卒業生 | 経済担当副大臣 |
| ミャンマーの国費卒業生 | 外務省上級官僚 |
こうした人脈は、日本企業の進出や外交交渉でも非常に有利に働くんです。
だからこそ、日本は他国と比べて「未来の知日派を育てる投資」として、国費制度に力を入れているわけです。



では、日本の制度は本当に「外国人にだけ優遇されている」のでしょうか? 他国と比較してみましょう。
海外の奨学金制度と比べて日本は本当に「優遇」してる?
一見「日本は外国人に手厚すぎるのでは?」と思うかもしれません。
でも、世界を見渡すと、もっと手厚い国も少なくないんです。
| 国 | 主な奨学金制度 | 月額支給例(大学院) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 国費外国人留学生制度 | 144,000〜150,000円 | 授業料・航空券付き |
| ドイツ | DAAD奨学金 | 約180,000円 | 家族帯同手当あり |
| フランス | エッフェル奨学金 | 約190,000円 | 滞在支援・医療保険あり |
| 韓国 | GKS(国費) | 約140,000円 | 韓国語研修義務あり |
| アメリカ | フルブライト等 | フルカバー | 授業料・生活費+滞在支援あり |
このように、日本の支援は特別優遇というより「国際的な水準」の中にあるというのが現実です。
むしろ、外交・経済・人材戦略の一環としては、他国も同様かそれ以上に支援している場合も多く見られます。



それだけ世界中が「優秀な外国人学生」を巡ってしのぎを削っている、ということなんですね。
中国人留学生に毎月18万円は本当?制度の実態を正しく理解しよう
今回の記事では、「中国人留学生に毎月18万円が支給されている」というネット上の話題について、制度の実態と事実をもとに詳しく解説しました。
誤解の元となった特殊な奨学金制度や、実際に支援を受けている留学生の割合、そして日本の国家戦略としての支援の背景まで幅広く触れました。
記事の要点をおさらいしていきましょう。
- 「毎月18万円支給」は、特殊な一部のプログラム(YLPやSPRING)のみ
- 多くの国費留学生は月11〜15万円の奨学金を受給
- 国費留学生は全体の約3%、97%は親の仕送り+アルバイトで生活する私費留学生
- 月18万円はむしろ東京など都市部での平均的な生活費
- 留学生支援は、将来の人材獲得・外交戦略として各国も取り組んでいる
中国人留学生を含む国費留学生への支援には「日本という国の明確な戦略と背景」があります。
話題になっている「18万円」はごく一部の話に過ぎず、大多数の学生は厳しい経済状況の中で学んでいます。



これを機に、ネットの情報を鵜呑みにせず「なぜ制度が存在しているのか?」という視点で考えることが大切ですよ。
🎧ここまで読んで「もっと詳しく知りたい!」と感じた人へ。
国際問題・教育制度・社会保障…このあたりの本が耳で聴けるAudibleが今アツいです!
90日=3ヶ月無料で全て聴き放題なので、試すだけでも価値あり👇
スキマ時間に聴けて、自分で未来を考える力が養われますよ!
\90日無料は期間限定7/31まで/
途中解約OK。料金負担ゼロ!
コメント