ケアマネってそんなに偉いの?原因と対処法をケアマネが解説

 あんこ
あんこケアマネってそんなに偉いの?
介護の現場でケアマネに対して不信感を抱く場面は、決して珍しくありません。「ケアマネの性格が悪い」「ケアマネって何様?」「ケアマネに腹が立つ」といった気持ちを抱いたことがある人も多いでしょう。
中には、最悪なケアマネージャーにあたってしまい、ケアマネと喧嘩に発展してしまったケースも耳にします。
さらに、ケアマネへの苦情事例では、説明不足や高圧的な態度、連絡不備など、さまざまな問題が報告されています。時にはケアマネの理不尽な対応に直面し、どう対処すべきか迷うこともあるでしょう。
「ケアマネジャーと看護師、介護福祉士はどの職種の立場が上ですか?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。
この記事を書いている僕は、ケアマネ歴13年の現役主任ケアマネです。
これまで多くの利用者・家族から寄せられたケアマネへの苦情対応や、担当交代のサポートも行ってきました。
はっきり言って、ケアマネは別に偉くありません!
利用者の生活をより良くするため、多職種や地域資源を結びつけるコーディネーターに過ぎないのです。
本記事では、ケアマネに対する不満や疑問の背景を整理し、適切な対処法までわかりやすく解説していきます。



読んだあとには、あなたのモヤモヤした気持ちが少しでも晴れることを目指しています!
- ケアマネは制度上偉い立場ではないことが理解できる
- ケアマネが性格悪く見える背景や理由がわかる
- ケアマネとのトラブルを防ぐ具体的な方法がわかる
- ケアマネと合わない場合の交代手順を知ることができる
ケアマネってそんなに偉いの?実態を解説


- ケアマネが性格悪いと感じる理由とは
- ケアマネが何様と思われる背景
- ケアマネに腹立つときに確認すべきこと
- 最悪なケアマネージャーの特徴とは
- ケアマネと喧嘩を避けるためのコツ
ケアマネが性格悪いと感じる理由とは


ケアマネジャーに対して「性格悪い」と感じる場面は、少なからず存在するでしょう。特に介護というデリケートな分野では、対応の仕方ひとつで受ける印象が大きく左右されるためです。
このように言うと、ケアマネ個人の資質ばかりが問題のように思われるかもしれません。しかし、実際には制度上の立場や業務負担など、さまざまな背景が関係しています。
例えば、ケアマネは担当する利用者数が多く、連絡調整やケアプラン作成に追われているケースがほとんどです。他にも全担当ケース分の記録や書類作成など、膨大な量の業務もあるんですよね。
このため、一人ひとりとじっくり向き合う時間が取れず、結果として「冷たい」「事務的」と感じられてしまうことがあるのです。
また、ケアマネは制度に則ってサービスの調整を行う立場にあるため、利用者や家族の希望に必ずしも応じられないことがあります。このとき、断る理由を十分に説明しない、あるいは言葉選びを誤ると、「上から目線だ」「思いやりがない」と受け取られてしまうリスクが高まります。
さらに、職場環境や人間関係によるストレスも影響を与えます。過酷な労働条件の中で精神的に余裕を失い、本来なら丁寧に対応すべき場面で感情的な態度を取ってしまうケースもあるでしょう。
このように考えると、ケアマネの性格そのものが悪いのではなく、制度や環境、業務負担によって「性格悪く見える」状況が生まれやすいことが理解できると思います。
とはいえ、利用者にとっては態度の冷たさや配慮の欠如は直接的なストレスとなるため、必要に応じて事業所へ相談するなど冷静に対応することが大切です。



僕自身も過去に、言葉の選び方をミスって、利用者との信頼関係が崩れてしまったケースが1回だけありました。小さな配慮はとても大切だと実感しています。
ケアマネの性格が悪いと感じた場合の具体的な対処法について、こちらの記事でまとめましたのでご覧ください。
ケアマネが何様と思われる背景
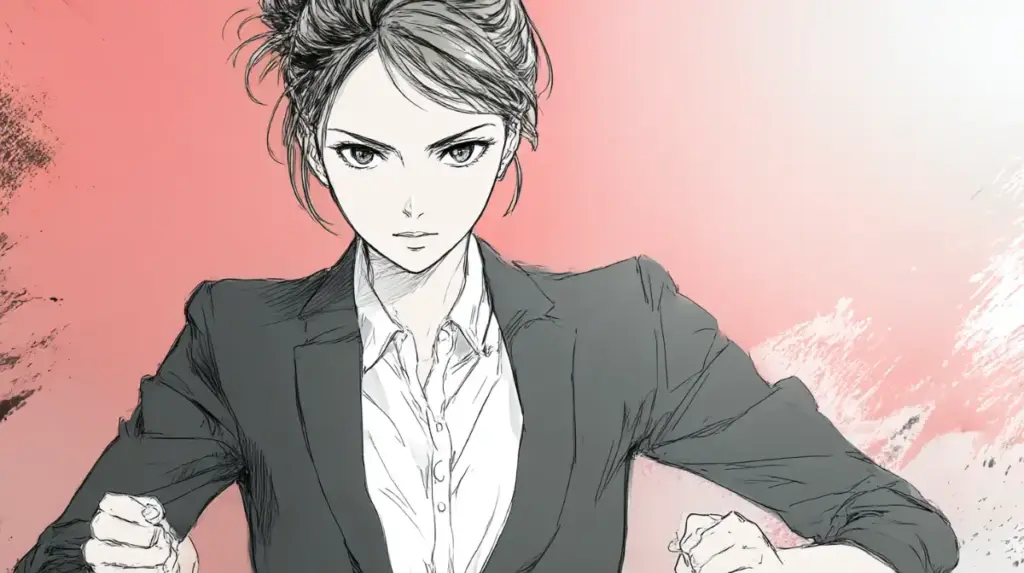
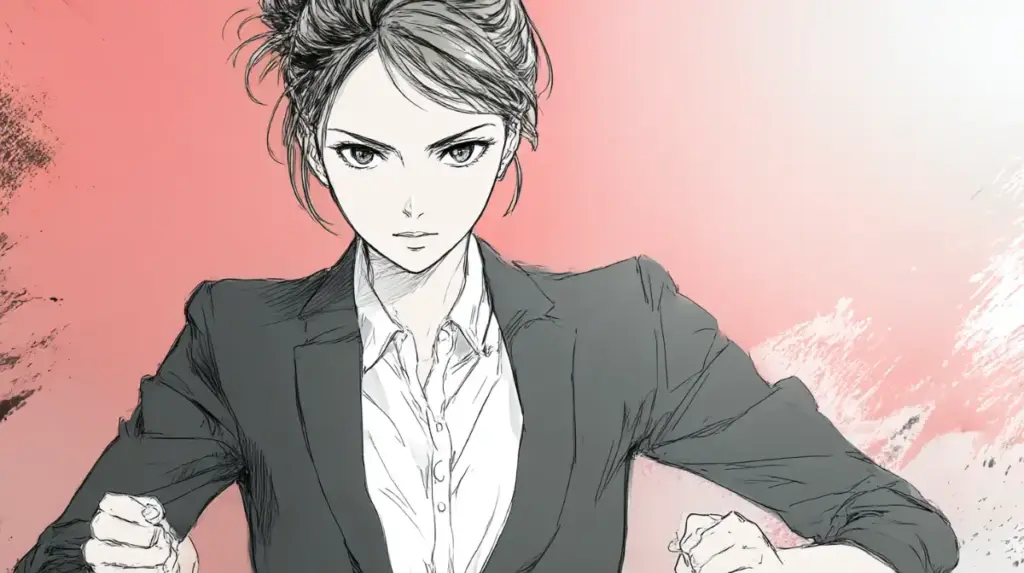
ケアマネジャーに対して「何様だ」と感じてしまう背景には、制度上の立場とコミュニケーションのギャップが深く関係しています。
まず、ケアマネは介護保険サービスを利用するために不可欠な「ケアプラン」の作成権限を持っているので、サービスの種類や内容、頻度などを決定する際に、大きな影響力を持つ存在となります。
特に、希望するサービスが制度上難しい場合や、専門的な判断により提案内容が希望と異なった場合、利用者や家族は「自分たちの意見を軽視された」と感じてしまうことがあるのです。
ここで問題となるのが、説明不足や一方的な進め方です。例えば、なぜ希望に沿えないのかを丁寧に説明せず、ただ「無理です」「できません」とだけ伝えた場合、利用者は自分たちの状況や思いを否定されたように受け取ってしまうことでしょう。
このとき、「何様のつもりだ」という感情が生まれやすくなります。
また、現場には「ケアマネ様」と呼ばれる慣習が一部に残っていることも影響しています。特定の事業者が利用者紹介を期待してケアマネに過剰に気を遣う結果、ケアマネ自身が無意識に「自分は偉い」と錯覚してしまうことがあるのです。
特に福祉用具の業者は数が多く、ケアマネの元に営業周りに行く人が多いので、「自分がサービスを紹介してあげてる」と勘違いしてるケアマネを僕も実際に見たことがあります。
さらに、忙しさからくる対応の荒さや、感情を抑えきれない対応も、「偉そう」という印象を与える要因となります。こうして、実際の意図とは裏腹に、ケアマネが「何様」と思われる構造ができあがってしまうのです。



ケアマネと他の専門職種、利用者それぞれの立場は本来対等であるべきでしょう!
ケアマネに腹立つときに確認すべきこと


ケアマネジャーに対して腹が立つとき、感情のままに行動する前に、冷静に状況を整理することが重要です。
まず考えるべきなのは、本当にケアマネ個人に問題があるのか、それとも制度や環境による制約なのか、という点です。
例えば、希望するサービスを断られた場合、ケアマネの個人的な意向ではなく、介護保険制度のルールや予算上の制限による場合もあります。このとき、ケアマネを責めても根本的な解決にはつながらないため、まずは「なぜ無理なのか」という理由をしっかり確認することが大切です。
次に、コミュニケーション不足が原因であるケースも多く見受けられます。忙しさから説明が雑になっていたり、利用者側が意図を十分に伝えきれていなかったりする場合も少なくありません。このため、要望や疑問は具体的にメモしておき、話し合いの場で一つ一つ確認する姿勢が効果的です。
また、相性の問題も無視できません。人間同士である以上、どうしても合わない場合はあります。このようなときは無理に我慢するのではなく、別のケアマネに変更することも選択肢の一つ。できれば、事前に新しいケアマネを確保してから手続きに入ることが望ましいですね。
さらに、感情的な対立を避けるために、話し合いの場では冷静な態度を心がけましょう。事実に基づいて問題点を整理し、「どうしてほしいのか」を具体的に伝えることで、建設的な解決に近づけます。
こうして確認を重ねた上で、それでも問題が解決しない場合は、事業所への相談や正式な苦情申し立てといった手段を検討するのが賢明です。
感情を爆発させる前に、できる限り冷静に対応策を考えることが、後悔しないための第一歩です。



僕自身、部下や他事業所のケアマネへの苦情や交代の対応を何度もしていますが、コミュニケーションと配慮の不足で誤解が生じていることが主な原因ですよ。
最悪なケアマネージャーの特徴とは


最悪なケアマネージャーには、いくつかの共通する特徴があります。ここでは、特に注意すべきポイントについて整理していきます。
まず、利用者や家族に対して高圧的な態度を取るケアマネは、大問題。例えば、利用者の希望を頭ごなしに否定したり、説明なしに自分の意見を押し付けるような行動は、利用者側に強い不信感とストレスを与えます。
このような対応をされると、話し合いが難しくなり、支援そのものがスムーズに進まなくなってしまうでしょう。
また、連絡が取れない、対応が遅いというのも大きな問題です。例えば、急ぎの相談をしたいのに数日間返事がない、月1回の定期訪問さえ形だけで終わってしまう、などの対応では、信頼関係を築くことは難しくなります。
ケアマネは利用者の生活に直結する存在ですから、コミュニケーション不足は致命的。
さらに、業務を雑にこなすケアマネにも注意が必要です。例えば、ケアプランを作成する際に、ろくに話を聞かずテンプレートのようにサービスを並べるだけだったり、必要なモニタリングを怠ったりするケースです。
このようなずさんな対応は、最終的に利用者本人に不利益をもたらします。
そして、特定の事業者をあからさまに優遇する行為も問題視されます。ケアマネは中立的な立場で利用者にとって最善の選択をサポートすべきですが、特定の業者との関係性を優先するような態度は、公正さを欠き、倫理的にも問題です。
最悪なケアマネージャーの特徴をまとめます。
- 高圧的
- コミュニケーション不足
- 業務がずさん
- 中立性を欠く
もし担当ケアマネがこれらに該当する場合は、適切な相談窓口に相談したり、ケアマネの変更を検討することをおすすめします。



残念ながらこういった特徴を持つケアマネも一定数いるんですが、一人ケアマネや少人数の事業所だと自分のおかしさに気付けないということも多いんですよね。
ケアマネと喧嘩を避けるためのコツ


ケアマネジャーと喧嘩になってしまうと、介護サービス全体に悪影響を及ぼす可能性があります。だからこそ、できるだけ冷静に、建設的な関係を保つことが重要です。
まず意識しておきたいのは、感情的な言動を控えることです。介護はどうしてもデリケートな問題が絡むため、つい怒りたくなる場面もあるでしょう。
しかし、感情をぶつけるだけでは問題は解決せず、かえって関係が悪化してしまいます。あなたが冷静でいれば、相手も冷静さを取り戻しやすくなります。
次に、要望や不満を伝えるときは、具体的な事例を挙げることがポイント。
例えば、「なんだか対応が悪い」と漠然と言うのではなく、「先月の訪問時にこちらの要望を最後まで聞いてもらえなかったので残念に思った」と伝えるほうが、ケアマネも改善策を考えやすくなります。
さらに、話し合いの場では「自分たちはチームだ」という意識を持つことが効果的です。ケアマネと利用者・家族は、対立する立場ではなく、協力して利用者本人の生活を支えるパートナーです。
だからこそ、一方的に責めるのではなく、「どうすれば一緒に良くできるか」という視点で話を進めると、相手の反応も変わるでしょう。
また、事前に伝えたいことをメモにまとめておくと、冷静に話しやすくなります。急な感情に振り回されず、要点を整理して伝えることができるため、無駄なトラブルを回避しやすくなるでしょう。
ケアマネとの喧嘩を避けるコツをまとめます。
- 冷静な態度で感情的にならないようにする
- 改善してほしいところを具体的に伝える
- チーム意識を持つ
- 事前にメモをとっておくなどの準備をして話す



こうした工夫を取り入れながら、より良い関係を築いていきましょう。
ケアマネってそんなに偉いの?対処法も紹介


- ケアマネへの苦情事例から学ぶ注意点
- ケアマネの理不尽な対応への正しい対策
- ケアマネジャーと看護師はどちらの立場が上ですか?
- ケアマネと介護福祉士はどちらが上ですか?
- ケアマネが合わない時には交代できる
ケアマネへの苦情事例から学ぶ注意点


ケアマネジャーに対する苦情事例には、共通するパターンが存在します。ここでは、実際によくある事例をもとに、注意すべきポイントを整理していきます。
例えば、最も多い苦情の一つが「説明不足」です。利用者や家族に対して、サービス内容や制度の制約を十分に説明しないまま話を進めてしまい、後から「そんなつもりじゃなかった」「聞いていなかった」とトラブルになるケースです。
これを防ぐためには、説明を受ける際には必ずメモを取り、わからないことはその場で確認する習慣をつけることが大切。
次に、「態度が高圧的だった」という苦情も多く見られます。特に、高齢の利用者が「命令口調で話された」と感じると、ケアマネに対する不信感が一気に高まります。
前述の通り、態度に違和感を持った場合は早めに記録を残し、必要に応じて事業所や地域包括支援センターなどに相談しましょう。
また、「連絡が取れない」「相談しても動いてくれない」といった不満も多く寄せられています。これらは業務多忙が原因である場合もありますが、それでも利用者にとっては大きなストレスです。
こうした場合には、連絡方法を明確にする(メール、電話、連絡帳など)取り決めをするだけでも、ある程度のトラブルを防げます。
さらに、苦情申し立ての際には感情的にならないことが非常に重要。感情的に訴えてしまうと、話が本質からズレてしまい、かえって解決が難しくなることがあります。
事実と希望する対応を整理して、冷静に伝えることを意識しましょう。
このように、ケアマネへの苦情事例には、「説明不足」「高圧的な態度」「連絡不備」という共通点があります。
これらのポイントを意識しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、よりスムーズな支援を受けることができるでしょう。



ケアマネは担当件数が多いため、常に時間に追われやすく、報連相やコミュニケーション不足になりがちなので、僕はいつも配慮するよう心がけています!
ケアマネの理不尽な対応への正しい対策
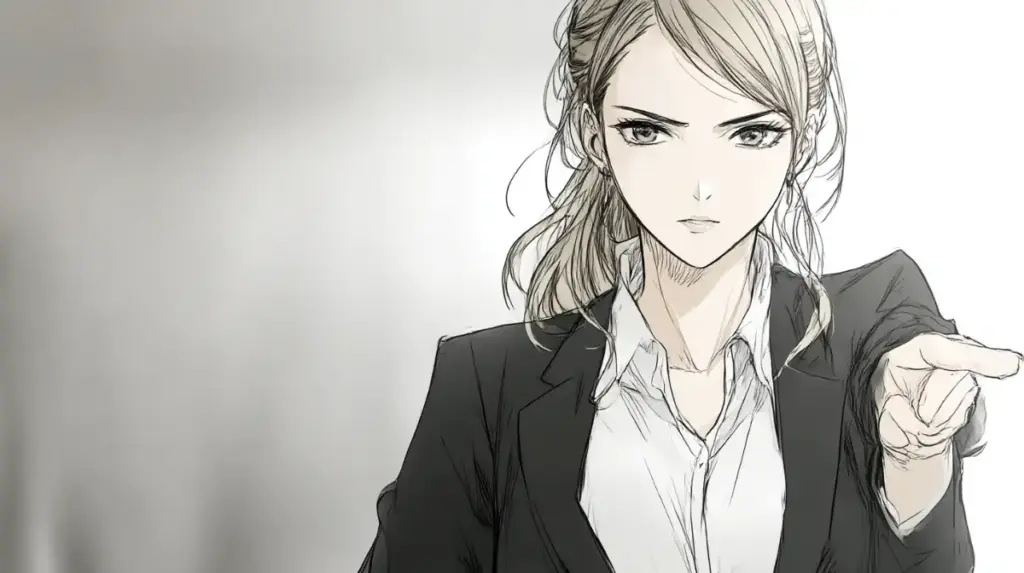
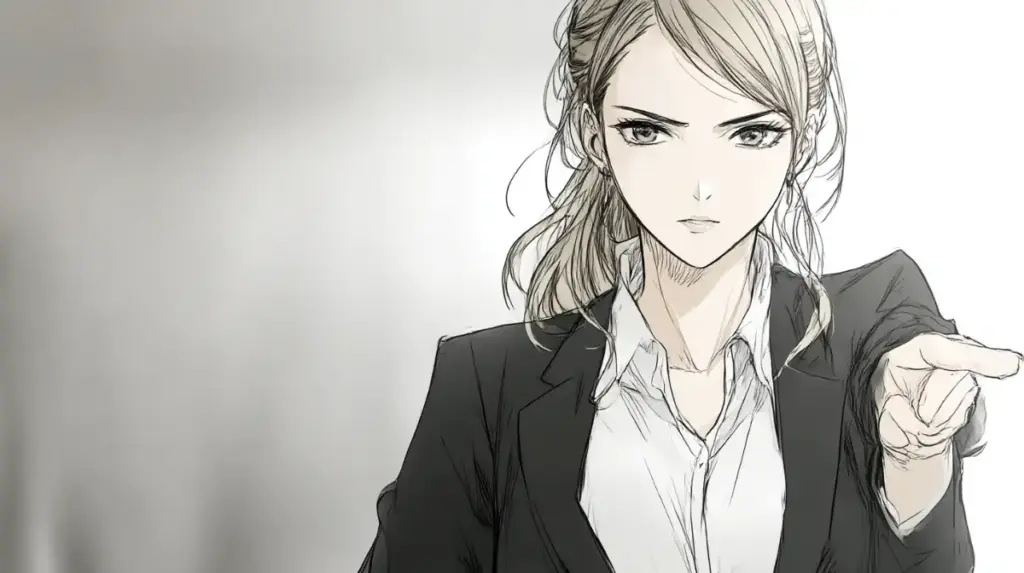
ケアマネの対応に対して「理不尽だ」と感じたときは、ただ我慢するのではなく、冷静に対処することが重要です。
まず、理不尽に思える対応に遭遇した場合は、その出来事を客観的に記録しておきましょう。
例えば、「〇月〇日にサービス内容を変更されたが、事前の説明がなかった」「希望していない事業所を強く勧められた」といったように、日時・内容・相手の発言などを具体的にメモに残しておきます。
この記録は後々、事業所や行政機関に相談する際に非常に役立ちます。
次に、直接ケアマネに「なぜそのような対応になったのか」を冷静に質問してみましょう。このとき、決して感情的にならず、「私はこう感じたのですが、どうしてこのような判断になったのでしょうか」といったスタンスで話すことがポイント。
多くの場合、ケアマネも制度上の制約や業務上の事情を抱えているため、事情を聞くことで納得できることも少なくありません。
それでも納得できない場合には、ケアマネが所属している事業所の管理者に相談する方法があります。事業所には、利用者からの相談を受けるための責任者が置かれているため、正式に話を通すことで、より中立的な対応を期待できます。
さらに、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに相談するという手もあります。これらの機関は、介護サービスの質を監督する立場にあり、公平な立場からアドバイスや是正措置を取ってもらえる可能性があります。
このように、ケアマネの理不尽な対応には「記録を取る」「冷静に直接確認する」「上位機関に相談する」という段階を踏んで対策していくことが大切です。
我慢し続ける必要はなく、むしろ早めに対処することで、ストレスを軽減し、より良い介護環境を整えることにつながります。



要介護認定の更新のタイミングでサービス担当者会議が開催されない、毎月のモニタリング訪問にケアマネが来ないなども、ルール違反なので申し出てくださいね。
ケアマネジャーと看護師はどちらの立場が上ですか?


ケアマネジャーと看護師の関係について、上下関係があるのかと疑問に思う方も少なくありません。しかし、実際には制度上、ケアマネジャーと看護師に上下関係は存在しません。
ケアマネは、介護保険制度の中で、利用者の生活全般を支えるためにケアプランを作成し、さまざまなサービス事業者との連携を図る役割を担っています。
一方、看護師は、医療・看護の専門職として、利用者の健康管理や医師の指示に基づく医療的ケアを行う役割を担っています。
つまり、それぞれが異なる専門分野を担当しており、業務の内容も目的も異なるのです。
例えば、ケアマネは利用者の生活の質を高めるために、どのサービスをどのくらい使うかを計画しますが、看護師は病気やけがの治療・予防を専門にしています。
互いの役割は補完的であり、どちらが上ということではなく、利用者のために協力し合うことが前提となっています。
ただし、現場では時に看護師の医療知識に対して、ケアマネが劣等感を持ったり、逆にケアマネがサービス調整の主導権を握ることから、上下関係のように見える場面もあるかもしれません。
しかしこれは、制度上のルールではなく、現場の人間関係や力量による部分が大きいといえます。
このように考えると、ケアマネジャーと看護師はそれぞれが専門家であり、対等な立場で連携することが求められる存在です。



どちらかが上であるべきではなく、互いに専門性を尊重しながら協働することが、利用者にとって最も良い支援につながるでしょう!
ケアマネと介護福祉士はどちらが上ですか?
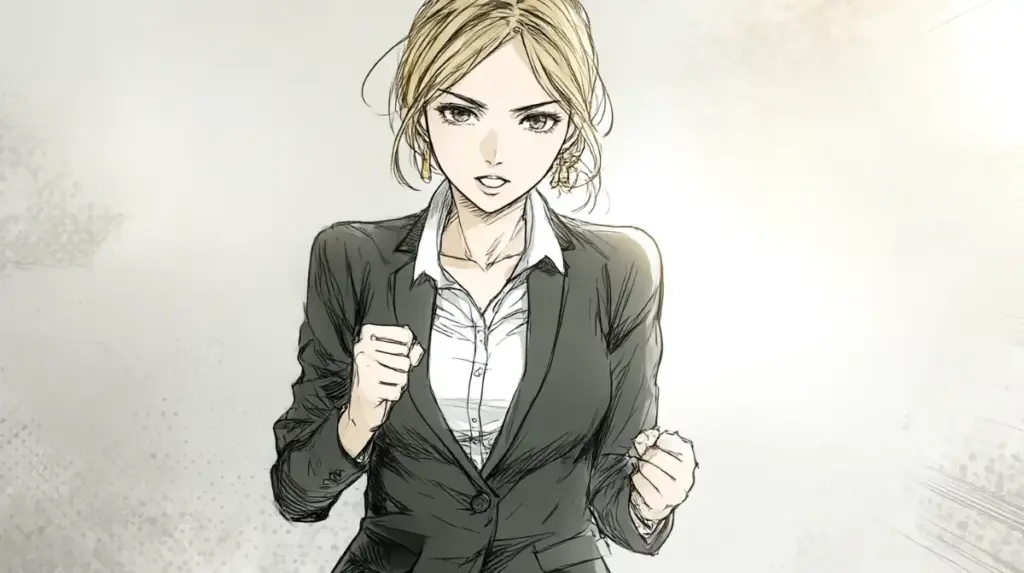
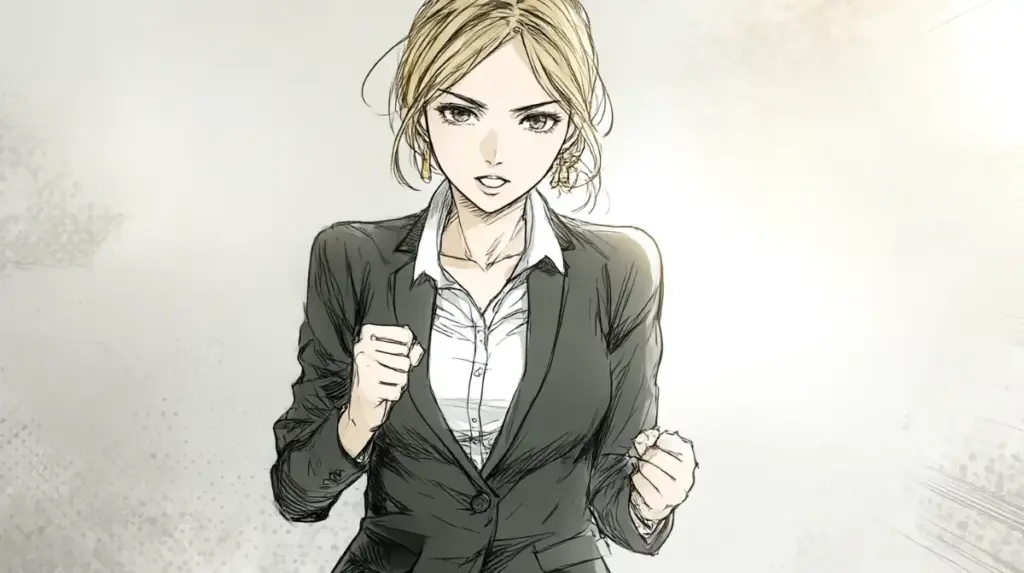
ケアマネと介護福祉士の間に、制度上の上下関係は存在しません。それぞれが異なる専門分野で役割を果たしており、どちらが上という考え方は適切ではないのです。
まず、ケアマネジャーは、利用者の生活全体を支援するためのケアプランを作成し、必要な介護サービスを調整する役割を担っています。これに対して、介護福祉士は、現場で実際に利用者の身体介護や生活援助を行う専門職です。
このように、ケアマネは「計画と調整」、介護福祉士は「直接支援」という形で、役割分担がなされています。
例えば、ケアマネが作成したプランに基づいて、介護福祉士が訪問介護やデイサービスで利用者をサポートします。
このとき、ケアマネが一方的に指示を出す立場であるわけではなく、現場の介護福祉士からのフィードバックを受け取りながら、必要に応じてプランを修正。こうして連携を図ることで、より良い支援が実現できるのです。
一方で、現場では「ケアマネのほうが偉い」と感じるような場面があるかもしれません。これは、ケアプランを決定する立場にケアマネがあるため、介護福祉士側が「指示される側」と意識してしまうことが原因の一つです。
しかし、本来は上下関係ではなく、専門職同士の協力関係であるべきです。
このように考えると、ケアマネと介護福祉士は立場に優劣はなく、それぞれの専門性を尊重し合いながらチームで利用者を支えていく存在だと理解することが大切です。
役割の違いをきちんと認識し、対等な関係で意見交換することが、より良いケアにつながります。



医師と看護師、ケアマネと介護福祉士、その他の専門職種など、全て利用者の生活を良くするためのチームで対等な立場ですよ!
ケアマネが合わない時には交代できる


ケアマネとの相性に悩んだ場合、無理に我慢する必要はありません。適切な手順を踏めば、ケアマネを交代してもらうことができます。
まず、ケアマネと合わないと感じたときは、自分の感情を整理することから始めましょう。例えば、「話がかみ合わない」「希望をうまく汲み取ってもらえない」「態度に不満がある」といった具体的な理由をはっきりさせることが重要です。
単なる好き嫌いではなく、支援に支障が出ている場合は、交代を考える正当な理由になります。
その上で、現在依頼している居宅介護支援事業所に「担当ケアマネを変えてほしい」と申し出ることができます。多くの場合、事業所内で別のケアマネに担当替えしてもらうか、事業所自体を変える手続きが案内されます。
このとき、感情的にならず、冷静に事情を説明することがスムーズな交代につながります。
注意点として、元の事業所を解約する場合には「新しいケアマネ」を事前に確保しておくことが非常に重要です。新しい担当者がいないと、ケアプランの作成やサービス利用に支障が出てしまう恐れがあるからです。
具体的には、他の居宅介護支援事業所に相談したり、地域包括支援センターに依頼先を紹介してもらう方法があります。
また、交代後のトラブルを避けるためにも、今後の希望やこれまで困った点を、新しいケアマネにしっかり伝えることが大切です。「こういう支援を望んでいる」という方向性を明確にすることで、より良い関係性を築きやすくなります。
このように、ケアマネが合わないと感じた場合は、早めに行動することが重要です。適切な支援を受けるためには、遠慮せず交代を検討し、自分自身の安心と満足を最優先に考える姿勢が求められます。



人同士なので相性問題でケアマネを交代した方がうまくいくこともあるでしょう。偉そうな態度に加えて、やるべきことがなされていないのであれば交代を申し出てくださいね。
ケアマネってそんなに偉いのかを総括して整理する
この記事のポイントをまとめます。
- ケアマネは介護保険制度上重要な役割を担うが偉いわけではない
- ケアマネが性格悪いと感じる背景には業務負担や制度上の制約がある
- ケアマネが何様と思われるのは説明不足や態度の問題が影響している
- ケアマネに腹立つときは制度上の理由か個人の問題かを見極めるべきである
- 最悪なケアマネージャーは高圧的・連絡不足・業務の雑さが目立つ
- ケアマネと喧嘩を避けるためには冷静な態度と具体的な要望伝達が必要である
- ケアマネとのトラブルを防ぐには事前に質問や確認を怠らないことが重要である
- 苦情を申し立てるときは冷静に記録を残し具体的に伝えるべきである
- 理不尽な対応に対しては記録と冷静な確認、必要なら上位機関への相談が効果的である
- ケアマネジャーと看護師には上下関係はなく対等な立場で連携するべきである
- ケアマネと介護福祉士も専門分野が異なるだけで立場に上下はない
- ケアマネが制度上の制約で希望を通せない場合も多いので早合点は禁物である
- 担当ケアマネと合わない場合は無理せず交代を検討するのが賢明である
- ケアマネの態度に違和感を感じたら早めに相談や交代の準備を始めるべきである
- 介護支援はチームワークであり上下意識ではなく協力意識が大切である

コメント