【徹底解説】グリコのアイスがタイで撤退!日本では今後も販売継続?
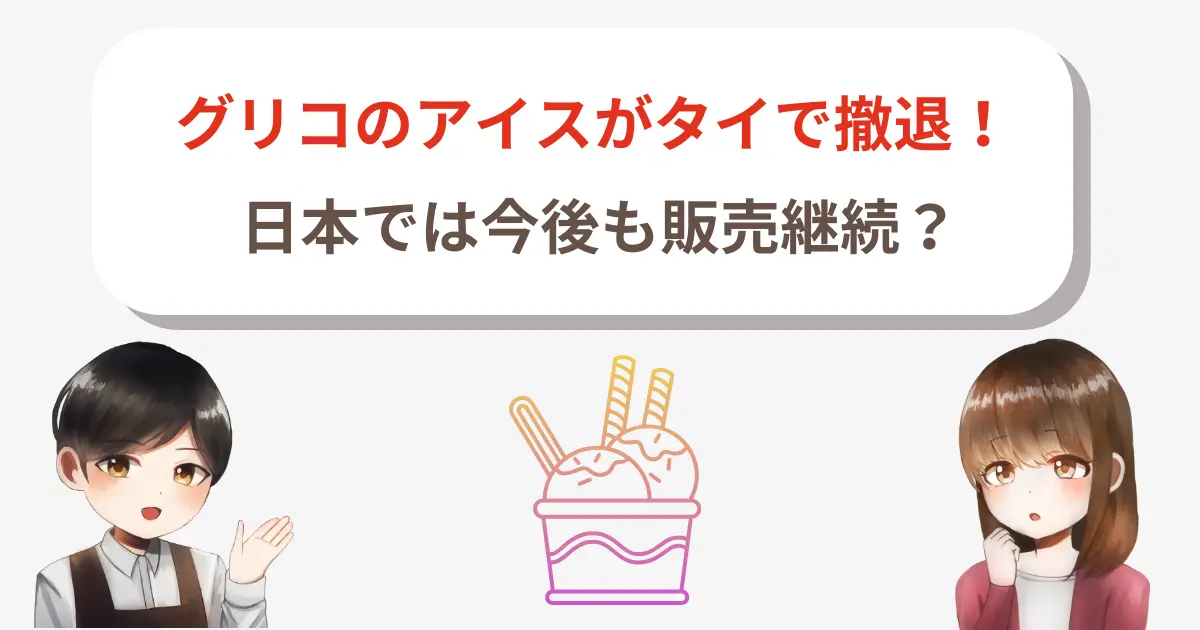
 あんこ
あんこ「グリコのアイスが撤退するらしい…え、日本でもパピコ食べられなくなるの?」
そんな声がSNSで広がったのは、2025年7月のこと。
実はこの話、グリコがタイ市場のアイスクリーム事業から撤退するというニュースで、日本国内の販売には一切影響がありません。
でもなぜ、グリコは海外展開していたタイでのアイス事業をやめたのでしょうか?
この記事では、そんな疑問に答えるべく「グリコ アイス 撤退」の真相を徹底解説します。
- グリコのアイスはなぜタイから撤退したのか?
- 日本では今後も販売が継続される理由とは?
- アイス事業をやめて何に力を入れるの?
- グリコが描く次なる成長戦略とは?



「撤退=失敗」とは限りません。グリコが選んだ“次の一手”に注目です!
グリコのアイスがタイで撤退!その背景と真相とは?
2025年7月3日に報じられた「グリコ アイス撤退」のニュースは、多くの人に衝撃を与えましたね。
でも実は、日本ではなく「タイ市場」限定の話なんです。
この記事では、なぜグリコがタイ市場から撤退を決断したのか、その背景を詳しく解説していきます。



まずは、タイ市場でグリコが直面した厳しい競争環境について見ていきましょう。
タイ市場での苦戦:強すぎた競合ブランドの壁
グリコがタイ市場で撤退を決めた最大の理由は、強力すぎる競合ブランドの存在です。
タイのアイス市場は、ユニリーバ傘下の「ウォールズ」やネスレといったグローバル企業が圧倒的なシェアを握っています。
彼らは安価な商品を武器に、大衆向けセグメントをガッチリと押さえていて、グリコの入る余地はなかなかありませんでした。
さらに、コンビニや移動販売などの販売網にも強みがあり、流通面でも圧倒的に優位に立っていたんです。
グリコはプレミアム路線で勝負しましたが、ソフトクリームブランドの台頭や、地元のトレンディなブランドの登場で、その立ち位置もどんどん苦しくなっていきました。
つまり、どのセグメントでも優位性を保てなくなってしまったんです。
このように、タイ市場では「価格競争」と「ブランド競争」の二重苦が重くのしかかっていました。



次は、そんな厳しい環境の中でグリコがどんな数字を出していたのか、財務面から検証していきます。
財務データが示す撤退の必然性
タイ市場での競争が激化する中、グリコの財務状況も悪化の一途をたどりました。
2020年と2021年はまだ黒字を維持していたものの、2022年には赤字へと転落。
2023年には1億バーツを超える損失を計上するなど、収益性は急速に低下していきました。
売上自体はある程度維持していたものの、利益が継続的に失われていたことが数字からもはっきり読み取れます。
以下の表を見ると、その流れが一目でわかります。
| 年度 | 総売上高(億バーツ) | 純利益/純損失(百万バーツ) | 主な市場の出来事 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.1 | +394.58 | 安定した収益期 |
| 2021 | 41.5 | +179.44 | 利益の減少が始まる |
| 2022 | 48.9 | -1.27 | 赤字転落 |
| 2023 | 34.9 | -112.94 | 大幅な赤字 |
| 2024 | 35.2 | +67.35 | 一時的な回復 |
このように、2020年の394.58万バーツの黒字から、2023年には1億1294万バーツの大赤字に転落。
事業継続が難しいと判断されるのも無理はありません。
このような厳しい現実が、戦略的撤退を決断させた背景にあるのです。



次は、グリコが掲げたプレミアム戦略が、なぜタイ市場で通用しなかったのかを見ていきます。
プレミアム戦略の限界と市場の変化
グリコは日本で培った高品質なブランドイメージを武器に、タイ市場では「プレミアムアイス」として勝負を挑みました。
「ジャイアントコーン」や「パピコ」などをそのまま展開し、当初は新鮮さから品切れが相次ぐほどの人気ぶりでした。
でもその熱狂は、残念ながら長続きしませんでした。
理由のひとつは、プレミアム市場そのものが急速に混雑してきたことです。
「ハーゲンダッツ」などの既存ブランドに加え、MoltoやGuss Damn Goodといった地元のおしゃれ系ブランドも次々登場。
グリコが築いたセグメントに、次々と競合が参入してきたことで、かつての“日本発ブランドの目新しさ”が薄れてしまったんですね。
さらに、ソフトクリーム市場の急成長も見逃せません。
特に「MIXUE(蜜雪冰城)」のような中国発の格安ソフトクリームがブームになり、消費者の選択肢が大きく広がったんです。
このように、グリコは大衆向けでは価格競争に勝てず、プレミアム市場でも個性を出しきれず、両側から圧迫される“挟撃状態”に追い込まれていきました。
それでは、なぜ日本ではこのような状況になっていないのか?



次の章では、日本でグリコのアイスが撤退しない理由を、しっかり解説していきます。
日本では今後も販売継続?グリコの国内アイス戦略を解説
タイ市場からの撤退が発表されたことで、「日本のグリコアイスもなくなるのでは…?」と不安になった人も多いと思います。
でも安心してください!
グリコのアイス事業は日本国内ではむしろ“主力中の主力”であり、今後も変わらず販売が継続される見込みです。
ここでは、なぜグリコが日本では撤退する必要がないのか、その理由を事業構造やブランド力の面から詳しく解説していきます。



まずは、日本市場でグリコが圧倒的な強さを誇る理由から見ていきましょう。
日本市場はなぜ安泰なのか?圧倒的なブランド力
日本でのグリコアイスは、単なるスイーツを超えた“文化的アイコン”としての地位を確立しています。
「パピコ」「アイスの実」「ジャイアントコーン」など、どれも子どもの頃から親しんできた定番ブランドばかり。
こうした長年のブランド蓄積が、他の企業には真似できない“絶対的な信頼感”を築いているんです。
さらに、販売チャネルも超強力。
コンビニ、スーパー、自販機など、どこに行ってもグリコのアイスが置かれていて、生活に溶け込んでいます。
消費者からのロイヤルティが非常に高く、簡単に他社製品に切り替えられるものではありません。
これだけ強固な基盤がある限り、日本でグリコのアイスが消えるようなことはまず起こらないでしょう。



次は、グリコの国内事業がなぜここまで安定しているのか、流通や生産体制にも注目してみましょう。
国産生産体制と販売網が支える国内市場
グリコのアイス事業が日本で安定しているもうひとつの理由は、国内にしっかりとした生産と流通のインフラを持っているからです。
タイではOEM生産(外部委託)によって製造を行っていましたが、日本では自社工場と研究開発拠点をフルに活用し、高品質な商品を安定供給できる体制が整っています。
また、日本全国に流通網を構築しており、スーパーマーケットからコンビニ、自販機にいたるまで、グリコのアイスが届かない場所はほとんどありません。
このように、商品の「質」と「量」の両方をコントロールできる仕組みがあるからこそ、市場の信頼も厚く、長年にわたってトップブランドとして君臨し続けているのです。
さらに、物流体制の強さは災害や異常気象などのリスクにも強く、継続的な販売を支える重要な基盤になっています。



次は、タイと日本それぞれの事業構造を比較しながら、なぜ一方は撤退し、もう一方は継続なのか、その“根本的な違い”に迫っていきます。
タイと日本、戦略と構造の決定的な違いとは?
タイと日本、どちらもグリコが展開している国ですが、その事業の中身はまったく別物です。
タイは2016年にスタートした“海外初の挑戦”であり、プレミアム市場を狙った限定的な戦略展開でした。
一方の日本は、1985年から続く歴史ある中核事業。グリコにとっての“牙城”とも言える存在です。
まず大きな違いは、事業モデル。
タイではOEMによる外部委託生産を採用しており、撤退も比較的容易な“アセットライト型”。
それに対して日本では、自社工場と研究開発体制を持つ“フルインハウス型”で、深く国内市場に根ざしています。
ブランドの位置づけも異なります。
タイでは「新しい日本製品」という目新しさに依存していたのに対し、日本では「長年愛される定番商品」として強力なロイヤルティがあります。
このように、同じグリコのアイスでも、事業構造・市場の成熟度・ブランド戦略のすべてが根本から異なっているのです。
だからこそ、タイでは撤退が合理的な判断となり、日本では今後も継続することが明確なんですね。



ここまでで、タイと日本の違いが見えてきたところで、次はグリコが見据える「次の一手」について掘り下げていきます。
撤退の先に見据える未来:グリコの次なる成長戦略とは?
タイ市場でのアイスクリーム事業撤退は、単なる“撤退”ではありません。
それは、グリコが次なる成長の柱に向けて大きく舵を切った「戦略的再配置」でもあります。
今後の焦点は、「アーモンド効果」を中心とした健康・ウェルネス分野。
この章では、グリコがどのようにしてアイスから次のステージへ進もうとしているのか、その戦略と展望を解説していきます。



まずは、グリコが注力を始めた“アーモンド効果”について見ていきましょう。
アイスからアーモンド効果へ?注力分野の転換
グリコはアイス事業の縮小と引き換えに、健康飲料「アーモンド効果」にリソースを集中させ始めています。
実はこの商品、日本国内ではすでに“アーモンドミルク市場の売上No.1”を獲得している実績あるブランドなんです。
グリコはこのアーモンド効果を、タイ市場にも本格展開。
なんと、初年度から「市場トップ3入りを狙う」と宣言するほど、強気な姿勢を見せています。
背景には、東南アジアにおける健康志向の高まりがあります。
高齢化や中間層の生活水準向上により、植物性ミルクや低カロリー飲料の需要が急速に伸びているんですね。
つまり、グリコは「成熟した競争市場」から、「成長著しい未来市場」へと、大胆にポジションを変えようとしているんです。



次は、こうした健康志向のトレンドが、どれほどのビジネスチャンスを生んでいるのかを見ていきましょう。
健康志向と東南アジア市場の可能性
グリコがアーモンド効果に注力する背景には、明確な市場データがあります。
現在、タイをはじめとする東南アジアでは“健康志向”が急速に広がっており、その中でも植物性ミルク市場は注目の成長分野です。
以下のデータからも、その成長率の高さがよくわかります。
| 年度 | 植物性ミルク市場規模(バーツ) |
|---|---|
| 2022年 | 約9.6億バーツ |
| 2026年 | 約30億バーツ |
※2022年比で約3倍の市場成長が予測されています。
このように、高齢化や中間層の増加によって健康的な食生活を求める人が急増中。
グリコが「アーモンド効果」でそのトレンドを取りに行くのは、非常に理にかなっていますね。
さらに、日本や中国での成功実績もあるため、勝ち筋が見えている状態での展開と言えます。



では最後に、このような撤退と投資のバランスが、グリコの経営戦略としてどんな意味を持つのかを見ていきましょう。
「選択と集中」が導く経営戦略の本質
グリコのタイ市場撤退は、一見すると“失敗”や“撤退戦”のように見えるかもしれません。
でもその実態は、経営戦略としての「選択と集中」を実践した好例なんです。
企業にとって、すべての事業で勝ち続けることは不可能です。
だからこそ、勝てる市場・伸びる分野にリソースを再配分する判断が重要になってきます。
タイでのアイス事業は赤字が続き、利益率もどんどん低下。
一方で、植物性ミルク市場のように将来性があり、成長が期待できる分野に資源をシフトすることは、企業としてごく自然な流れです。
加えて、グリコは株主に対して「ROE(自己資本利益率)を6〜8%に引き上げる」「連結配当性向を45%以上に保つ」といった厳格な財務目標を掲げています。
このような背景を考えれば、タイ市場で苦戦を強いられていたアイス事業の撤退は、単なるコストカットではなく、全社的な利益最大化のための戦略的判断だったということがよくわかります。



まさにこれは、「成熟した企業がとるべき経営の再構築」そのものなんですね。
グリコ アイスのタイ撤退を通して見えた企業戦略の本質とは?
今回のグリコ アイス撤退のニュースは、日本の消費者にも大きな注目を集めました。
しかしその内容を深掘りしてみると、単なる撤退ではなく、企業としての次なるステージに進むための「戦略的再構築」であることが見えてきます。
以下に、記事の要点を整理しておきます。
- グリコ アイス撤退はタイ市場限定で、日本では今後も販売継続
- タイ市場では競争激化やプレミアム戦略の限界に直面
- 売上よりも利益率の悪化が深刻で、財務的に撤退が妥当と判断
- 日本では高いブランド力と生産・流通の基盤により撤退の可能性なし
- 撤退はマイナスではなく、健康飲料「アーモンド効果」などへの再集中
- 経営目標や株主還元を見据えた、理にかなった経営判断だった
今回の決断を通じて、グリコは「勝てる領域」に経営資源を集中させる方向へとシフトしています。



これは単なる縮小ではなく、むしろ企業の未来を切り拓くための、前向きな選択と言えるでしょう。
日本国内ではパピコもジャイアントコーンも販売は継続なので安心ですね。
夏の暑い時期にはやっぱりグリコのアイスが最高!!



ちなみに僕はパピコ推しです。笑
コメント