7月5日に予言で休業|損害賠償は予言者やインフルエンサーに請求できる?
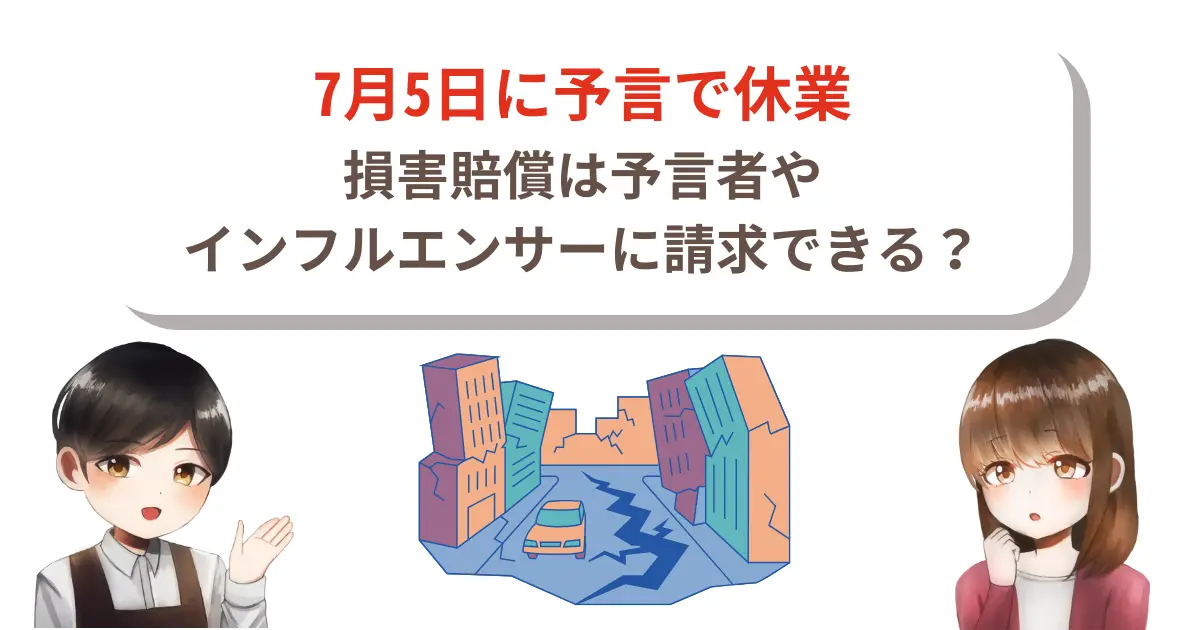
2025年7月5日、災害が起きるという“予言”がSNSや動画サイトで大きな話題となり、実際に休業を決める店舗も出始めています。
「もし何も起こらなかったら…損害はどうなるの?」「責任を取るべき人はいるの?」と不安や疑問を感じる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、予言者やインフルエンサーに対して損害賠償を請求できる可能性について、法律の観点からわかりやすく解説します。
 よーかん
よーかんデマに惑わされず、冷静に判断するための視点を知っておきましょう。
- 「7月5日予言」はどのような内容で、なぜ社会的に影響が広がったのか
- 休業などによって損害が出た場合、誰かに損害賠償請求できるのか
- 法的に予言者やインフルエンサーに責任を問える可能性とその条件
- 情報に惑わされず、冷静な判断をするために必要な視点と備え方
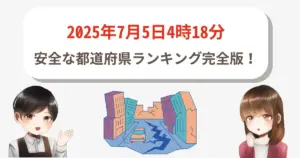
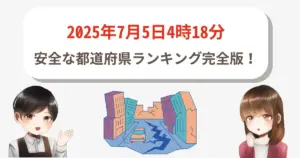
7月5日 予言で休業して損害?背景と社会的影響とは
2025年7月5日を目前に控え、「予言」による社会的混乱が広がりを見せています。
単なるオカルト話では済まされないレベルで経済や世論に影響を与えており、今や企業や店舗にとっても無視できない問題となっています。



ここでは、どんな予言が発端になっているのか、そしてなぜここまでの騒動に発展したのかを解説しますね。
「2025年7月5日予言」の内容と広がり
すべての発端は、漫画家・たつき諒さんの著書『私が見た未来 完全版』に記された “夢” の内容でした。
その夢とは「2025年7月5日に日本の太平洋側に巨大津波が来る」というもので、東日本大震災の3倍の被害を想定した衝撃的な予言です。
この書籍は累計90万部を突破し、予言はYouTubeやSNSを通じて爆発的に拡散されました。
検索エンジンでは関連ワードが上位に並び、防災グッズの購入が急増するなど、予言の影響は一部の消費行動にも波及しています。



「夢」として語られた内容が、多くの人々に「現実の脅威」として受け止められている現状は、情報社会における不安の拡がりやすさを物語っていますね。
企業や店舗に起きた実際の反応と影響
予言が「話題」から「社会現象」に変わった大きなポイントは、実際の経済行動に影響を与えている点です。
例えば、香港の一部航空会社が日本便を減便する判断を下したと報じられ、海外の動きにも波紋が広がっています。
国内では、個人経営の飲食店や美容室などが「7月5日は休業予定」とSNSで公表するケースも出てきており、すでに“自主的な休業宣言”が複数見られます。
売上への打撃や仕入れの調整、人件費の負担を考慮すれば、こうした判断は経営に少なからぬ影響を及ぼすことになります。
しかしこの時点で、あくまで災害は「起こるかもしれない」という予測に過ぎず、「信じた側にも責任があるのでは?」という声も出始めています。



では、こうした“予言による経済損害”は誰の責任になるのでしょうか?
損害賠償は可能なのか? 次のパートで詳しく解説します。
損害賠償はインフルエンサーや予言者に請求できるの?
7月5日を前に休業を決断する動きもある中、「損害が出たら誰が責任を取るの?」という疑問が多くの人の頭をよぎります。
特に話題の中心である予言者や、情報を拡散したYouTuber・インフルエンサーに対して、法的な責任を問えるのかという声も出始めています。



ここでは、予言者と拡散者それぞれについて、法律的な観点から検証していきます。
法律的に予言者に責任を問えるのか?
まず予言者、つまり「大災難が起こる」と発信した本人に損害賠償を請求できるのかという点について。
結論から言えば、原則として請求は極めて困難です。
その理由は、損害賠償請求を成立させるには「違法性」「損害」「因果関係」という3つの要件を満たす必要があるからです。
しかし、「個人の夢を本に書いて発表した」という行為自体は、法律的に違法とはされません。
さらに、たとえ予言を信じて休業し損害を被ったとしても、最終的に休業の判断をしたのは経営者自身であり、自己責任の原則が適用されます。
この考え方は、投資や占いなどのケースと同様で、アドバイスを信じて行動した結果が不利益だったとしても、発信者に賠償責任が問われることは基本的にないのです。



次に焦点となるのが、予言を広めたYouTuberやSNSの拡散者です。
YouTuberやSNS拡散者の法的責任は?
予言の情報を拡散したインフルエンサーやYouTuberが、法的責任を問われる可能性はゼロではありません。ただし、それも条件付きです。
重要なのは、「どのような意図で、どういう形で情報を発信したか?」という点。
たとえば…
- 予言の話を「興味深い夢の話」として紹介し、断定的な言い回しを避けていた場合
- 動画内で「信じるかどうかはあなた次第」「自己判断でお願いします」といった注意書きをしていた場合
このようにエンタメや話題提供としての発信であれば、責任を問われる可能性は低くなります。
一方で
- 予言を事実のように断定し、「今すぐ避難すべき」と強く煽った場合
- アフィリエイトで防災グッズを売ったり、自身の商材に誘導していた場合
こうした過度に扇動的で商業的な発信は、「注意義務違反(過失)」として民事責任が問われるリスクがあります。
また、2024年10月施行の改正景品表示法により、誇張的な広告発信に対する法的規制が強化されたことも見逃せません。
つまり、インフルエンサーが損害賠償の対象となるかどうかは、「その発信がどれだけ人をミスリードしたか」「商業目的がどの程度あったか」が重要になるのです。



では、予言者やインフルエンサーに損害賠償を求めるにはどんな法律の壁があるのか?
次の章で具体的に解説していきますね。
法律的に損害賠償が成立するには?3つの壁とは
「損害を受けたのだから、誰かに請求したい」と感じるのは当然の心理です。しかし法律の世界では、感情よりも厳密な条件が重視されます。
ここでは、損害賠償が成立するために乗り越えなければならない3つの法的ハードルを見ていきましょう。
自己責任の原則とは何か
最も基本的な壁は「自己責任の原則」です。
これは、日本の民法が大切にしている「私的自治」という考え方に基づいています。
つまり、何を信じるか・どう行動するかは自分の自由であると同時に、その結果については自分で責任を持つということです。
予言を信じて休業するかどうかを決めたのは、あくまでも経営者自身。
たとえその情報が不確かなものであっても、自主的に判断した結果であれば、損害を誰かに転嫁するのは非常に難しいのです。



この考え方は、占いや株式予測などにも通じるものがあります。
相当因果関係の有無が分かれ目
次に問われるのが「相当因果関係があるかどうか」です。
たとえば、「予言を見た→休業した→売上が落ちた」という流れがあったとしても、それだけでは法的には不十分です。
大事なのは「予言がなければ、通常、その損害は起きなかったと社会的に評価されるかどうか」。
つまり、「一般的に一冊の本の夢を信じて休業するなんて予見できる?」という視点で判断されるということです。
裁判所はこうしたケースで、予言よりも“経営者の個人的な判断”を損害の主な原因と見る傾向が強いです。



そのため、相当因果関係が認められるケースは非常に限られています。
違法性がなければ責任は問えない
最後のハードルは「違法性の有無」です。
損害賠償を請求するには、相手の行為が違法であることが必要です。
しかし、予言のような「個人の夢や信条を表現する行為」は、日本国憲法で保障された表現の自由に該当します。
よほどのことがない限り、それが違法と判断されることはありません。
つまり、たとえ多くの人に不安を与えたとしても、夢を語っただけでは罪にならないというのが法律の立場です。
これら3つの壁「自己責任」「相当因果関係」「違法性の欠如」があるため、予言を信じて休業した場合の損害について、予言者や拡散者に損害賠償を請求するのは、かなり難しいというのが現実です。



ただし、全く可能性がないわけではありません。
次は「例外的に損害賠償が成立するケース」について掘り下げていきます。
例外的に損害賠償が成立するケースとは?
原則として損害賠償は難しいとされる予言の問題ですが、じつはごく限られた状況下では「法的責任が問われる可能性」が存在します。



ここでは、どのような場合にその“例外”が認められるのか、具体的なシナリオに分けて解説していきますね。
詐欺的な商法や悪質な勧誘がある場合
もっとも典型的な例外が「詐欺や不当な勧誘にあたる場合」です。
例えば、
- 「このお守りを買えば7月5日の災害から絶対に助かる」
- 「この祈祷を受ければ予言は回避できる」
- 「高額でも安全な場所を教える」
といった内容で商品やサービスを売っていたとしたら、それは不当表示や詐欺に該当する可能性が出てきます。
こうしたケースでは、購入者が騙されたことに対して、消費者契約法や民法の不法行為に基づき損害賠償や返金請求が可能になります。
特に、実在しない人物を装って信用させたり、断定的な言い回しで不安を煽るようなやり方は、過去の裁判でも不法行為として認定された事例が多数あります。



「占いが外れたから」ではなく、「欺いてお金を取った」ことが問題なのです。
特定の企業や個人を狙った業務妨害・信用毀損
もう一つの例外は「特定の誰かを狙った虚偽情報の拡散」です。
たとえば、「◯◯レストランの場所は地震で崩れる」「△△社のビルは津波で流される」など、特定の実在する企業や人の信用を傷つけるような内容を含んでいた場合。
これが拡散され、客離れや営業妨害が生じたなら、信用毀損罪や偽計業務妨害罪といった刑法が適用される可能性もあります。
ただし今回の「7月5日予言」は、あくまで大規模な自然災害に関するものであり、特定の企業や個人を名指ししているわけではありません。
そのため、このケースには当てはまりにくいと考えられます。
とはいえ、今後もし誰かがこの予言を利用して特定の相手に対してデマを流したり営業を妨害した場合は、損害賠償や刑事罰の対象になるリスクも否定できません。
まとめると、例外的に損害賠償が成立するのは
- 予言を利用した金銭目的の詐欺や不当勧誘
- 特定の相手に向けた虚偽の風評被害
など、すでに法律で明確に禁止されている行為と結びついていた場合に限られるということです。



では、こうした情報を拡散した人に対してはどうなるのでしょうか?
次は「情報発信者が負う可能性のあるリスク」について掘り下げます。
情報発信者の注意義務とリスクとは?
YouTubeやSNSなど、個人が誰でも簡単に情報を発信できる時代。「予言」を取り上げて話題にするインフルエンサーや動画配信者は数多く存在します。
では、こうした発信者たちは法的にどこまでの責任を負うのでしょうか?
ここでは、情報発信者に課せられる注意義務とリスクについて解説します。
SNSやYouTubeの発信に求められる責任
予言の話をSNSや動画で紹介すること自体は、基本的には表現の自由の範囲内とされています。
しかし、以下のような場合には法的リスクが高まる可能性があります。
- あたかも事実であるかのように断定的に語る
- 不安を過剰に煽るような演出やサムネイルを使用する
- 商材やアフィリエイト商品に誘導し、収益を得る構成になっている
- 「助かりたい人は今すぐこれを買って」など、視聴者の判断を歪める表現がある
このような発信は「注意義務違反」とみなされ、民事責任や行政指導の対象になる可能性があります。
また、被害が集団的に発生した場合には、発信内容によっては集団訴訟に発展するリスクも否定できません。



YouTuberだからといって免責されるわけではなく、インフルエンサーには一定の社会的責任があるという認識が求められています。
景品表示法と商業的発信の規制
2024年10月に改正された景品表示法にも注目です。
この改正により、「事実と異なる表示を使って不当な利益誘導をする行為」への取り締まりが強化されました。
たとえば、
- 「これで災害は回避できる!」と謳って商品を売る
- 実際には根拠のない予言に“科学的裏付け”があるかのように見せかける
といった行為は、誇大広告や優良誤認表示に該当する可能性があります。
行政処分や罰則が科されるケースもあり、収益化を前提とした発信にはより慎重さが求められています。
予言をエンタメとして扱うことと、不安を利用して金銭的利益を得ようとする行為の線引きが、これからますます重要になっていくでしょう。
では、こうした情報に触れる側は、どのような心構えを持っておくべきなのでしょうか?



最後に、読者が「予言」と向き合う上での注意点を解説しますね。
読者が気をつけるべきことと正しい備え方
SNSやYouTubeを通じて「不安」が一気に拡がる今の時代。
私たち一人ひとりが情報をどう受け止め、どう判断するかがこれまで以上に重要になっています。



ここでは、予言のような話題に接したときに意識しておきたいポイントを紹介します。
デマに惑わされないための情報リテラシー
まず大切なのは、「情報の出どころを確認する習慣」です。
予言のような話は、発信者の信念や主観が強く反映されていることが多く、客観的な裏付けがないケースがほとんどです。
情報を見聞きしたときは、
- それが事実に基づいているか
- 誰がどんな立場で発信しているのか
- 科学的・法律的な根拠があるのか
などを冷静に確認することで、無用な不安や誤った行動を防ぐことができます。
また、SNSでバズっているからといって、内容の正確さが保証されているわけではありません。



「情報が多い=信頼できる」ではないという意識を持つことが、現代の情報社会を生き抜くカギになります。
経営判断を下す際に見るべき情報源
店舗や企業が営業を判断する際は、風評よりも公的な情報を重視すべきです。
たとえば、
- 気象庁や地震研究所の公式発表
- 地方自治体や官公庁からの通達
- 総務省・内閣府などの防災関連サイト
といった信頼性の高いソースを常に確認し、感情的な判断を避けるよう心がけましょう。
不安になったときほど、冷静な情報収集が大切です。
さらに、どうしても心配なときは「営業を短縮する」「スタッフに在宅勤務を促す」など柔軟な対応を検討することで、過度なリスクを避けつつ、経済活動を維持する選択も可能です。



不確かな情報に踊らされず、「信頼できる根拠に基づいた行動」が、経営にも生活にも大きな安心をもたらします。
「じゃあ、7月5日にどこなら安全そうなの?」という方にはこちらの記事もおすすめです。
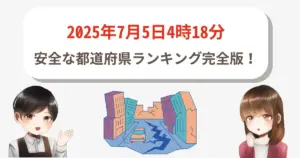
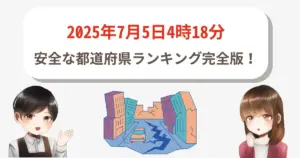
まとめ|7月5日の予言と損害賠償、予言者やインフルエンサーの責任は?
今回の記事では、2025年7月5日の予言に関連して、休業などの対応によって生じる損害と損害賠償の可能性について解説しました。
以下に、記事の要点をまとめます。
- 「7月5日に災害が起こる」という予言は、たつき諒氏の夢をもとにしたもので、科学的根拠は存在しない
- 予言を信じて休業したことによる損害は、原則として自己責任とされる
- 予言者やインフルエンサーに損害賠償を請求するには、違法性・因果関係・注意義務違反など厳しい要件が必要
- 詐欺的な商法や特定の人物・企業に対する虚偽情報による損害ならば、例外的に法的責任が問われる可能性もある
- 情報に接する際は、発信の意図や根拠を見極め、冷静に判断することが重要
不確かな予言によって判断を誤り、後悔する前に。



感情ではなく、信頼できる情報に基づいて行動することが、私たちにできる最も確かな備えでしょう。
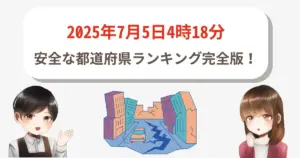
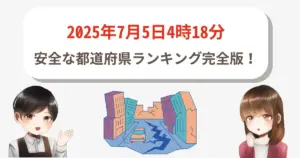
コメント