介護職員の自己評価シート例文まとめ|高評価される書き方のコツも解説

 あんこ
あんこ「自己評価シートって、何を書けばいいの?」
「例文を見てもピンとこない…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
僕自身も、介護職として働き始めた頃は自己評価が苦手でしたし、今では部下や後輩の評価を書く立場としても、「伝わる書き方」に悩む声をたくさん聞いてきました。
この記事では、介護業界で20年勤めていて、現役の主任ケアマネである僕が、実際の現場経験に基づいて、「そのまま使える自己評価例文」を32個ご紹介します。
さらに、評価されるためのコツ・NG表現・例文の選び方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説しています。
自己評価は“ただの提出物”ではありません。ちゃんと書けば、あなたの頑張りを上司に伝える大きな武器になります。



ぜひこのページを参考に、自信をもって自己評価シートを仕上げてくださいね。
- 自己評価シートにそのまま使える具体的な例文
- 評価されやすい自己評価の書き方のコツ
- よくあるNG表現と改善のポイント
- 自己評価が転職活動にも活かせる理由
【例文32選】介護職の自己評価シートにそのまま使える文例集!


「自己評価、何を書けばいいのか分からない…」という声を本当によく聞きます。僕自身も部下にアドバイスしてきた経験から、介護職員の現場目線で“そのまま使える”例文を30個厳選しました。



それでは、さっそく順番に解説していきますね。
①新人・初任者向けの自己評価例文
新人介護職員が自己評価を書くときは、「覚える姿勢」「基本動作」「報連相」などが主な評価ポイントになります。
まだ大きな成果はなくても、素直さや成長意欲をしっかり伝えることが大切です。
介護の現場に入ってからは毎日の業務を通じて基本動作を習得するよう努力し、先輩職員の動きを観察しながら実践での学びを重ねてきました。まだ不慣れな点もありますが、できることを一つずつ確実に増やしていけるよう、引き続き業務に励みたいと思います。
利用者様一人ひとりのお名前と顔を覚えることを目標にし、挨拶やちょっとした声かけを通じて関係性を築くよう心がけてきました。日々のコミュニケーションを通して、信頼関係を少しずつ築けている実感があります。
報告・連絡・相談を徹底することを自分の課題とし、業務中に気づいた点は速やかに先輩職員に伝えるよう意識してきました。情報共有の大切さを日々感じており、今後も信頼される職員を目指して取り組んでいきたいです。
入職後すぐに介護職員初任者研修を受講し、基礎的な介護技術の理解と実践力を養うことに努めました。現場での経験と学びを結びつけることで、より実践的なスキルの向上に取り組んでいます。
業務中に分からないことがあればそのままにせず、必ず確認・メモを取るようにし、同じ失敗を繰り返さない姿勢を持ち続けています。失敗も学びと捉えて、前向きに業務に向き合うよう努力しています。
清潔保持や移乗介助などの基本業務においては、マニュアル通りに行うだけでなく、先輩職員からのフィードバックを取り入れながら少しずつ自分なりの工夫を重ねてきました。利用者様の安心につながるよう、丁寧な対応を今後も心がけていきたいです。
この段階では「できないことを隠す」よりも、「できるようになろうとしている姿勢」が大事です。



僕自身も新人の頃は、完璧にやろうとして空回りしたこともありました。だからこそ、“誠実さ”が伝わる文が評価されやすいんですよ。
②中堅職員向けの自己評価例文
中堅職員になると、基本的な業務の遂行力に加えて、チーム連携や後輩指導、改善提案など“職場全体をよくする姿勢”が求められます。
僕もこの時期に「現場の空気を変えられる人」を意識して動いていました。
業務の正確性と効率を意識し、利用者様への対応だけでなく、チーム全体の業務が円滑に回るよう動くよう心がけてきました。特に他職種との連携を強めるため、情報共有のタイミングや伝達方法の見直しを行いました。
新人職員のOJTを担当し、業務手順だけでなくメンタル面のサポートにも配慮しました。相手の理解度に合わせた指導を心がけ、定期的にフィードバックを行うことで、安心して現場に立てる環境づくりに貢献しました。
毎月の業務ミーティングにて、ヒヤリハット事例の共有と改善策の提案を継続的に行っています。実際に排泄介助時の手順を見直すことができ、事故防止にもつながったと実感しています。
認知症ケアの専門性を高めるために外部研修に参加し、その学びを職場内で共有しました。職員間での対応方針を統一するきっかけになり、利用者様への声かけの質も向上したと感じています。
チーム内の雰囲気作りにも力を入れており、日々のちょっとした声かけやフォローを大切にしています。スタッフ間の関係が良好になることで、利用者様にもより丁寧な対応ができるようになりました。
自分の業務に加え、後輩や新人職員が困っているときには声をかけるようにしています。全体の流れを見ながらサポートする姿勢を意識し、相談しやすい存在として信頼されるよう努めてきました。



中堅の自己評価では、“自分だけができるようになった”ではなく、“周りの成長や職場の改善にどう関わったか”を言語化できると、上司にも響きやすいですよ。
③ベテラン・管理職向けの自己評価例文
ベテランやリーダー職になると、「数字で語れる成果」「マネジメント視点」「人材育成への関与」などがポイントです。
僕も小規模多機能ホームでは管理者として、現場を守るだけでなく、後進を育てる責任を日々感じてきました。
チーム全体の業務改善を目的に、スタッフ間の情報共有ツールを導入・運用しました。導入後は申し送り漏れが減少し、月間報告ミスも2割削減。業務の効率化と現場の安心感につながったと感じています。
離職率の高さが課題となっていたため、個別面談と職員アンケートを実施。現場の声をもとに勤務体制と教育支援を見直した結果、前年より離職者数が約40%減少しました。継続的な定着支援が重要だと再認識しました。
主任として業務シフトの調整を担当し、スタッフの負担を平準化する体制を構築しました。業務量の偏りを防ぎながら、ご利用者への介護サービスの質も保てるよう工夫しています。結果として有給取得率も向上しました。
ベテラン職員として後輩指導に積極的に関わり、個々の成長に合わせたOJTを実施しました。新人時代の戸惑いを理解して寄り添う姿勢が、結果的に職場の風通しの良さにもつながっています。
高齢化が進む地域において、地域包括ケアの担い手として多職種との会議にも定期参加。在宅支援や医療機関との連携強化を通じて、利用者様の生活の質向上に貢献しています。
感染症対策の取り組みでは、マニュアルの更新と職員への周知をリーダーとして主導しました。現場からの意見も積極的に取り入れ、実践に即した運用ができたことで、クラスター発生も防止できました。



ベテランの評価は、「経験年数」だけではアピールになりません。具体的に何を成し遂げたか、数字や成果を添えて説明すると、信頼感がグッと増しますよ。
④苦手・課題を書くときの自己評価例文
自己評価では、「自分の弱み」を書くことに戸惑う方が多いです。でも正直に書くだけではダメで、「どう改善しようとしているか」までセットで伝えることが大切。
僕も部下を見るときは、その姿勢を一番見ています。
忙しさに追われると報告のタイミングが遅れることがあり、チーム内の連携に影響を与えてしまうと感じています。今後は、業務の合間でも優先順位を意識し、報告すべき内容を簡潔に共有できるよう努力します。
状況の変化に臨機応変に対応する力がまだ不十分であり、特に複数の業務が重なった際に焦ってしまう傾向があります。冷静な判断ができるよう、事前の業務整理や心構えを強化していきたいと考えています。
利用者様との会話中、意図をうまく汲み取れずに返答に詰まることがあります。傾聴力を高めるため、相手の話を遮らずに受け止める姿勢と、確認の声かけを意識的に実践するよう心がけています。
他職種との連携において、自分の意見をうまく伝えられず消極的になる場面があります。今後は、自分の意見を整理した上で、必要なときはしっかり発信できるよう、準備と練習を積みたいと思います。
記録業務に時間がかかり、定時を過ぎることが多くなってしまう点を課題と感じています。文章の簡潔さや優先順位を見直し、時間管理能力の向上を図るとともに、事前準備の工夫も取り入れています。
利用者様の行動や表情の細かな変化を見逃すことがあり、観察力の強化が必要だと感じています。看護師からの助言や他の職員の視点を学びながら、日々の業務で注意深く観察する習慣を意識しています。
「苦手なこと=評価が下がる」ではありません。上司は“課題に向き合う姿勢”を見ています。



僕が自己評価をチェックする立場でも、正直に書いた内容+前向きな一文があると、すごく信頼できますよ。
⑤長所・短所の自己評価例文
自己評価シートで「長所・短所」を書く欄があると、何を書けばいいか迷う方が多いです。ここは自分の“クセ”や“傾向”を素直に振り返りつつ、職場にどう活かしているか/活かしたいかを添えるのがコツ。僕も評価者として、ここはけっこう見ています。



長所の例文について、以下のようなものはいかがでしょうか。
私の長所は、利用者様との信頼関係を築くスピードが早いことです。初対面でも緊張を与えず、自然な笑顔と柔らかい声かけを意識することで、安心していただける関係性を築けていると感じています。
チーム内の雰囲気を柔らかくすることが得意で、感情的になりやすい場面でも落ち着いて対応するよう努めています。急なトラブル時にも冷静に対処することで、周囲にも安心感を与えられるよう意識しています。
細かい変化に気づく観察力があり、利用者様の体調や表情の違和感を早めに察知できることが強みです。気づいた点はすぐにチームへ共有し、早期対応に貢献できるよう努めています。
私の長所は、利用者様の話にしっかり耳を傾ける姿勢です。たとえ忙しい時間帯であっても、相手の表情や語調を丁寧に観察し、安心していただけるようなコミュニケーションを意識しています。聞き手としての姿勢は、利用者様だけでなく、ご家族や他職員との信頼関係にもつながっていると感じています。



短所の例文も以下に記載します。
私の短所は、完璧主義な一面があり、業務中に細部まで気を配りすぎてしまうことです。その結果、時間配分が偏りがちになるため、今後は業務全体を俯瞰し、優先順位を柔軟に調整する力を意識的に高めていきたいと考えています。
一方で、慎重すぎる性格から、判断が遅れてしまう場面もあります。特に初めての業務に対して自信を持てないことがあり、今後は経験を積みながら少しずつ判断力を鍛えていきたいと考えています。
自分の短所は、責任感が強すぎて他人の仕事まで抱え込んでしまうところです。周囲に頼ることも必要であると自覚し、最近では業務の一部を任せるなど、バランスを取る工夫を始めています。
感情が表に出にくいタイプで、誤解を招くことがある点は課題です。最近は、自分の気持ちを簡単な言葉で伝えることを意識し、信頼関係の維持につなげています。自分自身も成長を感じている部分です。



長所は遠慮せずしっかりアピールしてOKですし、短所も「改善の意識」とセットで語れば印象が良くなります。僕も指導する際は、“人柄や姿勢がにじむ自己評価”を評価しています。
書き方に迷わない!介護職員の自己評価シートの基本と注意点
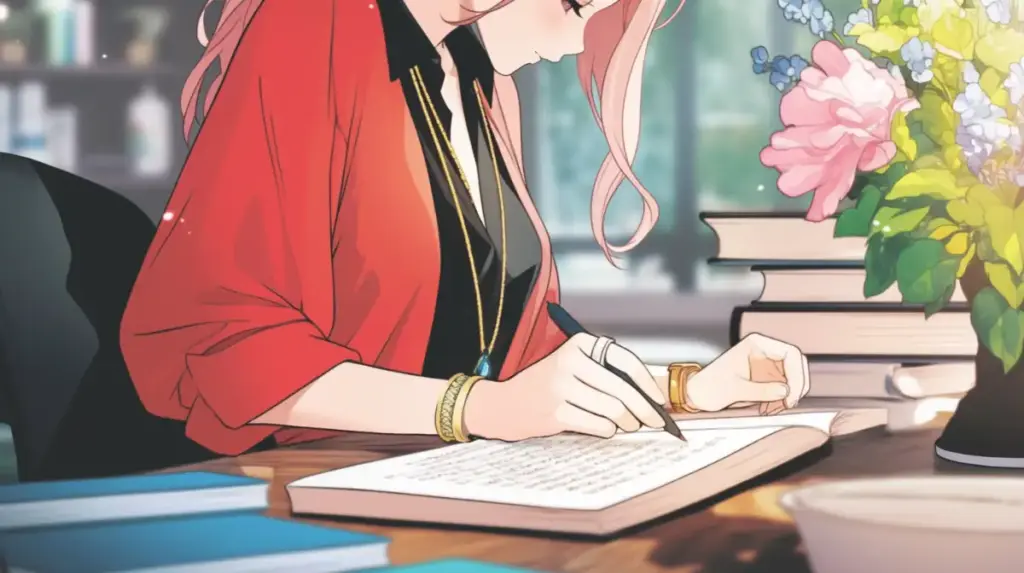
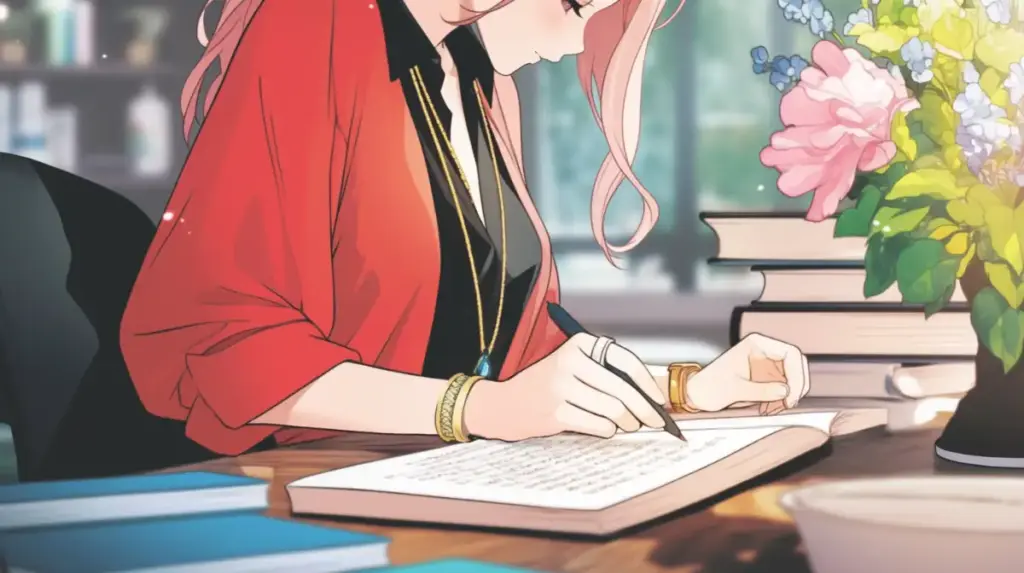
「そもそも自己評価って、どうやって書けばいいの?」と悩む方も多いと思います。ここでは、僕の現場経験から感じた“正解に近づく自己評価の書き方”をお伝えします。



ここを押さえておくことで、評価されやすい“伝わる自己評価”に変わりますよ。
①介護職員の自己評価シートって何?なぜ必要?
自己評価シートは、現場での自分の取り組みや課題を言語化し、上司や管理職と共有するためのツールです。評価制度の一環として導入されることが多く、僕の職場でも年2回は記入しています。
なぜ必要かというと、単に「上司に評価されるため」ではなく、自分自身の成長を振り返り、次の目標を考えるきっかけになるからです。
例えば、普段の仕事の中で「当たり前」になっている行動も、自己評価を書くことで初めて「これ、自分の強みかも」と気づくことがあるんです。
逆に、「いつも忙しさに流されて、じっくり考えてなかった」と反省点が見えることも。
評価する側としても、「この職員はどこを頑張っているのか」「どこに課題を感じているのか」が見えることで、支援の方向性や指導のアプローチが変わってきます。



だからこそ、形式的に書くのではなく、「今の自分をちゃんと見つめ直す機会」として活用するのが大事なんです。
②自己評価シートにありがちな失敗例とNG表現
ここ、すごく大事なポイントです。僕が上司としてチェックしていると、こんな自己評価が多くて「もったいないな」と思うことがよくあります。
- 「頑張りました」「努力しました」だけで終わっている
- 抽象的すぎて、何をしたのかが伝わらない
- 「特になし」「思い当たらない」と書いてしまう
- 課題や苦手なことに触れていない(完璧すぎて逆に不自然)
- ネガティブに書きすぎてしまい、自己否定っぽくなっている
例えば、「ご利用者様とよく話すようにしています」というだけでは伝わりません。
「1日3回は必ず話しかける」「名前を覚えて毎日声をかける」など、数字や具体的な行動を入れることで、評価する側も「お、やってるな」と納得します。



また、課題を書くときも「私はダメだ」ではなく、「○○が課題です。今後は〜したいと思います」というふうに、前向きな言葉で締めるのがポイントです。
③例文の選び方ガイド|あなたに合うパターンを見つけよう
先ほど紹介した「例文32選」の中から、自分に合う表現を選ぶときのコツをお伝えします。僕も後輩に自己評価の書き方を教えるときは、ここを重点的に伝えています。
①自分の立場に合っているか?
新人なら「学ぶ姿勢」、中堅なら「指導や連携」、ベテランなら「組織への貢献」など、立場ごとの評価ポイントは違います。同じ文章でも、立場とズレていると評価されづらいです。
②「これは自分が本当にやっているか?」
例文が立派でも、自分に当てはまらないことを書くと、面談でツッコまれて苦しくなります。あくまで“自分の言葉”で書ける内容にするのが◎です。
③文章を「組み合わせる・編集する」こともOK
例文は一語一句使うよりも、「この文とこの文を組み合わせる」「少し言い回しを変える」など、自分仕様にカスタムすると、より自然な文章になりますよ。
もしどうしても迷ったら、「上司は何を見てるか?」の視点で選ぶのがおすすめです。



僕自身も部下の評価を見るときは、「この人はどう成長したいのか?」「自分をどう見てるのか?」を重視しています。
【実践テク】上司に高評価されやすい自己評価の書き方5つのコツ


「一応書いたけど、なんとなく無難になっちゃう…」「どうすれば評価されるの?」そんな声に応えるべく、僕が20年の現場で培ってきた“伝わる自己評価の書き方”を5つにまとめました。



どれも、ただの“テクニック”ではなく、読み手への配慮と思いやりです。それでは解説していきます。
①目的を理解して“伝わる言葉”で書く
自己評価は「良く思われるための作文」ではなく、「自分の業務を振り返り、これからの目標につなげるもの」です。
この“目的”をちゃんと意識するだけで、評価される文章になります。
たとえば「笑顔で対応しています」だけでは抽象的すぎて伝わりませんが、「利用者様が不安を感じている場面でも、安心できるよう声のトーンや表情に注意して接するよう意識しました」と書けば、読み手に伝わります。



文章は短くても構いません。“伝える”ことが目的だと意識すれば、自然と内容が変わってきます。
②抽象語ではなく具体エピソードを入れる
評価されやすい自己評価には、必ず“具体的な行動”が書かれています。「努力しました」「丁寧に対応しました」では、読む側に何も伝わりません。
例として、「清潔保持に努めました」だけではなく、「毎日ご利用者の排泄後の陰部洗浄を徹底し、皮膚トラブルが起きないよう清拭と観察を行いました」とすると、あなたが普段からどのようなことを努力しているのかが明確に伝わります。



このように、「いつ・どこで・誰に・どうしたか」を簡単にでも入れるだけで、一気に伝わりやすくなります。僕が見る立場でも、エピソードが入っていると評価しやすいんです。
③「できたこと+今後の目標」で成長を示す
自己評価は“現在の棚卸し”であると同時に、“未来への宣言”でもあります。
たとえば、こんなふうに書くと自然に伝わります。
「利用者様との関係づくりに苦手意識がありましたが、挨拶や声かけを意識することで少しずつ会話が増え、自信につながりました。今後は信頼関係をさらに深められるよう、趣味や生活歴への理解も意識していきたいです。」
評価する側としては、「この人は自分を客観視できていて、成長意欲があるな」と受け取れます。



完璧な実績よりも、“これからどう成長するか”を言葉にすることが大切です。
④NGワード&印象が悪くなる表現を避ける
いくら頑張っても、「伝え方」で損をしているケース、よく見かけます。避けたほうがいい言葉をいくつか挙げておきます。
- 「〜できませんでした」「あまり〜できませんでした」→ そのまま書くと自己否定に聞こえがち
- 「頑張ってるつもりです」「なるべく〜」→ 意志の弱さ、あいまいな印象
- 「特にないです」「思いつきませんでした」→ やる気がないように見える
これらの代わりに、「〜が課題と感じています」「〜に取り組んでいる最中です」など、ポジティブな表現を使うのがコツです。



僕も面談のとき、「言葉だけで印象って変わるなあ」と感じることがよくあります。
⑤上司目線を意識して差をつける
最後はちょっと上級テク。自己評価を書くときに「この文章を上司が読んだとき、どう感じるか?」を意識すると、ワンランク上の文章になります。
たとえば、「後輩のフォローを頑張りました」だけでは不十分ですが、「後輩が困っている様子に気づいたら自分から声をかけ、業務内容だけでなく精神的な不安の軽減も意識して関わりました」と書けば、“見ている視点”の高さが伝わります。
上司は、「この人はチーム全体をどう見ているか?」という視点でも評価していることが多いです。そこに気づいた上で自己評価を書くと、抜け出せますよ。



僕も正直、“ただ仕事をこなす人”と“全体を見て工夫できる人”では、評価に差をつけます。
転職にも使える!自己評価で見えた「あなたの強み」の活かし方


自己評価シートって、実は“今の職場のため”だけじゃないんです。僕は自己評価を書くたびに「自分って、どんな働き方が向いてるんだろう?」って気づかされました。
それって、まさに転職のヒントにもなります。



「今の職場、ちょっと合ってないかも…」そう思ったときの選択肢としても、ぜひ参考にしてください。
①自己評価は“転職の自己PR”にそのまま使える
転職活動では、必ずと言っていいほど「自己PR」や「志望動機」が求められます。そのとき、自己評価シートでまとめた自分の強みや課題が、そのまま役立つんです。
たとえば、「利用者様との信頼関係を大事にしている」と自己評価に書いていたなら、それはそのまま“自分らしさ”として転職の場面でも伝えられます。
逆に、課題として書いた内容も、「それに対して努力している」「工夫している」ことが言えれば、前向きな成長ストーリーになります。
僕もケアマネに転職したとき、現場で書いていた自己評価の内容が履歴書や面接での受け答えにそのまま生きました。



だからこそ、今のうちに“ちゃんとした自己評価”を持っておくのは、未来の自分の武器になると思いますよ。
②自分に合う職場を探すにはプロの力を借りよう
「今の職場、なんか違うかも…」「もっと自分の強みを活かせる環境ないかな」って思ったことありませんか?
そういうときこそ、自分の評価シートを見返してみてください。そこには、自分の“得意なこと”がちゃんと書かれているはずです。
ただ、自分だけで職場を選ぶのって難しいんですよね。給与や休みだけじゃなく、「どんな人が多いか」「人間関係はどうか」って、求人票には載ってません。
そんなときに助かるのが、介護職に特化した転職エージェントを使うことです。希望や不安、職場の雰囲気まで相談しながら、自分に合ったところを探してくれます。



自分の強みを活かせる職場を“プロと一緒に見つける”という選択肢はありだと思いますよ。
③おすすめの介護職専門エージェントを紹介
「じゃあ具体的に、どんな転職エージェントがあるの?」と思った方へ。介護職専門のエージェントって実はかなり種類があって、それぞれ特徴や得意分野が違うんです。
そんな方のために、今おすすめできる介護職向け転職エージェントを10社まとめた記事を用意しました。
サポートの手厚さ、未経験対応、職場の雰囲気の聞き取り精度など、選びやすいように比較してあります。





自己評価シートを書いた今だからこそ、「自分の強みが活きる職場ってどこだろう?」と考える良いタイミングかもしれません。ぜひチェックしてみてくださいね。
【まとめ】介護職の自己評価シートは成長のチャンスに変えよう


自己評価って、正直めんどうだったり、自信がなかったりしますよね。でも僕は、自己評価こそが“自分の強みや成長に気づけるきっかけ”になると思っています。
介護の現場で働く一人として20年、僕もたくさんの自己評価を書いてきました。
今では後輩や部下の評価も担当していますが、「自分の言葉で、丁寧に書かれている内容」はやっぱり伝わりますし、信頼につながります。
このページで紹介した例文を参考に、自分の経験や感じていることを、少しずつ言葉にしてみてください。
それができれば、評価の場面だけじゃなく、あなた自身の働き方を見直す良いきっかけにもなります。
もし、「今の職場でこの先もやっていけるのか不安」「もっと自分に合う環境があるかもしれない」と感じているなら、介護職向けの転職エージェント比較ページも、ぜひ参考にしてみてください。
自己評価は、ただの提出物ではありません。しっかり向き合えば、これからのキャリアに役立つ“土台”になります。



あなたの仕事が、もっと自分らしく、やりがいを感じられるものになりますように。



コメント