介護職の退職理由に「嘘」は通用する?リスクと伝え方を徹底解説!
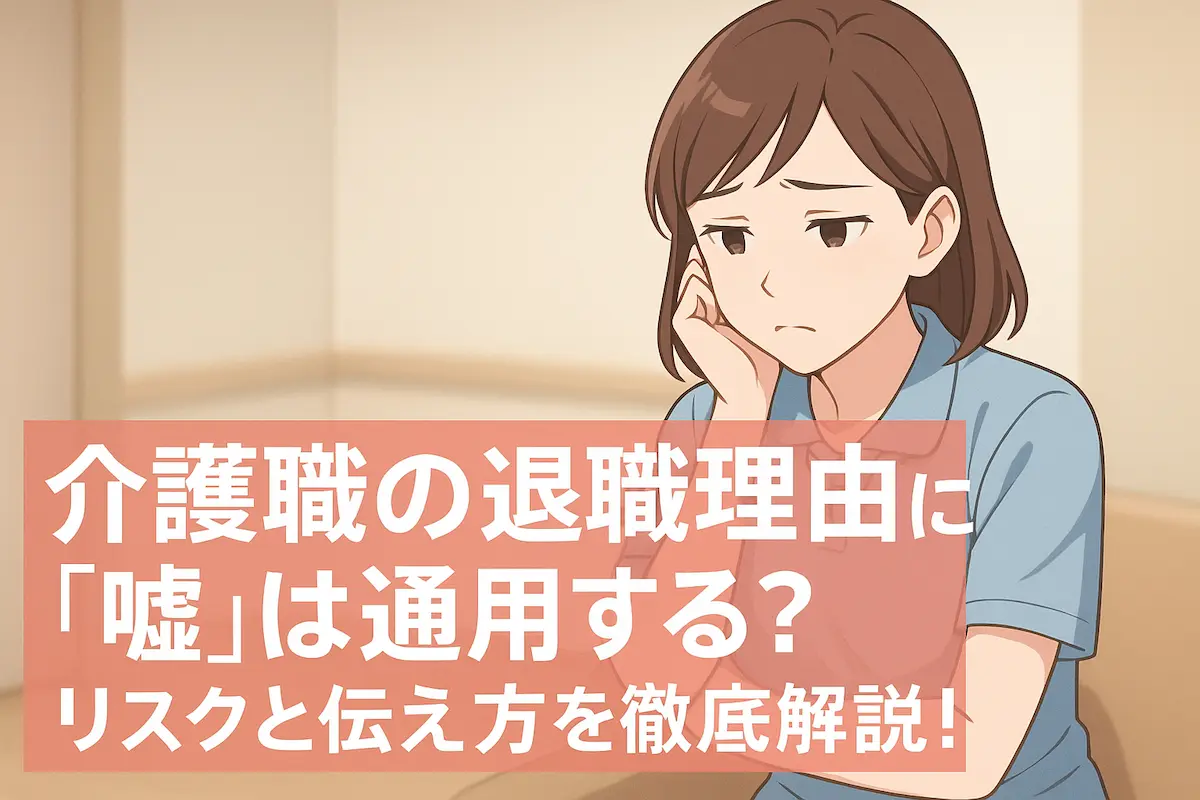
こんにちは。この記事を執筆している僕は、介護業界に20年間身を置き、現在は地域包括支援センターで主任ケアマネジャーを務めています。
ケアマネジャーとしての経験は13年になり、その間、多くの部下の退職相談に乗ったり、新規採用の面談に立ち会ったりしてきました。
そんな経験から、介護の仕事は、大きなやりがいがある一方で、心身ともに負担が大きい場面も少なくないことを実感しています。
退職を決意したものの、本当の理由を伝えづらく、「嘘の理由を使った方が円満に辞められるのでは…」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、介護職の方が退職理由で嘘をつくことの是非、考えられるリスク、そして円満退職に向けた賢い伝え方や手続きの進め方について、僕の経験も踏まえながら網羅的に解説します。
 よーかん
よーかん退職という大きな決断を後悔のないものにするために、ぜひ最後までお読みください。
- 介護職の退職理由に嘘を使うリスクと影響
- 嘘の退職理由が法的に問題になるかどうか
- 嘘を使わず円満に退職するための伝え方
- ネガティブな本音を前向きに変換する技術
介護職が抱える退職の悩み:なぜ「嘘の理由」を考えてしまうのか


介護職の方が退職を考える際、その背景には様々な悩みや事情が存在します。
まずは、介護職員が実際にどのような理由で退職を決意しているのか、そしてなぜ「嘘の理由」を検討してしまうのか、その深層心理に迫ります。
①:介護職の主な退職理由
介護労働安定センターの調査によると、介護職員の主な退職理由は以下のようになっています 。
| 順位 | 退職理由 | 割合 |
| 1位 | 職場の人間関係による問題 | 28.4% |
| 2位 | 施設・事業所への理念や運営方法に不満があったため | 22.5% |
| 3位 | 収入が少ないため | 20.4% |
| 4位 | 他に良い仕事がみつかったため | 18.2% |
| 5位 | 将来の見込みがたたないため | 15.0% |
| 6位 | 結婚・妊娠・出産・育児のため | 9.8% |
| 7位 | 新しい資格をとって活かすため | 3.4% |
出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査」より作成
1位の「職場の人間関係による問題」には、コミュニケーション不足や摩擦、パワーハラスメントやいじめの存在、チームワークの欠如などが含まれます 。介護現場はチームケアが基本であり、職員同士の密な連携が求められるため、人間関係のトラブルが仕事に直接影響しやすい環境です 。
2位の「施設・事業所への理念や運営方法に不満があったため」という理由には、具体的に「人手が足りず業務負担が大きい」(52.1%)、「仕事内容の割に賃金が低い」(41.4%)、「有給休暇がとりにくい」(26.2%)といった労働条件への不満が隠れています 。
また、入職前に聞いていた話と実際の運営が異なり、そのギャップにストレスを感じるケースも少なくありません 。
3位の「収入が少ないため」は、特に無資格の職員やパートタイムの職員が感じやすい不満です その他にも、入浴介助や移乗介助などによる腰痛といった「体力的なつらさ」や、夜勤を含む不規則な勤務時間も大きな負担となっています 。
これらの退職理由の多くは、職場環境や待遇、人間関係といったデリケートな問題を含んでいます。



そのため、正直に伝えることを躊躇し、「嘘の理由」を考えてしまう介護職員の方がいるのには、いくつかの心理的な背景があると言えるでしょう。
夜勤や入浴介助で大変な思いをしている介護職の現状についてこちらの記事で詳しく解説しています。
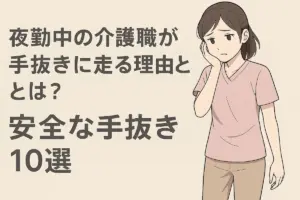
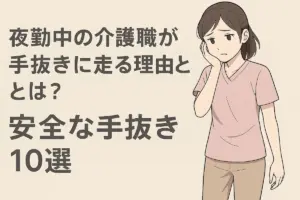
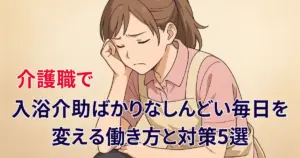
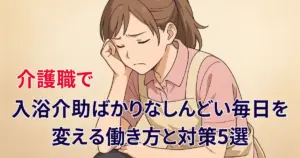
②:「嘘の理由」を考えてしまう心理的背景
介護職の方が退職理由で嘘を考えてしまう背景には、以下のような心理が働いていると考えられます。
引き止めや説得を避けたい
特に人手不足が深刻な介護業界では、退職を申し出ると強い引き止めに遭うことがあります 。
上司や同僚に迷惑をかけることへの罪悪感や、説得されることへの煩わしさから、波風の立たない「無難な理由」を求めてしまうのです。
円満退職を望む気持ち
本音を伝えて職場の雰囲気を悪くしたり、上司や同僚との関係をこじらせたりすることを避けたいという思いも、嘘の理由を考える一因です 。
日本の職場文化には、直接的な不満の表明を避け、波風を立てないことを重んじる「建前」の文化も影響しているかもしれません 。
本音を伝えることへの不安や恐怖
職場の人間関係や運営方針への不満など、ネガティブな本音を伝えることで、不当な扱いを受けたり、否定的な評価をされたりするのではないかという不安も、嘘の理由を選ぶ動機になり得ます。
特に、職場の人間関係や運営方針への不満が退職理由の上位を占めている現状は、一部の介護施設において、職員が直接的かつ正直なフィードバックを安全に行える環境が十分に整っていない可能性を示唆しています。
そのような環境下では、自己防衛のために「建前」や「嘘」の理由を用いることが、最も抵抗の少ない選択肢と感じられるのかもしれません。
社会的に受け入れられやすい理由への逃避
「親の介護」や「体調不良」といった理由は、個人的でやむを得ない事情として、職場側も強く引き止めにくい傾向があります。
これらは社会的に理解を得やすい理由であるため、追及を逃れるための「便利な嘘」として選ばれやすいのです。



しかし、安易に嘘の理由を使うことには、様々なリスクが伴います。次の章では、退職理由で嘘をつくことの是非と、具体的なリスクについて詳しく見ていきましょう。
退職理由で「嘘」をつくことの是非とリスク


退職理由を偽ることは、一時的にスムーズな退職につながるように見えるかもしれません。しかし、そこには倫理的な問題だけでなく、将来にわたる様々なリスクが潜んでいます。
①:法的に問題はある?
まず、退職理由を会社に伝える際に嘘をつくこと自体が、法的に問題になるのでしょうか。
結論から言うと、労働基準法や民法において、労働者が退職理由を正直に伝える義務は課されていません。
つまり、会社に対して本当の理由と異なる退職理由を述べたとしても、それ自体が直ちに法律違反となるわけではありません。
しかし、これはあくまで「会社に伝える理由」に限った話です。



失業保険の申請など、公的な手続きにおいて虚偽の申告をすることは、法的な問題に発展する可能性があります。
②:なぜ、嘘を理由にしてはいけないのか?
法的に問題がないとしても、嘘の退職理由を使うことは、当然ですが一般的に推奨されません。
その主な理由とリスクは以下の通りです。
倫理的な観点と信頼の失墜
嘘をつくことは、倫理的に褒められた行為ではありません。最も重要なのは「真実を適切に表現する」ことであり、安易な嘘は避けるべきです。
万が一、嘘が発覚した場合、職場からの信頼を大きく損なう可能性があります。特に介護業界は人の繋がりが比較的強い場合もあり、一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。
「責任感がない」というレッテルを貼られ、将来のキャリアに悪影響を及ぼすことも考えられます。
精神的な負担と矛盾の露呈
嘘をつき続けることは、精神的なストレスにつながります。いつバレるかと怯えたり、話の辻褄を合わせるために神経を使ったりすることは、想像以上に心身を消耗させます。
特に、家族の病気や自身の体調不良を理由に嘘をついた場合、その後の言動との矛盾が生じやすく、発覚した際の精神的ダメージは大きいでしょう。
複数の人に退職理由を伝える中で、説明に一貫性を持たせる必要があり、そのための労力も無視できません。
転職活動への支障
嘘の退職理由が、転職活動の際に不利に働くこともあります。
面接で退職理由について深く質問された際に、しどろもどろになったり、話の辻褄が合わなくなったりすれば、採用担当者に不信感を与えてしまいます。
前職の悪口や不満ばかりを述べるのも、「同じような理由でまた辞めるのではないか」「問題解決能力が低いのではないか」と見なされ、マイナス評価につながる可能性があります。
損害賠償請求の可能性(稀なケースと条件)
退職理由を偽ったこと自体で損害賠償を請求されるケースは極めて稀です。
しかし、嘘の理由が、会社に具体的な損害を与える行為と結びついた場合には、問題となる可能性があります。
例えば、「親の介護のため」と偽って退職し、実際にはすぐに同業他社に転職した場合、これが発覚すればトラブルになり、場合によっては損害賠償を請求されるリスクもゼロではありません。
これは、雇用契約における信頼関係を損なう行為と見なされる可能性があるためです。
ただし、会社側が退職者に対して損害賠償を請求できるのは、無断退職や引き継ぎの放棄によって会社に明らかな損害が生じた場合や、会社の機密情報を漏洩した場合など、限定的な状況に限られます。
単に「退職理由が嘘だった」というだけでは、法的に損害賠償が認められることはほとんどありません。
しばしば、退職を引き止めるための脅し文句として「損害賠償を請求する」という言葉が使われることもありますが、その多くは法的な根拠が薄いことを理解しておく必要があります。
離職票への影響と失業保険の不正受給リスク
ここが最も注意すべき点です。
会社に伝える退職理由と、公的な書類である「離職票」に記載される退職理由、そして失業保険の申請時に申告する理由は、整合性が取れている必要があるでしょう。
もし、失業保険を有利に受給する目的で離職理由を偽った場合、それは「不正受給」と見なされ、厳しいペナルティが科されます。
具体的には、受給した失業保険の全額返還に加え、最大でその2倍に相当する金額の納付を命じられる、いわゆる「3倍返し」の制裁があります。
悪質な場合には、詐欺罪として刑事告発される可能性も否定できません。
例えば、「本当は自己都合退職なのに、会社都合退職として離職票を作成してもらった」「体調不良で働けないと偽り、実際にはアルバイトで収入を得ながら失業保険を受給した」といったケースは、明確な不正受給にあたります。
会社に伝える「建前」の理由と、公的な手続きにおける「事実」は、明確に区別しなければなりません。
一時的な感情や都合で、取り返しのつかない事態を招かないよう、細心の注意が必要です。



このように、退職理由で嘘をつくことには、短期的なメリットを上回る多くのリスクが伴います。では、どのように退職理由を伝えれば、円満かつ誠実に退職できるのでしょうか。次の章で、具体的な伝え方のコツを見ていきましょう。
円満退職を実現する!退職理由の賢い伝え方
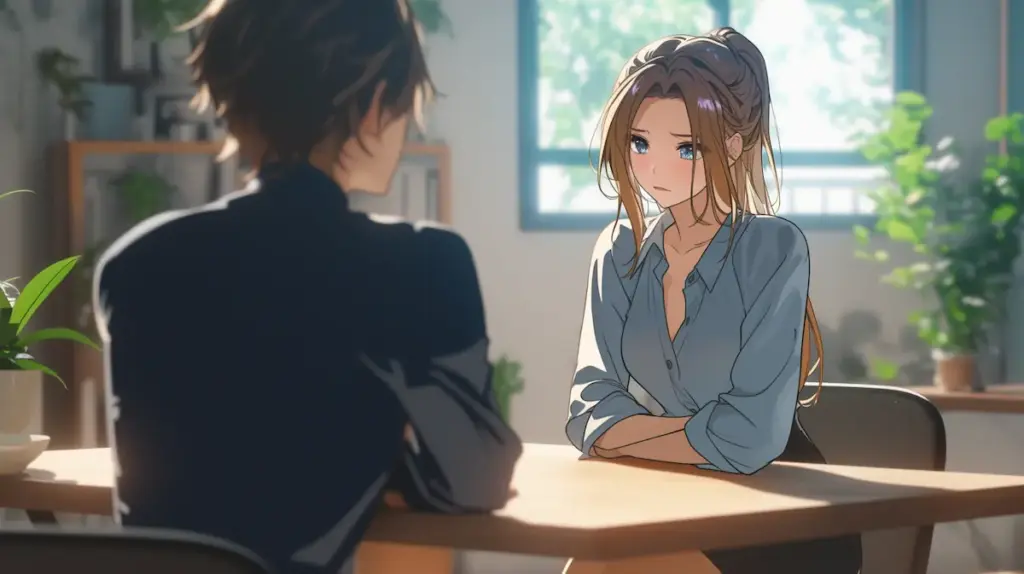
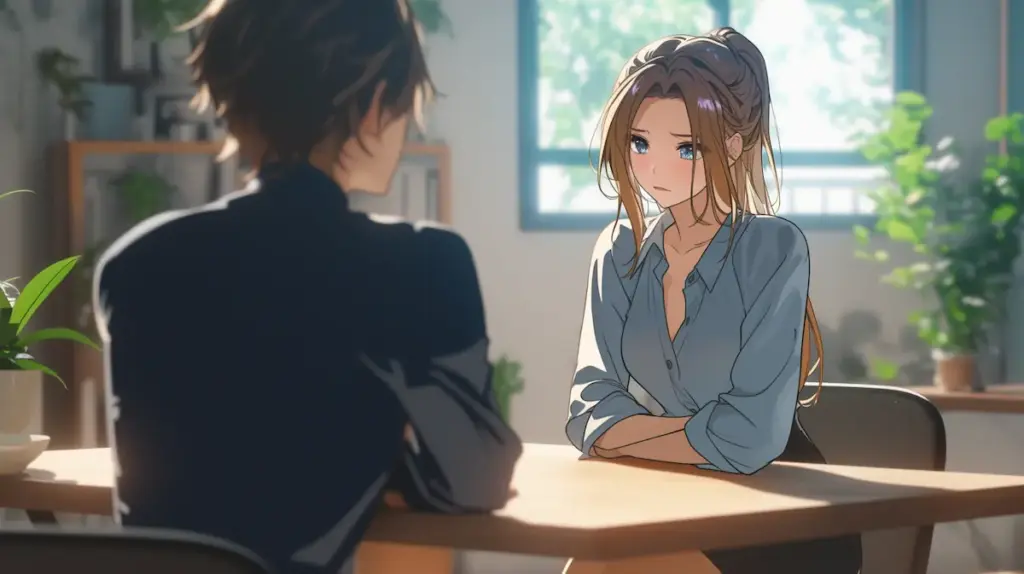
退職理由を伝える際には、正直さを基本としつつも、伝え方には工夫が必要です。
ここでは、円満退職を実現するための、賢いコミュニケーション方法と具体的な例文を紹介します。
①:「本音」と「建前」の境界線と上手な活用法
日本の職場文化では、直接的な物言いを避け、相手への配慮を示す「建前」が重視されることがあります。
退職理由を伝える際も、ネガティブな「本音」をそのままぶつけるのではなく、相手に不快感を与えない「建前」を用いることが、円満な退職につながる場合があります。
ただし、ここでの「建前」とは、全くの嘘をつくことではありません。
「真実を適切に表現する」ことが大切であり、本音をポジティブな言葉に置き換えたり、相手に配慮した表現を選んだりする技術です。



目的は、無用な対立を避け、スムーズな退職手続きを進めることにあります。
②:ネガティブな本音をポジティブな建前に変換する技術
退職理由が職場の環境や待遇に対する不満であっても、それをストレートに伝えると角が立ちやすくなります。
そこで有効なのが、「ポジティブ変換」の技術です。不満を「~ができなかったから辞める」という否定的な形ではなく、「これからは~がしたいから」という前向きな意欲として伝えるのです。
以下に、よくあるネガティブな本音と、それをポジティブな建前に言い換える例文をまとめました。
| よくあるネガティブな本音 | 円満退職のためのポジティブな建前例 |
| 人間関係が悪い・合わない人がいる | ・チームワークを重視しており、より協調性の高い環境で、これまでの経験を活かして貢献したいと考えています。 ・私自身が楽しく仕事ができる環境で、より力を発揮したいと考えています。 |
| 給料が安い・待遇に不満がある | ・これまでの経験や培ってきたスキルを活かし、成果がより正当に評価される環境で、自身のキャリアアップに挑戦したいと考えています。 |
| 仕事が体力的にきつい・残業が多い | ・これまでの経験を活かしつつ、自身の健康管理も考慮し、より持続可能な働き方を実現できる環境で、長期的に貢献していきたいと考えています。 ・自己の時間を大切にし、専門性を高めるための学習時間も確保したいと考えています。 |
| 事業所の運営方針や理念に不満がある | ・私自身の介護観を大切にしつつ、組織と同じ方向を向いて仕事がしたいと考えています。 ・貴社(現職の施設)の理念とは異なるアプローチで、新たな介護の可能性を追求してみたいという思いが強くなりました。 |
| やりがいを感じない・仕事内容が合わない | ・これまでの業務を通じて、新たな分野(例:在宅介護、予防介護など)への関心が高まり、専門性を深めたいと考えるようになりました。 ・より利用者様一人ひとりと深く関われる小規模な施設で、自分の理想とするケアを追求したいです。 |
このように、不満を直接的に表現するのではなく、「自分が何をしたいのか」「どのような環境で働きたいのか」という視点に転換することで、前向きな印象を与えることができるでしょう。



また、主語を「私」にする「アイメッセージ」(例:「私はこう感じた」「私はこうしたい」)を用いることで、表現が柔らかくなり、相手への配慮も伝わりやすくなりますよ。
③:具体的な退職理由の例文と伝え方のポイント
実際に退職理由を伝える際には、どのような言葉を選べばよいのでしょうか。
代表的な理由ごとに、例文と伝える際のポイントを解説します。
キャリアアップ・スキルアップを目指す場合
これは一般的に受け入れられやすい、前向きな退職理由です。
新しいスキルを習得したい、異なる介護分野(例:入所施設から訪問介護へ)で経験を積みたい、新しい技術を活用したケアに挑戦したいといった具体的な目標を伝えることで、説得力が増します。



現職で得た経験への感謝を述べつつ、将来の展望を具体的に語ることが大切です。
「体調不良」を理由にする場合
体調不良は、やむを得ない退職理由として比較的理解を得やすいものです。



現職で得た経験への感謝を述べつつ、将来の展望を具体的に語ることが大切です。
「家庭の事情」を理由にする場合
親の介護、結婚や出産・育児、配偶者の転勤などは、職場側も引き止めにくい、正当な退職理由と見なされやすいです。
「家庭の事情」はプライベートな内容であるため、詳細まで説明する必要はありません。ただし、完全に嘘の理由として使う場合は注意が必要です。
例えば、「遠方の親の介護」を理由にしたにも関わらず、近所で元気に過ごしているところを目撃されれば、嘘が露見する可能性があります 。
もし本当に介護が理由であるならば、上司から「要介護度は?」「どのようなサポートが必要か?」といった基本的な質問をされることも想定されます。



答えに困るようであれば、理由の信憑性が疑われてしまうでしょう 。
退職理由を伝える際は、単に「辞める」という事実を告げるだけでなく、これまでの感謝の気持ちを伝え、後任への引き継ぎを誠実に行う姿勢を示すことが、円満退職には不可欠です。
特に介護業界は、地域によっては人の繋がりが密接なこともあります。



良好な人間関係を保ったまま退職することは、将来のキャリアにとっても重要でしょう。
介護職のスムーズな退職交渉と手続きの進め方
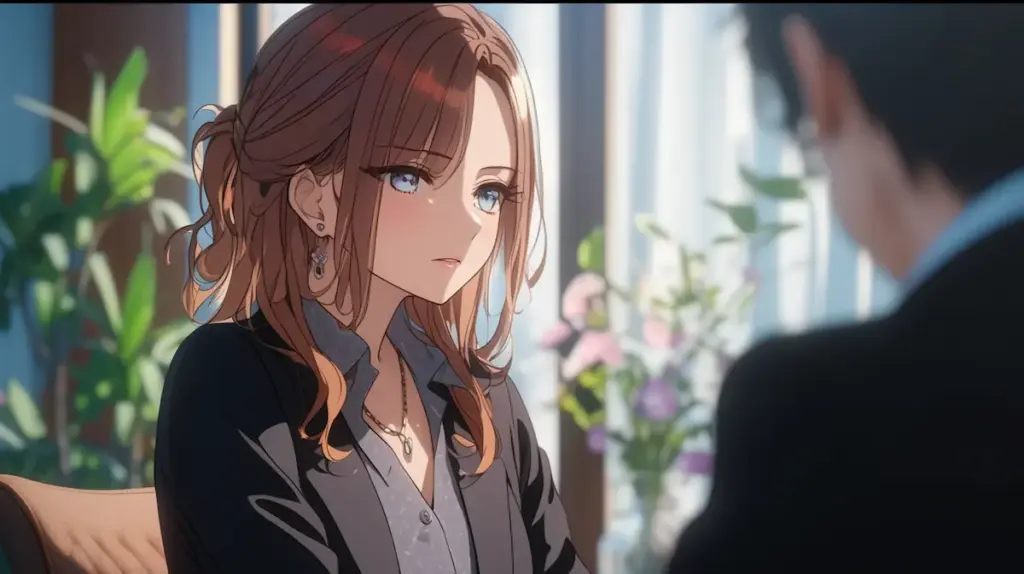
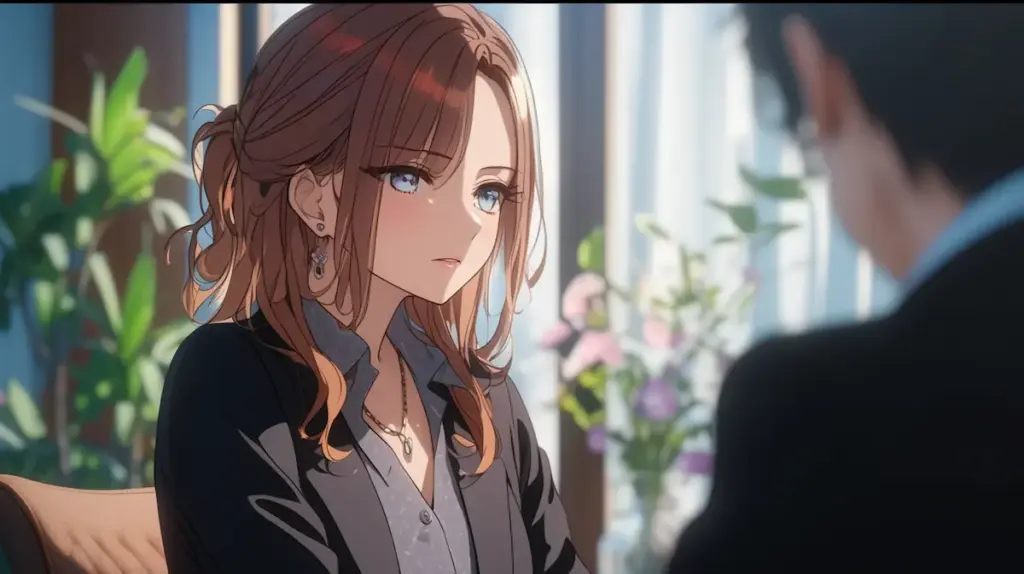
退職の意思を固めたら、次はその意思を職場に伝え、手続きを進める段階に入ります。
ここでは、スムーズな退職交渉と手続きのための具体的なステップと注意点を解説します。
①:退職の意思はいつまでに伝えるべきか(法律上の義務と職場の慣習)
退職を伝えるタイミングは、法律上の規定と職場の慣習の両方を理解しておくことが重要です。
法律上の義務
民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働者は退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約を解除できると定められています。
つまり、法律上は最短2週間前の通知で退職が可能です。就業規則と民法の規定が異なる場合、基本的には民法が優先されます。
職場の慣習・就業規則
多くの介護施設では、就業規則で「退職の申し入れは1ヶ月前まで」「2ヶ月前まで」といった規定を設けています。
円満退職を目指すのであれば、法律上の最短期間に固執せず、できる限り職場の就業規則に従うのが望ましいでしょう。
一般的には、退職希望日の1~2ヶ月前、理想を言えば2~3ヶ月前 24 に伝えるのがマナーとされています。
これは、施設側が後任者の採用や人員配置の調整、業務の引き継ぎに必要な期間を確保するためです。
年末年始などの繁忙期や、他のスタッフの退職が重なりそうな時期は、早めに申し出てもスムーズに辞められない可能性もあるため、時期の見極めも大切です。
法律上の権利と、円満な退職のための配慮とのバランスを考えることが求められます。



2週間で退職する権利はあっても、それを強行することで職場に大きな混乱を招き、結果的に後味の悪い辞め方になってしまう可能性も考慮すべきですね。
②:退職の伝え方:誰に、いつ、どのように伝えるのがベストか
退職の意思を伝える際には、相手や方法、タイミングに配慮することが、円満な退職への第一歩です。
誰に伝えるか
まず最初に、直属の上司に伝えるのが鉄則です。同僚や先輩に先に話してしまうと、噂が上司の耳に入り、心証を悪くする可能性があります。
いつ伝えるか
就業規則で定められた期日を確認し、シフト作成や引き継ぎ業務、自身の有給休暇の消化などを考慮して、余裕を持ったタイミングで伝えましょう。上司が忙しくない時間帯を見計らい、個別に話せる時間を設けてもらうのが理想です。
どのように伝えるか
- まずは口頭で
メールやLINEなどではなく、直接会って口頭で伝えるのがマナーです。
アポイントメントを取るか、上司の手が空いているタイミングを見計らい、「ご相談したいことがあるのですが、少々お時間をいただけますでしょうか」と切り出しましょう。 - 伝える内容
退職の意思、退職希望日、そして退職理由(前述のポジティブ変換や建前を活用)を明確に伝えます。この際、退職の意思が固いことをはっきりと示すことが重要です。 - 退職届の提出
口頭で伝えて了承を得た後、速やかに正式な退職届(または退職願)を提出します。退職届の様式や提出先については、上司の指示に従いましょう。
日本の職場文化では、重要な話を伝える際に、まず個人的な対話を通じて相手に心の準備をさせ、その後に正式な書面を提出するという手順が好まれる傾向があります。
いきなり退職届を突きつけるような形は、相手に冷たい印象を与えかねません。
③:強い引き止めに合った場合の対処法
特に人手不足の介護業界では、退職を申し出た際に強い引き止めに遭うことも少なくありません。そのような場合の対処法を心得ておきましょう。
- 明確な意思表示を貫く
退職の意思が固いのであれば、その旨を毅然とした態度で伝え続けることが大切です。
「あなたがいないと困る」「もう少し考えてほしい」といった情に訴える言葉に心が揺らぐかもしれませんが、一度決めたことであれば、曖昧な態度はかえって相手に期待を持たせてしまいます。 - 具体的な退職理由(建前)を再度強調する
「キャリアアップのため、〇〇の分野に挑戦したいという気持ちが強く、既に次の活動も進めております」など、現在の職場では実現不可能な目標や、既に退職後の道筋が決まっていることを伝えるのも有効です。 - 改善案や異動の提案への対応
もし退職理由が「人間関係」や「業務内容」であると伝えた場合、施設側から部署異動や業務改善を提案されることがあります。
本当に退職の意思が固いのであれば、「大変ありがたいお話ですが、今回は退職の意思は変わりません」と丁重にお断りしましょう。 - 不当な引き止めや脅しには屈しない
万が一、「損害賠償を請求する」「辞めさせない」といった脅しや不当な引き止めに遭った場合は、冷静に対処しましょう。
前述の通り、労働者には退職の自由があり、損害賠償請求が認められるケースは限定的です。
一人で抱え込まず、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することも検討してください。



退職交渉は、時に精神的な負担を伴うこともありますが、自身の権利を理解し、誠実かつ毅然とした態度で臨むことが重要です。
「嘘」に頼らない円満退職のための最終確認


退職という大きな決断を、後悔なく、そして円満に進めるためには、いくつかの重要なポイントを再確認しておくことが大切です。
安易な「嘘」に頼るのではなく、誠実かつ戦略的なコミュニケーションで、新たな一歩を踏み出しましょう。
①:重要なポイントの再確認
嘘のリスクを再認識する
特に、離職票の記載内容や失業保険の申請に関する嘘は、法的なトラブルや金銭的なペナルティに直結する重大な問題です。会社に伝える退職理由が「建前」であったとしても、公的な書類には事実を正確に記載する義務があります。
正直かつ建設的なコミュニケーションの価値
相手に配慮した「建前」や「ポジティブ変換」は有効なテクニックですが、その根底には誠実さが必要です。「真実を適切に表現する」ことを心がけ、感謝の気持ちや引き継ぎへの協力姿勢を示すことが、信頼関係を保ったまま退職するための鍵となります。
退職時期と引き継ぎの重要性
法律上の権利と職場の慣習を理解した上で、適切な時期に退職の意思を伝え、後任者への引き継ぎを責任を持って行うことが、円満退職の基本です。
②:誠実かつ戦略的なコミュニケーションの勧め
退職理由を伝える際は、感情的にならず、冷静かつ論理的に話すことが大切です。相手に不快感を与えないよう、言葉遣いにも注意しましょう。
- ポジティブな言葉を選ぶ
前述の通り、ネガティブな表現は避け、前向きな言葉を選びましょう。 - 「アイメッセージ」を活用する
「あなたは~だ」という相手を主語にする「ユーメッセージ」ではなく、「私は~と感じた」「私は~したい」という自分を主語にする「アイメッセージ」で伝えることで、攻撃的な印象を和らげ、自分の気持ちを正直に伝えやすくなります。 - 感謝の気持ちを忘れない
たとえ不満があって辞める場合でも、これまでお世話になったことへの感謝の言葉を伝えることで、相手の受け止め方も変わってきます。
「円満退職」とは、単に波風を立てずに辞めることだけを指すのではありません。
法的な権利や職場の慣習を理解し、適切なコミュニケーション戦略を用い、そして何よりも自分自身の将来にとって最善の選択をするための、実利的で賢明なアプローチです。
退職理由をどう伝えるかという決断は、時に大きなストレスを伴います。



しかし、この記事で紹介した情報が、介護職の皆さんがより良い情報を元に、よりリスクの少ない、そして自分らしい選択をするための一助となることを願っています。
③:僕がおすすめするエージェントをまとめました
もし、退職や転職に関して一人で悩んでいるなら、転職エージェントに相談するのも一つの有効な手段です。
僕自身も、キャリアに悩む部下や知人にアドバイスを求められた際には、信頼できるエージェントの活用を勧めることがあります。





エージェントの人たちは多くの事例を見てきており、客観的な視点からあなたに合ったアドバイスや求人を紹介してくれるでしょう。
介護職の退職理由で「嘘」はNG?後悔しないための最終結論


介護職の退職において、「嘘の理由」を使うことは、一見すると円満退職への近道のように思えるかもしれません。
しかし、その背後には信頼失墜、キャリアへの悪影響、さらには法的な問題に発展するリスクまで潜んでいます。特に、失業保険の受給資格に関わる嘘は、深刻な結果を招きかねません。
大切なのは、安易な嘘に頼るのではなく、「真実を適切に、かつ建設的に伝える」技術を身につけることです。
ネガティブな本音も、ポジティブな言葉遣いや「アイメッセージ」を駆使することで、相手に配慮しつつ、自身の意思を明確に伝えることができます。
退職の意思を伝えるタイミング、相手、方法、そして引き継ぎの責任を果たすこと。これら一つひとつを丁寧に行うことが、円満な退職、そして次のステップへの円滑な移行に繋がります。
退職は、決してネガティブなことばかりではありません。自身のキャリアを見つめ直し、より良い未来を築くための大切な転機です。



この記事が、退職という大きな決断を前に悩む介護職の皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。



コメント